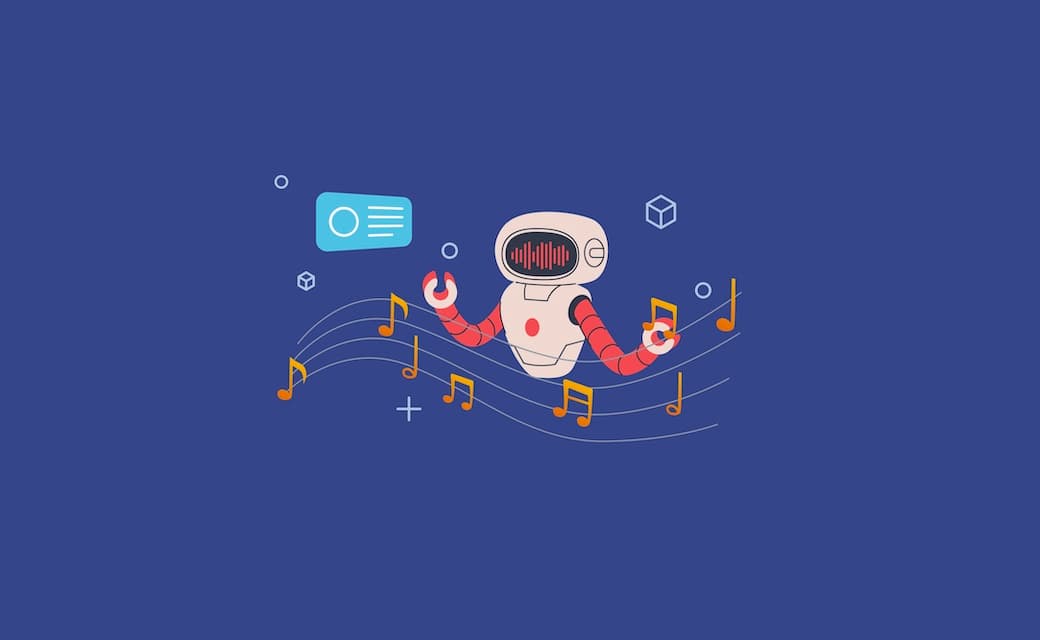Vision-Making in the age of AI — How artificial intelligence is transforming the meaning of work and the nature of organizations
However, these changes are far more than a matter of technological advancement. In recent years, AI-driven job displacement—so-called “AI layoffs”—has become a growing concern. The mass layoffs at Amazon, reportedly influenced by the use of AI, remain fresh in our memory (as of November 2025).
In this article, we explore the nature of the anxieties that have deepened since the rise of AI, identify the kinds of jobs that may be “taken” by AI and those that may emerge in its wake, and consider how organizations and companies should respond to this transformation. Above all, we examine what must be valued more than ever in this new era—why the age of AI is precisely when vision-making becomes essential.
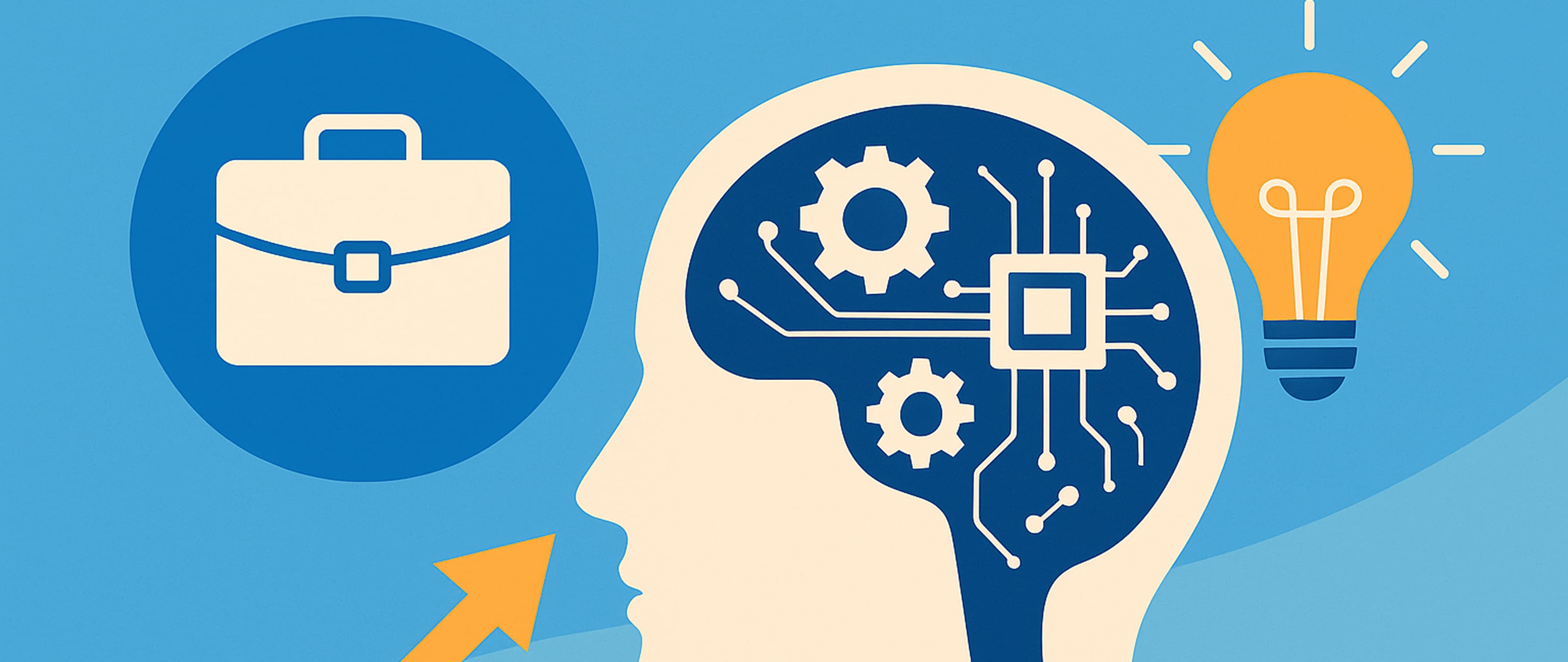
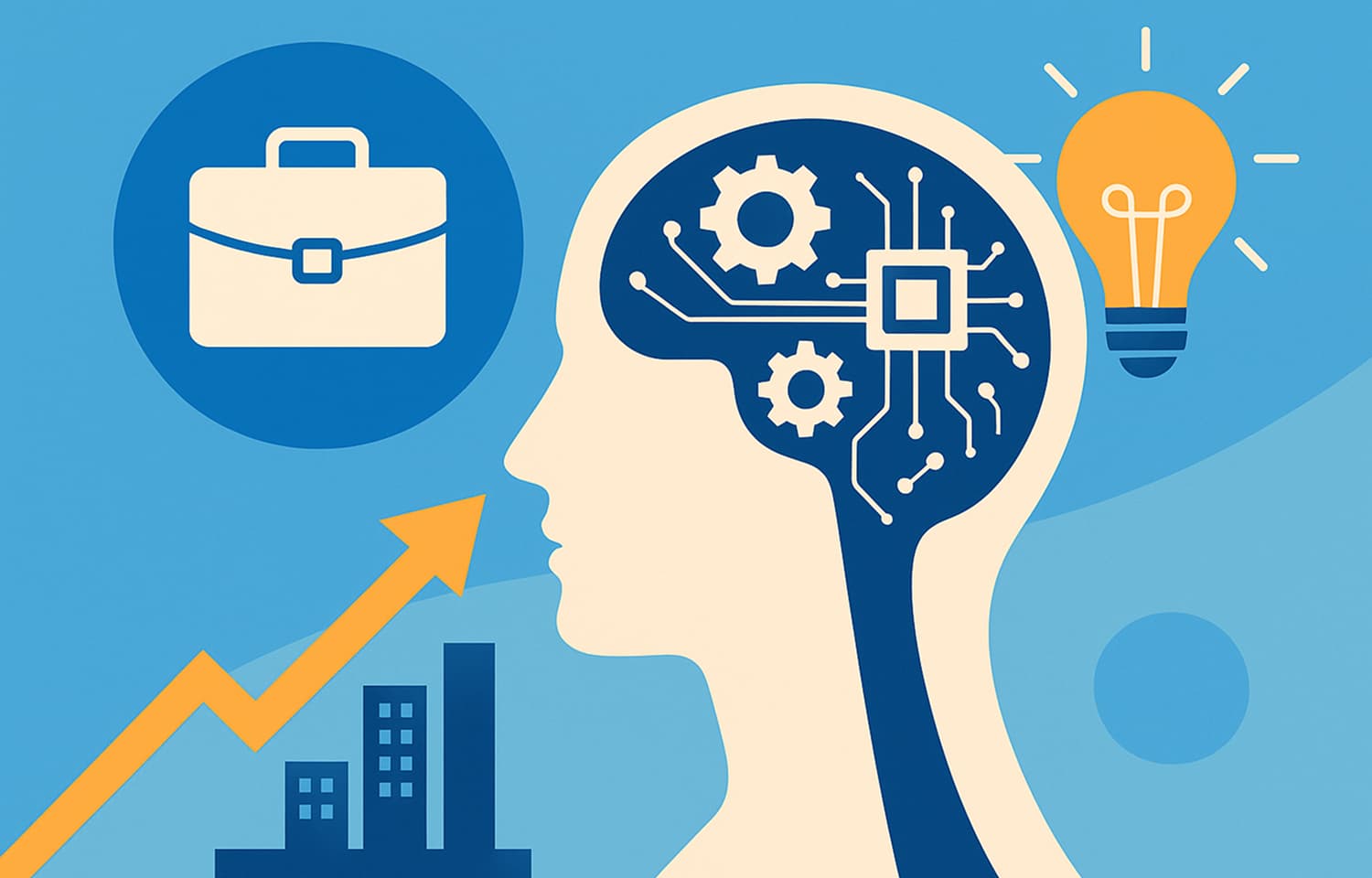
1. Inside the Social Anxiety Triggered by AI — Five Key Factors
AIが社会にもたらすのは、利便性だけではありません。これまでにない利便性を享受しながらも、一方で私たちの心の奥には「得体の知れない不安」が広がっているのも事実です。ここでは、その不安の中身を5つの主な要素に整理して洗い出してみましょう。
① 雇用不安 — 不可避な喪失と再配置の不透明さ
世界経済フォーラム(WEF)による「Future of Jobs Report 2025」では、今後5年間で約9200万人分の仕事が消滅する一方、1億7000万人の新しい職が生まれるとも予測されています。
つまり、仕事が“なくなる”のではなく、“入れ替わる”のです。昭和初期に人気職業だった電話交換師やタイプライターオペレーターが現在では姿を消し、代替される形で新たな仕事が生まれてきた歴史を想起してみましょう。
現在私たちは、その過渡期にあります。重要なのは、「自分のスキルは新時代で通用するのか」「どんな仕事に移行できるのか」といった“予想できない未来”に対して、多くの人が不安を抱えているという点です。
| 区分 | 職種例 | 変化の方向 | 主な要因 |
|---|---|---|---|
| 減少する仕事 | 事務職、データ入力、秘書、カスタマーサポート(一次応答) | 自動化・AI代替 | 定型作業の機械学習代替 |
| 増加する仕事 | データアナリスト、AIエンジニア、UXデザイナー、倫理・監査担当 | 新技術需要 | AI・データ関連の拡大 |
| 新たに生まれる職 | AI監督官、AI教育設計士、Promptデザイナー | 新産業・新役割 | 生成AIの普及 |
② 所得格差の拡大 — スキルプレミアムの上昇
AIの普及は、スキルを持つ人ほど高い報酬を得る「スキルプレミアム」の時代が到来しつつあります。すなわち、“AIを使う側”と“使われる側”の格差が生まれるという構図です。
日本においても、大企業と中小企業、都市部と地方との間で、“AI格差”による分断が現実味を帯びているという指摘があります。
ただし一方で、AIやロボットが機能的に人に近づけば近づくほど、「人間にできることは何か?」がより問われることになるという見方もあります。結果として、スキルだけでなく、人間的価値がこれまで以上に評価される時代が到来するかもしれません。
③ 心理的・社会的孤立 — 「働く意味の喪失」
人が働く理由は、収入だけではありません。社会との接点、仲間との協働、達成感──それらが「働くことの意味」を形成しています。ところが、AIの導入によって仕事のプロセスが分断・自動化されると、人と人とが関わる“余白”が失われる可能性があります。
確かに、無人販売店やネット購買の普及はその象徴です。人との接点が希薄になる中、「自分は何のために働いているのか?」という実存的な疑問を抱く人は少なくありません。これは、社会的な不安や無力感の背景にもなり得ます。
④ 制度(教育・社会保障)の追いつかなさ
AIが社会に浸透するスピードに対し、教育制度・職業訓練・社会保障などの制度設計はしばしば一歩遅れを取っています。従来の産業モデルを前提に構築された制度では、未来の働き方やスキル変化に対応しきれないのが実状です。
・リスキリング支援が一部の大企業に偏りがち
・中高年層への職業転換支援が乏しい
・AIによる業務変化に対応できる教育プログラムが整備されていない
これらの「制度の遅れ」は、社会全体の適応力を低下させ、結果として不安を増幅させる要因となっています。
⑤ 信頼の問題 — AIの判断に対する不信
私たちは、AIの分析や判断をあたかも“完璧”であるかのように信頼しがちですが、AIの判断が必ずしも「公正」ではないという点を忘れてはなりません。データの偏りや設計者の価値観が結果に影響を及ぼすケースがあります。特に、採用・ローン審査・医療診断といった、人の生命や人生に関わる領域では、AI活用には依然として大きな課題があります。
企業として問われるのは「AIをどう活用するか」ではなく、「AIをどう信頼性ある形で運用するか」です。AIの判断に対する責任の所在を明確にしておくことが、これからの時代において不可欠です。
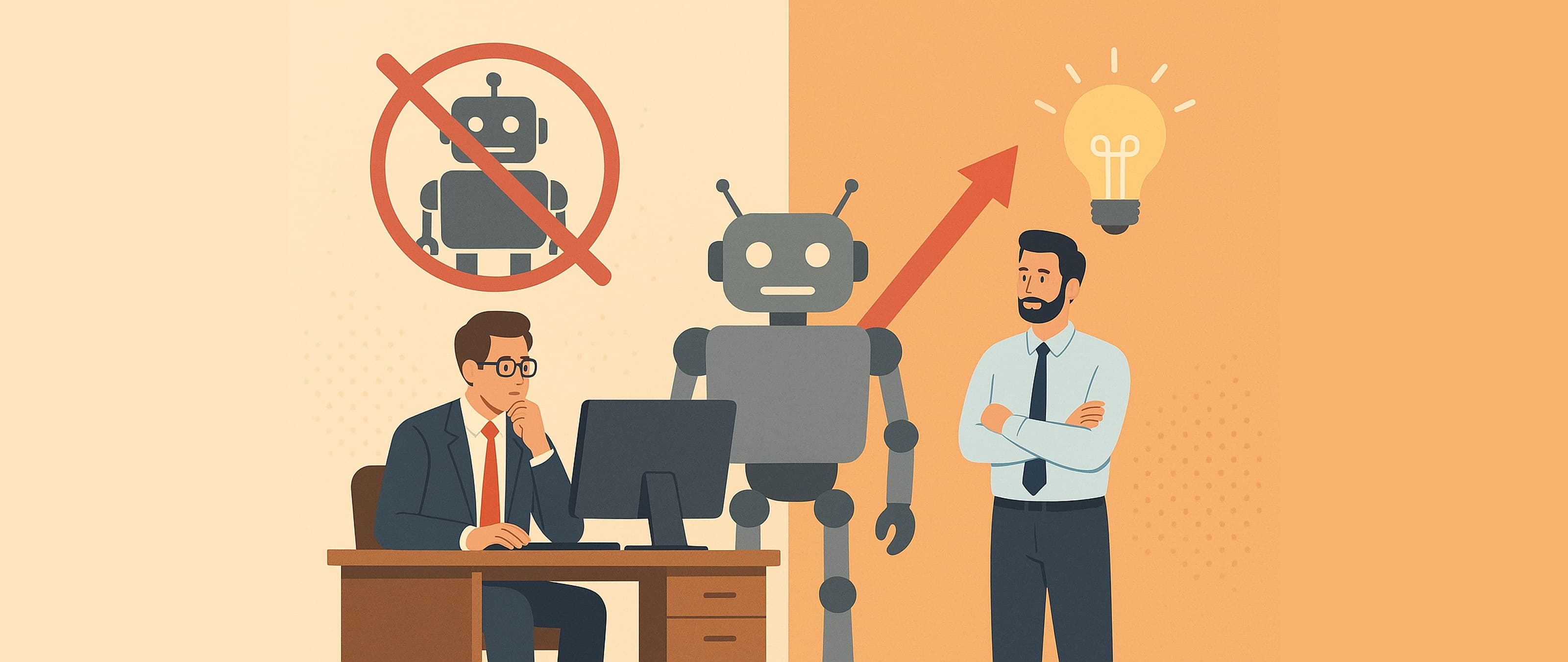
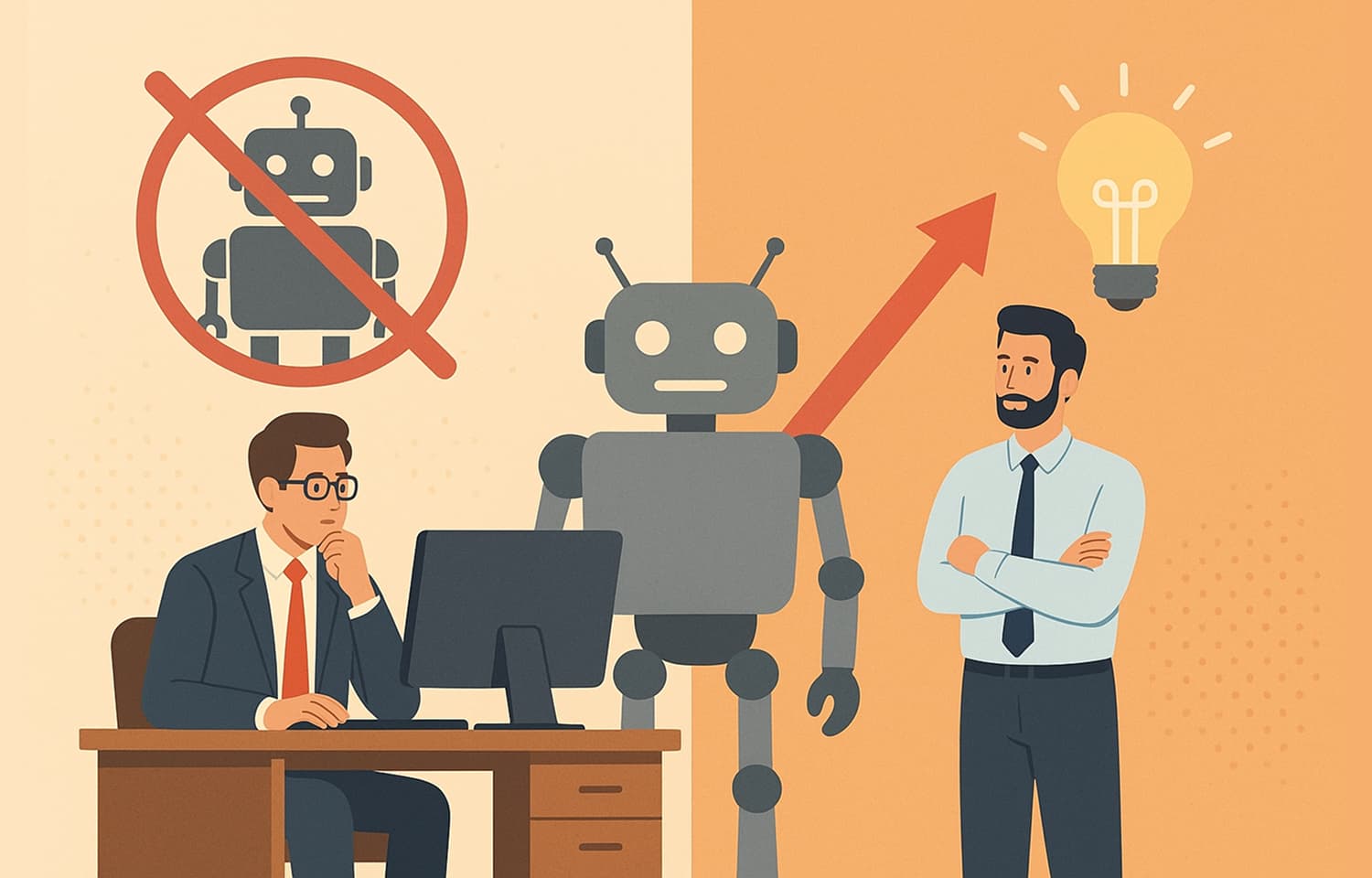
2. Jobs That Will Disappear in the Age of AI — and the Rising Value of Human Talent
AIが働き方を変えるのは確実ですが、すべての仕事が奪われるわけではありません。むしろ「人とAIが補完し合う新しい仕事」が次々と生まれていくと考えられます。以下では、「消えやすい仕事」と「生まれる仕事」を予測ベースで整理します。
2-1.なくなりやすい職業(高い自動化の可能性がある職業)
自動化の波が最も早く到達するのは、反復的・定型化された業務です。たとえば次のような分類が考えられます:
| 職種カテゴリ | 代表的な仕事 | 自動化要因 |
|---|---|---|
| 事務・総務 | データ入力、請求処理、契約管理 | RPA・RPA/AIによる処理自動化 |
| サービス業 | コールセンター、予約受付、FAQ応答 | 生成AIチャットボット |
| 製造・物流 | 組立・検品、倉庫ピッキング | ロボティクス/画像認識 |
| 金融・保険 | 審査・査定、定型報告書作成 | AIリスクモデル |
| クリエイティブ下流 | 広告文案・バナー生成 | 生成AIの普及 |
ただし注意すべきは、「仕事そのもの」が消えるのではなく、「仕事の中の一部タスク」がAIに置き換わっていくという点です。例えば広告制作においてAIがラフ案を生成し、人間がコンセプトや最終判断を担う、というような人とAIの分業構造が進行しています。
AIによって“奪われる“のではなく、AIをどう使うか?という主体的な姿勢が問われているのかもしれません。しかし、職種によってはAIはそもそも必要ない可能性もあることを付記しておきます。
2-2. 生まれる/伸びることが予想される職業
AIが進化するほど、それを“使いこなす側”の需要は増します。また、人にしかできない領域(共感・創造・倫理判断)への価値も並行して高まっていくでしょう。AIの進化によって、次のような領域の需要が高まると予測されます:
新たに伸びる仕事の領域
・AI・データ関連職
→AIエンジニア、データアナリスト、プロンプトデザイナーなど
・人間中心設計・UX領域
→人がAIを安心して使える体験設計を担う専門家
・教育・リスキリング支援職
→AIを使う“人”を育てるトレーナー
・倫理・ガバナンス関連職
→AIの透明性を監査・設計する専門職
創造・コミュニティ領域
→AIが模倣できない“物語”や“共感”を生み出す職種
職種やスキルに関しても以下の図表にまとめてみました。
| 分類 | 代表職種 | 必要スキル | 補足 |
|---|---|---|---|
| 技術 | AIエンジニア、MLリサーチャー | Python、統計、アルゴリズム | 専門性高 |
| 実装 | データアナリスト、業務DX推進 | SQL、BIツール、課題設定 | 企業導入領域 |
| 人文 | UXデザイナー、ナラティブ設計 | 行動心理、デザイン思考 | “人間らしさ”の領域 |
| 組織 | AI倫理責任者、ガバナンス担当 | 倫理学、法務、AI理解 | 社会的信頼形成 |
2-3. 企業が取り組むべき“人材戦略”のポイント
AIを導入する際に最も重要なのは“技術”ではなく“人”です。AIを使うのも、価値を生み出すのも、結局は人だからです。主体が人であるというスタンスを変えてはいけません。そこで、企業が取り組むべき3つのポイントをご紹介します:
①スキルの可視化とリスキリングの仕組み化
社内人材のスキルマップを作成し、定期的に更新する
→ 学びを業務と接続する仕組み(“仕事しながら学ぶ”)が鍵
②ジョブ再設計と人間の価値領域の特定
AIに任せる領域と、人が担う“創造・共感・倫理”領域を明確化
→ 「AIにできない仕事」を再定義する
③理念を軸とした人材育成
「なぜAIを導入するのか」「何を守るために使うのか」を明確に
→ 社員が“恐怖ではなく目的意識”でAIを受け入れられる環境を作る
企業がAI時代においてどのような姿勢をとるべきか。その問いについて、次の章でさらに掘り下げます。
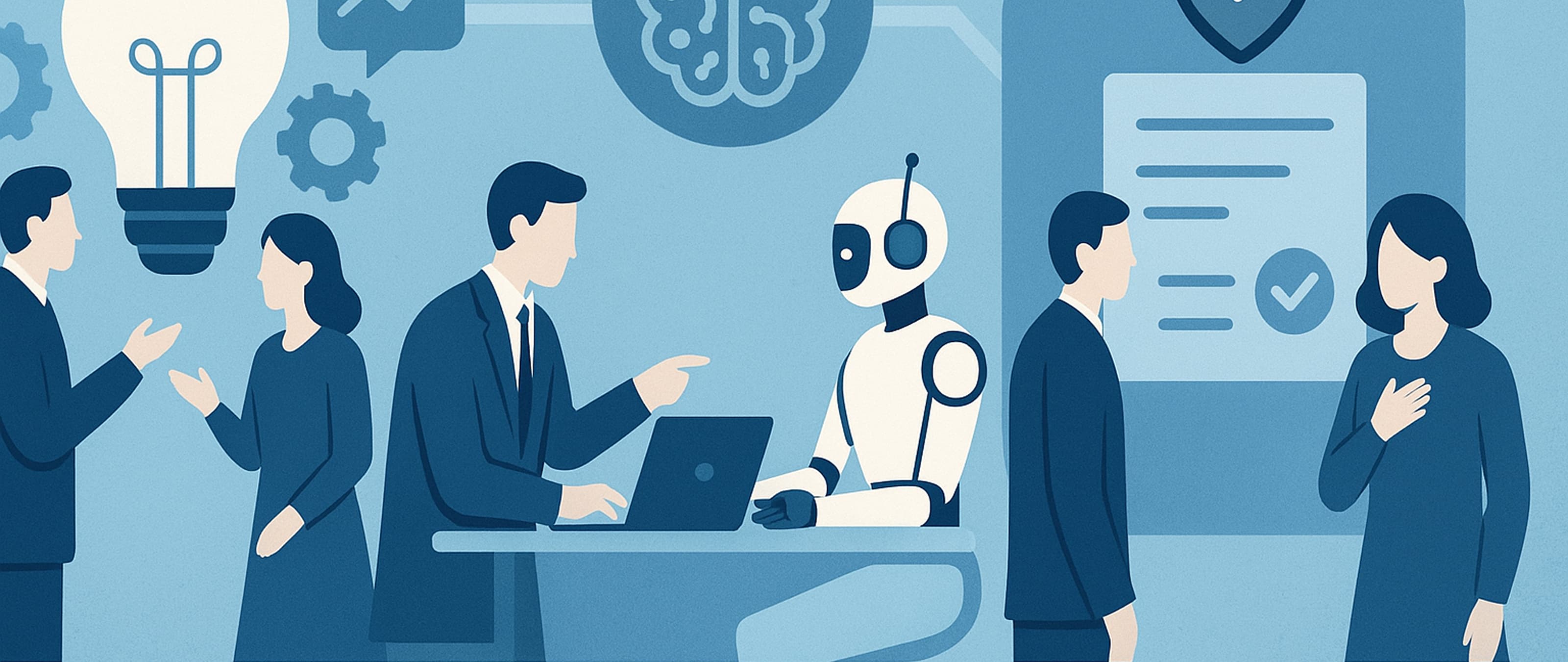

3. The purpose of companies in the age of AI — Reframing It from three perspectives
AIが社会構造を変える中、企業の存在意義そのものも根底から問い直されています。かつては生産性第一主義を掲げていた「効率を追う組織」から、今や「意味を提供する組織」へとアップデートが求められています。以下では、その変化を支える3つの観点を整理します。
3-1. 価値創造の再定義 — 顧客とともに学ぶ会社へ
AIは確かに生産性を劇的に高めますが、同時に“差別化”を困難にもします。誰もが同じツールを使える時代において、差を生むのは「何のためにそれを使うのか」という問いに対する答えです。とりわけ近年では、企業の存在意義を示す「パーパス」という言葉が、マーケティング界隈や経営層の間で頻繁に語られるようになりました。
今や、「自社は何のために存在しているのか?」「自社が実現したい未来(ビジョン)は何か?」といった存在意義を、明確に打ち出す必要性が一段と高まっています。
価値創造の視点においては、従来の“モノを売る”ビジネスモデルから、「顧客と共に未来をつくる」モデルへとシフトしています。データを通じて顧客との関係が深化する中で、企業は“顧客の学びの伴走者”として存在するかもしれません。
3-2. 人材と知識の組織化 — “AI×人”の共創体制をどう作るか
AIを単なるツールで終わらせず、組織知として活用するには、人とAIの役割分担を明確に設計する必要があります。たとえば、以下のような分担が考えられます:
| 領域 | AIが得意なこと | 人間が担うべきこと |
|---|---|---|
| 情報処理 | データ分析、パターン認識 | 問題設定、仮説構築 |
| 意思決定 | 過去データからの最適化 | 価値判断、倫理的選択 |
| 創造 | アイデア生成、組合せ提案 | 文脈理解、意味づけ |
| 組織運営 | 効率的アロケーション | 動機づけ、文化形成 |
AI導入を「効率化工具」と捉えるのではなく、「共創プラットフォーム」として設計すること。そうするためには、ナレッジ共有と学び合いの文化が組織に不可欠です。
3-3. 信頼と倫理 — 「AIをどう使うか」が企業の人格を決める
未来において、AIの使い方は企業の“人格”を映す鏡となるかもしれません。どのようなデータを使うか、どのように判断を監査するか──これらは自社ブランドの信頼そのものに直結します。以前なら“ゼロから何かを生み出すのが苦手”だとされたAIも、今では DALL‑E に代表される生成AIによって、文章の指示から多様で創造的なビジュアルまでも生成可能な状況にまで進化しています。そんな中、私たちはAIを「どう使うか」を問い続けているとも言えます。AIと向き合う姿勢こそに、企業のパーソナリティやアイデンティティが透けて見えてきます。
「AIをどう活用するか?それは何のためか?」という問いは、まさに「なぜ我々は存在するのか?」という自社の存在意義を考えることに等しいと感じます。単に「便利だから使う」ではなく、「我々の価値観に合うか?」という視点で導入を判断する姿勢がますます重要です。そのためにも、まず自社のMVVを明確にすることが求められます。
自社がどんな価値観を持ち、何のために事業を行い、どんな未来を実現したいのか――それが明示され、AI活用がその実現手段の一つとして有効であるかどうかを判断できる組織こそが、これからの時代を生き抜くと筆者は考えます。
「AIの活用」はあくまで手段です。AI導入・活用を目的化してしまうと、本来あるべき「人が主体」の立場から、AIに振り回されてしまう可能性があるのです。


4. A future where “Vision and Philosophy” become more important than ever
テクノロジーが進化すればするほど、企業や組織は“理念”を軽視しがちになります。なぜなら、AIや自動化の進展によって、目の前の「効率化」や「最適化」に意識が向かいやすくなるからです。しかし筆者は、まさにこのAI時代こそが「理念の時代」であると考えています。
AIは無限に近い手段をもたらします。課題解決の方法、業務の最適化、顧客アプローチの改善――これらはAIに任せれば、これまでにないスピードと精度で実現可能です。ただし、AIは“何をするか”“どこを目指すか”という“目的”を決めることはできません。
「なぜそれをするのか」「何を目指すのか」という“方向性”を定義するのは、あくまで人間の役割です。だからこそ、企業が持つビジョン(目指す未来像・展望・希望)や理念、存在意義、価値観が、AI活用の時代においては“判断の軸”として、これまで以上に強く作用します。
理念が曖昧な組織では、AIが出す“最適解”に振り回されます。データ分析や予測モデルが導き出した「もっとも効率的な道」が、必ずしも企業や社会にとって“正しい道”とは限りません。
短期的な利益を追い求めるアルゴリズムが、結果として従業員の幸福度や社会からの信頼を損なう可能性もあります。理念なきままAIを用いることは、方向を見失ったまま加速する自動運転車のようなものだとも言えます。
一方で、理念が明確な企業は異なります。AIが示す手段を選別し、自らの価値観に沿った「自分たちらしい最適化」を行うことができます。「効率よりも誠実を重んじる」「成長よりも共感を重視する」といった価値の優先順位が定まっていれば、膨大な選択肢の中から、価値観に合致した手段だけを選び取ることが可能なのです。
言い換えれば、AIはあくまで「道具」であり、理念こそがその道具を正しく使うための「人間らしい知性」となるのです。今後、企業間の差は「AIをどれだけ導入したか」ではなく、「理念をどれだけ深く持ち、それを軸にAIを活用できているか」で決まっていくでしょう。
つまり、AI時代における競争優位は、“技術の深度”ではなく“理念の深度”にこそ宿るのです。その深度が、組織の意思決定の一貫性、ブランドの独自性、そして社会からの信頼の厚みを形づくっていきます。
最後に — “AI時代の会社”を生きるために
AIが社会に浸透していくこれからの10年において、問われるのは技術を持つかどうかではなく、「どんな未来を望むか」です。企業も個人も、AIに“奪われる”立場ではなく、AIを“活かす”立場へと立てるかどうか。その差を生むのは、明確な理念と、学び続ける文化にあります。
未来の会社は、もはや単なる“経済単位”ではありません。社員・顧客・地域・社会──あらゆるステークホルダーと価値を共創するコミュニティへと進化していきます。AIはその進化を支える「道具」であり、理念はその進化を導く「灯台」なのです。
マーケティングの神様と言われるフィリップ・コトラーが自著で述べているように、私たち自身が人間である以上、テクノロジーとは協力しながらも、「人間らしら(ヒューマニティ)」や人としての幸せを模索していくべきなのではないでしょうか。
参考資料:
・World Economic Forum, Future of Jobs Report 2025
・McKinsey Global Institute, Jobs lost, jobs gained: What the future of work will mean for jobs, skills, and wages
・労働政策研究・研修機構(JILPT), 「AIの職場導入による働き方への影響等に関する調査(2025)」
・JBpress(牛窪恵氏ほか)記事「アマゾンは1万4000人、米国で進むAIリストラが日本で全く起きないのはなぜか?」
・保険市場(牛窪恵コラム)「企業の存在意義が問われている - AIがもたらすマーケティング革命」
RECENT POSTS

Vol.198
From parent–child bonds to community: The future of education that nurtures diversity and designs relationships

Vol.197
Exploring the future of environmental design integrating vision, diversity, and a future-oriented perspective

Vol.196
Vision-making for diverse and future-oriented education: Interpreting the future of learning through environmental design

Vol.195
“One Health” and Japan — Toward an Era of Integrating Humans, Animals, and the Environment

Vol.194
The benefits and challenges of digital education in the AI era, and the future of learning

Vol.193
Vision-Making in the age of AI — How artificial intelligence is transforming the meaning of work and the nature of organizations
TRENDING

Vol.164
Steps and strategies for internal branding to enhance employee engagement

Vol.160
What Small and Medium-sized Enterprises Should Do About Employer Branding

Vol.159
ユーザー行動をデザインする|UXの心理学と行動変容
INDEX
1. Inside the Social Anxiety Triggered by AI — Five Key Factors
2. Jobs That Will Disappear in the Age of AI — and the Rising Value of Human Talent
3. The purpose of companies in the age of AI — Reframing It from three perspectives
4. A future where “Vision and Philosophy” become more important than ever
最後に — “AI時代の会社”を生きるために