ブランド連想とパーセプション設計──消費者の頭に“ブランド”が宿る方法
本記事では、ブランド連想の概念整理やブランドパーセプション設計という視座、消費者にブランドが「宿る瞬間」を生む要因を詳らかにしていきます。
また、消費者の購買意思形成プロセスと接点や第一想起(Top of Mind)を獲得する具体的な施策、一貫性・ブランドロイヤルティとの関係をブランディングの初心者にもわかりやすく、かつ実践できるレベルで紹介します。


1.ブランド連想とは何か:パーセプションとの関係
まず最初に、ブランド連想とは何なのか?その定義とブランドパーセプションについて概要やブランド連想との関係、「認知」を重視するあまりに陥ってしまう「認知の呪縛」について紹介します。
1-1.ブランド連想の定義と機能
「ブランド連想」とは、消費者の頭の中でブランド名と特定のイメージや価値が結びつく、あらゆるものであり、また結びついた状態を指します。
例えば:
・「高級バッグ」→ ルイ・ヴィトン
・「エナジードリンク」→ レッドブル
・「ハンバーガー」→マクドナルド
誰しもがこうした連想を日々しているのではないでしょうか。これは、単なる「知名度の高さ」だけによるものではありません。ブランド連想とは、「特定の文脈で思い出される確率」であり、購買行動の第一歩なのです。
重要なのは、ブランド連想が単なる「知られている」状態(認知度)を超えて、ユーザーが“使う場面”や“課題解決の瞬間”に自発的に想起するかどうかです。この段階が達成されると、ブランドは検討対象の一角に入り、選択の可能性が高まります。
ユーザーがブランドに対して抱く連想は次の3層構造で形成されます。
| 層 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 機能的連想 | 製品の機能・性能 | 「速い」「軽い」「省エネ」 |
| 情緒的連想 | 感情や雰囲気 | 「安心」「楽しい」「上質」 |
| 社会的連想 | 立ち位置・文脈 | 「サステナブル」「挑戦的」「文化的」 |
この3層が一致しているほど、ブランドの記憶構造は強固になります。
1-2. ブランド連想とパーセプションの関係
ブランド連想は「何を思い出すか」を扱います。
一方でパーセプション(Perception)は「どう感じるか」を扱います。
・ブランド連想=“記号”としての想起
・パーセプション=“意味”としての印象
これら2つは不可分です。いくらブランド名を思い出しても、印象が悪ければ選ばれることはないでしょう。逆に、印象が良くても思い出されなければ購買機会は生まれないということです。
つまり、ブランド連想だけでは不十分で、「ユーザーがそのブランドをどう見ているか?(どう感じるか?)」問いいったブランドパーセプションの設計視点を取り込む必要があるのです。
そこで、パーセプションを形づくる5つの要因を利用して、ユーザーの頭にブランドを宿らせるパーセプション設計を行います。詳しくは、3章で紹介します。
1-3. 認知の呪縛
ブランド連想とブランドパーセプションの概要について理解したところで、「とにかく認知を獲得できればいいんだ!」と誤解してしまうケースがとても多いことにも触れておきます。
これは、第5章で消費者の意思決定プロセスにおいても取り上げますが、「認知」を獲得することは重要ですが、あまりにも認知獲得に比重を置きすぎている、いわゆる「認知の呪縛」にとらわれている起業家や経営者が多いのです。
どう認知されているのか?が重要であるのに、「認知されること」ばかりに注意が向きすぎて、本質を見誤ってしまうのです。
「知ってもらう」≠ユーザーにとっての「好き」とは限らないということを忘れないでおきましょう。だからこそ「認知を取ればいい」ではなく、「好き」を獲得するようユーザーにとってのブランドパーセプションを変えていくために何ができるのか?どういった知覚的刺激が必要なのか?といった中身が最も重要だということを付け加えておきます。


2.ブランド連想をつくるための6つの基本要素(理論と実例)
これまでブランド連想とブランドパーソナリティに関して見てきましたが、より具体的にブランド連想をつくる要素とそれらが何によって形づくられるのか?について見ていきます。
ブランド連想は多要素の積み上げです。ここでは主に実務で使える6つの基本要素を紹介します。各要素の重要点と短期〜中期で取れる施策を示します。
基本要素①:明確なブランドプロポジション(何を提供し、誰に刺さるか
曖昧なブランドは、曖昧にしか記憶されません。ブランドプロポジションとは、「自社が提供する価値」と「誰のどんな課題を解決するか」を明確にした約束のことです。ブランドプロポジションが明瞭であるほど、顧客の頭の中で「このブランド=〇〇な存在」として定着しやすくなります。
また、差別化された価値を言語化することで、コミュニケーションや表現の軸がブレにくくなり、組織内外の認識も揃いやすくなります。
具体的なアクション
まず、ブランドの存在意義を一文で示す「ブランドステートメント」を策定します。
次に、価値を支える柱となる「ブランドピラー」を設定し、機能的価値・感情的価値・社会的価値の3側面から検討します。
最終的には、「コアメッセージ(1〜3個)」に絞り込み、あらゆるコミュニケーションの基盤とすることがポイントです。
基本要素②:一貫したビジュアルとトーン(視覚・言語表現の統一)
人間の情報処理の約8割は視覚から得られるといわれます。したがって、ビジュアルと言語の一貫性は、ブランドを想起してもらうための「最短ルート」です。
例えば、ロゴ・色・フォント・トーン&マナーがバラバラだと、顧客はブランドを識別できず、印象が薄れてしまいます。逆に、一貫性のある表現は、短時間で「そのブランドらしさ」を思い出させ、信頼感を強化します。
具体的なアクション
ブランドガイドラインを策定し、ロゴ、配色、フォント、写真や動画のトーン、コピーライティングの文体などを定義します。
これをSNS、広告、店舗、Webサイト、パッケージなどすべてのコミュニケーションチャンネルで統一して運用することで、どこで接触しても同じ世界観を感じさせる「一貫したブランド体験」を築きます。
ブランドにおける「一貫性」の重要性については、第7章で改めて触れます。
基本要素③:シチュエーションベースのメッセージ(場面と結びつける)
消費者や顧客がブランドを想起するのは論理ではなく、「特定の場面」や「課題の瞬間」に紐づくときです。
例えば、「出勤前の忙しい朝」「子どもとの週末」「新生活を始めるとき」といった状況にブランドなどが結びつくと、潜在的なニーズ段階で想起されやすくなります。
つまり、ブランド連想は“文脈”とセットで記憶されるのです。
具体的なアクション
ペルソナごとの「顧客ジャーニー」を描き、各フェーズで顧客が抱く感情や行動を可視化します。カスタマージャーニーでも構いませんが、どういった行動にどういった感情が結びついているか、ターゲットではなくペルソナ規模で作成することが重要です。
その上で、「どんな状況で、どんな課題を抱き、どんな瞬間にブランドが役立つのか」をメッセージに落とし込みます。
広告コピーやSNS投稿、動画コンテンツなどは、その文脈に寄り添った「シチュエーション訴求」で設計すると効果的です。
基本要素④:タッチポイントの最適化(体験の連続性)
ブランド体験は、広告だけで完結しません。商品を手に取った瞬間、カスタマーサポートとのやり取り、配送時の梱包体験など、あらゆる接点が「ブランド連想」を強化もしくは損なう要因となり得ます。だからこそ一貫した顧客体験の積み重ねこそが、ブランドを“信頼できる存在”として記憶に定着させるのです。
具体的なアクション
顧客がブランドに触れるあらゆる接点、タッチポイント(Webサイト、店舗、メール、パッケージ、サポート対応など)を洗い出し、「タッチポイント監査」を行います。
それぞれの接点が、ブランドの世界観・トーン・価値を体現しているかを確認し、ズレがあれば改善します。
近年では、CX(カスタマーエクスペリエンス)設計の一環として、ブランドマネージャーとマーケティング部門が共同でこの監査を行う企業が増えています。
基本要素⑤: コンテンツとストーリーテリング(記憶に残る物語)
人は「事実」よりも「物語」でブランドを覚えます。人は断片よりも連続した意味であるストーリーの方が記憶に定着しやすい特性があるからです。ブランドの背景にある想い、創業者の原体験、ユーザーの成功事例など、感情に訴える物語があることで、単なる商品以上の「意味」が生まれます。
この意味づけが、顧客の中で情緒的な連想を形成し、第一想起(トップ・オブ・マインド)に繋がります。
具体的なアクション
ブランドストーリーを核に、コンテンツマーケティングを展開します。具体的には、創業エピソード、顧客のビフォーアフター、開発秘話などを記事・動画・SNS投稿として発信することです。SEO施策と連動させて検索経由の想起も高めると効果的でしょう。
また、ストーリーテリングのトーンをブランドピラーと揃えることで、「語り口」そのものがブランド体験になります。
基本要素⑥:リーチ+関連性(露出の最適配分)
どれだけ良いブランドであっても、知ってもらえなければ存在しないのと同じです。単なるリーチ(露出)や認知だけでは不十分で、「誰に・いつ・どの文脈で届くか」という関連性が伴って初めてブランド連想は形成されます。
つまり、“量”と“質”の両面での接触設計が鍵なのです。
具体的なアクション
ターゲットごとのメディア接触傾向を分析し、認知・関心・行動のフェーズごとに最適な媒体ミックスを構築します。
デジタル広告・PR・オウンドメディア・SNSコンテンツ・口コミなどをPESOフレーム(Paid, Earned, Shared, Owned)に基づいて整理し、露出の重複やギャップを最適化します。
また、キャンペーン単体ではなく、年間を通じて「想起の定常化」を意識したメディア運用が望まれます。
以上に紹介したブランド連想を形成する6つの要素は、単独で機能するものではありません。
ブランドプロポジションを核に、一貫した表現とストーリーを構築し、タッチポイントや露出戦略で体験を連続させる——この一連の設計によって、ブランドは顧客の頭の中に「意味あるイメージ」として定着します。
国内でもこうしたブランド連想構築を体系的に行う企業が増えており、特に中小企業においても「言語化」「ガイドライン化」「体験設計」の3ステップを実践することで、競合との差別化が実現しやすくなっています。


3.パーセプション設計:ユーザーの頭にブランドが「宿る瞬間」と5要因
ブランド連想とパーセプションの違いについて理解した上で、ユーザーの頭にブランドが「宿る瞬間」が生み出される要因について詳しく見ていきましょう。
ユーザーや顧客がそのブランドに対して抱く印象であったり、イメージや認識を総称してブランド・パーセプションと言いますが、パーセプションを形づくる要因は5つあります。企業側が本当に伝えたい価値と、ユーザーや顧客が抱くパーセプションとは必ずしも一致しません。
ユーザーの記憶や体験、社会的な情報などパーセプションを形づくる要因が深く関わってい流からです。5つの要因について紹介するとともに、「第一想起をつくる」観点から見た関係性やアクションプランに落とし込む方法も合わせて紹介します。
①ビジュアル・アイデンティティ(視覚表現)
②コミュニケーションの言語とトーン
③UX(ユーザー体験)
④第三者の評価(レビュー・SNS・メディア)
⑤社内的・文化的文脈(ブランドの立ち位置)
①ビジュアル・アイデンティティ(視覚表現)
ロゴ、カラー、フォント、UI構成、パッケージデザインといった「視覚的要素」は、人がブランドに抱く第一印象を大きく左右します。人はわずか数秒で「信頼できる/できない」「高品質/安っぽい」といった印象を判断しますが、その多くが視覚情報に依存しています。
人の特性上、視覚情報による情報取得が5感のうちで最も大きな割合を占めることからも、視覚的統一感は“信頼感”を生む鍵」であると考えていいでしょう。つまり、ビジュアルの一貫性はブランドの信頼性を補強し、認知の安定性を高める重要な要素なのです。
第一想起との関係
ブランドの視覚的特徴は、記憶のトリガーとして機能します。たとえば「青い背景に白い丸ロゴ」といえば、特定ブランドをすぐ思い浮かべる人も多いでしょう。このように、特徴的なビジュアルが頭の中で「検索キー」として働くことで、特定のブランドが第一想起として浮かびやすくなります。
視覚的な印象が記憶に残ることは、認知経路の短縮、すなわち「想起のしやすさ」に直結します。
具体的なアクション
・ブランドガイドラインを策定(ロゴ、カラー、フォント、写真構成、アイコンなど)
・広告・Web・SNS・パッケージ・店舗で統一感を保つ
・視覚要素だけでブランドが判別できる設計(ミニマルな差別性を加え、類似他社と区別)
②コミュニケーションの言語とトーン
ブランドは、単に商品やサービスを提供する存在ではなく、「声」を持つ人格として認識されます。キャッチコピーや記事文、SNS投稿、広告文など、ブランドが発する言葉の“語彙”と“口調”がその人格を形づくります。
ブランドの人格(ブランドパーソナリティ)を定義する上で、どのような語り方や語り口を選ぶかがブランドの世界観を支える重要な要素となります。
第一想起との関係
例えば、「〇〇のときには△△を使う」といったフレーズが繰り返し発信されることで、ユーザーの頭の中で特定のシーンとブランド名が自然に結びつきます。言葉の一貫した使用は、場面連想を促し、第一想起(Top of Mind)を強化する効果を持ちます。
具体的なアクション
・トーン&マナーを定義(話し方・語彙・文体・主語設計)
・コアメッセージ語句(スローガン・タグライン)を反復使用
・社内でライティング規範を文書化し、言葉遣いを統一
・内部チェックリストで一貫性を確認
③UX(ユーザー体験)
実際にブランドと接触したときの「体験」そのものがパーセプションを決定づけます。製品やサービスの使いやすさ、Webサイトやアプリの操作性、カスタマーサポートの対応など、体験の質が良ければ「信頼できる」「好きだ」という感情的評価が生まれます。
第一想起との関係
いくら広告で強い印象を残しても、実際の体験が悪ければ「名前は知っているけれど使いたくない」という逆効果を招くことがあります。
一方で、優れたUXは口コミを通じて肯定的な連鎖を生み、自然なかたちでブランド想起を強化します。体験から広がる記憶は、最も持続的なブランディング資産となります。
具体的なアクション
・顧客体験(CX)マップの作成と改善サイクルの構築
・Web/アプリの操作性最適化(表示速度・ナビゲーション・導線の明確化)
・問い合わせ・アフターケアの迅速かつ丁寧な対応
・感性に響くマイクロインタラクション設計
④第三者の評価(レビュー・SNS・メディア)
人は、自分が直接体験していないものでも、他者の意見や社会的評価から印象を形成します。レビュー、SNS投稿、インフルエンサーの発言、メディア報道などが「第三者の視点」として信頼形成に作用します。
他者の意見や社会的評価といった外部情報が潜在顧客の購買・消費行動に強く影響するため、ブランドの評判を左右する社会的信号としての役割として重要です。
第一想起との関係
「〇〇を使っている人が多い」「メディアで取り上げられていた」という情報は、ブランドを想起する際の補強要素として働きます。特に、検討前段階における“信頼性の裏づけ”として、第三者評価は想起経路を強化する重要な要因です。
具体的なアクション
・レビュー促進施策(購入後にレビュー投稿を依頼)
・SNSでユーザー投稿を引用・拡散
・メディア露出・PR記事の獲得
・信頼できるインフルエンサーの選定・活用
⑤社会的・文化的文脈(ブランドの立ち位置)
ブランドは孤立した存在ではなく、社会・文化の文脈の中で意味づけられます。SDGs、サステナビリティ、多様性、倫理といった社会的テーマとどのように関わるかが、ユーザーの共感を生みます。つまり、社会的潮流との接続がパーセプション形成に大きく影響するのです。
第一想起との関係
特定のカテゴリーにおいて、「環境に配慮するならこのブランド」「多様性を尊重する企業といえばここ」と想起されるようになれば、社会的価値観を軸とした差別化が成立します。理念に基づいた一貫した立ち位置は、第一想起の“意味的な深み”を形成します。
具体的なアクション
・企業理念・CSR・サステナビリティ方針の明確化
・社会的テーマに対する一貫した姿勢を継続的に発信
・社会貢献・共創プロジェクトをブランド活動と連動
+α(ブランド連想×パーセプション要因の統合モデル)
これまでの議論を踏まえると、ブランドの想起を高めるためには、単に広告やデザインの工夫を行うだけでなく、ブランド連想の「6要素」とパーセプション設計の「5要因」を統合的に設計することが重要です。
そこで、従来の「ブランド連想を作る6要素」と5つのパーセプション要因 を統合して、ブランド想起・印象設計の統合モデルを考えました。詳しくは、第6章にて統合モデルの深掘りをしますが、ここではまず、ブランド連想の6要素とパーセプションの5つの要因の関係性を整理してみました。
| 戦略軸(ブランド連想をつくる6要素) | 対応するパーセプション設計要因 |
|---|---|
| ブランドプロポジション(何を提供し、誰に) | ビジュアル・アイデンティティ(視覚表現) |
| 一貫性(表現の統一) | 言語とトーン(ブランドの声) |
| シチュエーション訴求(場面設計) | コミュニケーション言語(場面対応型メッセージ) |
| タッチポイント最適化 | UX+接触体験(実感的印象) |
| ストーリーテリング・物語化 | 社会文脈との連動(理念・文化的意義) |
| リーチと関連性(露出最適化) | 第三者評価(レビュー・話題形成) |
このように、ブランドパーセプションの5要因は、ブランド連想を形成する6要素と密接に結びついています。それぞれの要素を意識的に設計・統合することで、単なるイメージ形成を超え、「想起されるブランド」としての存在感を確立することが可能になります。
この統合モデルにより、単に「露出を増やす」や「場面広告を打つ」だけではなく、露出・体験・評価・社会文脈 を一体で設計して初めて、ブランドが「宿る瞬間」をつくることができます。

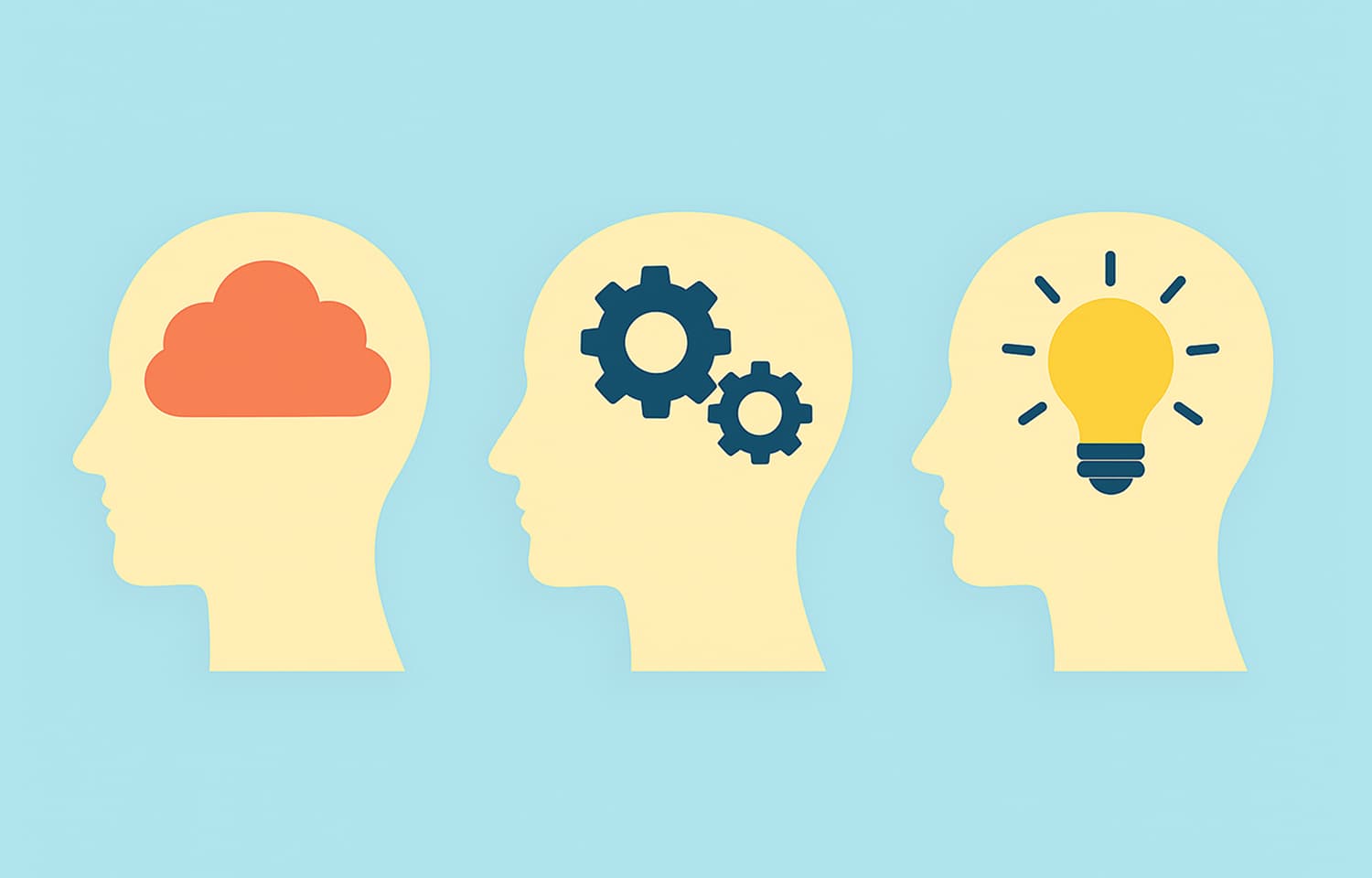
4.想起の種類:純粋想起・助成想起・第一想起(Top of Mind)の違いと意味
ブランドが記憶される過程は、「助成想起 → 純粋想起 → 第一想起」と段階的に進みます。
| 種類 | 意味 | 測定方法(質問例) |
|---|---|---|
| 助成想起 | 提示後に思い出す(提示(プロンプト)を与えたあとに回答する想起) | 「次の中で知っているブランドは?」(ブランドリストを提示して選んでもらう) |
| 純粋想起 | ヒントなしで思い出す(カテゴリやヒントを与えずに自由想起させる) | 「このカテゴリで思い浮かぶブランドは?」(自由回答) |
| 第一想起(Top of Mind) | 真っ先に浮かぶ(最も強く記憶されているブランド) | 「最初に思いついたブランドは?」(最初に挙げられたブランドを記録) |
マーケティング調査やブランディング設計で使う「想起」の概念は分類されます。各定義と示唆を整理します。
・助成想起(Aided Recall)
→ヒントやカテゴリ、あるいはブランドリストを提示して「あ、知っている」と答える想起。たとえば「次のリストの中で知っているブランドを教えてください」といった場面。助成想起は認知の幅を測るのに有効ですが、純粋想起よりは購買に結びつく力が弱いことが多いです。
・純粋想起(Unaided Recall)
→質問文などのヒントを与えずに、消費者が自発的にブランド名を挙げる想起。たとえば「洗剤ブランドを教えてください」と聞いてすぐに出てくるブランドが純粋想起です。純粋想起は、ブランドが頭の中に「自然に」存在しているかを示す強力な指標です。
・第一想起(Top of Mind)
→「そのカテゴリーで最初に思い浮かぶブランド」。純粋想起の中でも特に重要で、消費者が検討に入る瞬間に最も候補化されやすいブランドです。第一想起を獲得しているブランドは、広告投下や販促費を抑えても選ばれやすく、LTV(顧客生涯価値)やブランドロイヤルティ獲得に有利です。
ポイント
純粋想起→助成想起→第一想起の順に「購入への影響力」が高いと考えてください。Top of Mind(第一想起)を狙う施策は、単なる露出(認知度向上)よりも、「特定の課題/瞬間と結びつけること」に重きを置く必要があります。
第一想起率が最も高いブランドが「選ばれる」確率も高くなります。
パーセプション設計の目的は、 「思い出される確率」だけでなく「思い出されたときの印象」を一致させることです。つまり、「思い出された瞬間に、期待通りの感情が湧く」状態をつくることがゴールとなります。


5.消費者の意思決定プロセスと「検討前の瞬間(潜在ニーズ期)」の重要性
1-3.で「認知度の呪縛」について紹介しましたが、ユーザーにとってブランドとのタッチポイントが一つでも多くあり、企業・商品へのいい印象を消費者に抱いてもらえる機会を多く持つこと自体はメリットです。消費者として購買行動を行う際には、商品の企業名や商品名の認知度が高いほど、またブランドに対する印象が良いほど、消費者は安心して購買できます。
では、具体的に消費者が商品やサービスを選ぶ際には、どのような意思決定のプロセスを経て購入し、果てはリピーター顧客となるのでしょうか。
消費者の意思決定は、典型的には以下のプロセスを経ます。
認知 → 興味・関心 → 検討 → 購入 → 体験 → 共有(再購入)
| 段階 | 主な行動 | マーケティングでできること |
|---|---|---|
| 1. 問題認識 | 課題を自覚する(例:空腹、欲しい機能の欠如) | 認知広告・バイラルコンテンツ・トリガー設計 |
| 2. 情報探索 | 検索、レビュー、SNSで情報収集 | SEO、口コミ促進、比較コンテンツ提供 |
| 3. 選択肢の評価 | 価格や性能、ブランドを比較 | 製品比較表、トライアル、保証、口コミ強化 |
| 4. 購入決定 | 購入チャネル・支払い方法を選択 | 購入フロー改善、割引や送料無料の提示 |
| 5. 購入後評価 | 使用感の確認、満足度判定 | アフターサポート、レビュー依頼、LTV施策 |
ブランド連想が働くのは、「認知」から「検討」への橋渡しで、特に「検討に入る直前の瞬間」――すなわち潜在ニーズが顕在化する段階――において、大きく作用します。
以下に具体的にブランド連想が働く段階について例を挙げます。
具体例:
・朝、通勤中に「喉が渇いた」と感じた瞬間 → 自販機で買うかコンビニで買うかの検討が始まる。ここで「缶のお茶=X社」がすぐに頭に浮かべばX社が候補になる。
・子どもの運動会前、靴が必要になった瞬間 → 「子どもの靴=Yブランド」が最初に出てくれば選択肢に上がる。
言い換えれば、ユーザーが課題を自覚した瞬間にブランドが「つながっている」ことが第一想起獲得の鍵です。これには単なる視認認知(認知度)ではなく、「場面・シーン」との結びつきを作るコミュニケーション設計が必要になります。
消費者との「結びつき」をつくるコミュニケーションとして、多くの企業は多大な広告予算を投下して売上拡大を図っているのですが、注意しなければならないのが、一過性の売上拡大に向けたインパクト重視のキャンペーンや広告です。
インパクト重視の広告キャンペーンは、一次的には売上拡大に貢献するかもしれません。しかし、ブランドを育成していくという中長期的な観点からは、ブランド価値を損傷してしまう可能性もはらんでいることを忘れてはなりません。目先の利益ばかりを見ていては、本来目指していたブランドコンセプトとは離れてしまい、ブランド自体の価値を減ずることにもなりかねないのです。


6. ブランド連想を育てる6要素+5要因(統合モデルを深掘り)
この章では、第2章で提示した「ブランド連想6要素」と、第3章で紹介した「パーセプション5要因」を統合して解説します。
| ブランド連想6要素 | 対応するパーセプション要因 | 実務観点 |
|---|---|---|
| ブランドプロポジション | ビジュアル・トーン | 何を誰に、を視覚と言語で明確化 |
| 一貫性 | UX・言語 | 体験と発信を統一 |
| シチュエーション訴求 | コミュニケーション | 文脈ごとの語り口を最適化 |
| タッチポイント最適化 | UX | 接触設計を顧客旅程に合わせる |
| ストーリーテリング | 社会文脈 | ブランドの存在意義を物語化 |
| リーチと関連性 | 第三者評価 | 他者発信による信頼補強 |
両者を同時に設計することで、「意味をもって思い出されるブランド」が生まれます。
この章では、前稿の6要素(プロポジション/一貫性/シチュエーション訴求/タッチポイント最適化/ストーリーテリング/リーチ関連性)を、パーセプション設計の5要因と統合しながら、より具体的な戦略設計視点を強化します。
①ブランドプロポジション × ビジュアル・トーン
第2章で「明確なブランドプロポジション」が重要だと述べましたが、それを 視覚表現(ビジュアル) や 言語トーン に落とし込むことによって、パーセプション要因と連結します。たとえば、プロポジションが「親しみやすさ × 手軽さ」であれば、丸みのあるフォント、やさしい色調、語り口もカジュアルなトーンで統一すべきです。
②一貫性 × 全接点UX・体験整合性
ブランドガイドラインの徹底運用により、どのタッチポイントでも「見た目・手触り・言葉遣い」がブレないようにすることが、パーセプション要因でいう UX体験 と 語調トーン を守ることにつながります。さらに、体験がずれないよう、商品体験・顧客対応・配送体験なども含めて設計しなければなりません。
③シチュエーション訴求 × 言語トーン・ストーリーテリング
場面訴求を使う際、「この場面では○○を使いたくなる」「あなたの~にこたえる」といった言語表現と物語化が、印象設計(語調)を支えます。単に場面だけを打つのではなく、ストーリー+語り口 をもって設計することが、記憶に残る第一想起を生みます。
④タッチポイント最適化 × UX/体験整合性
タッチポイントを洗い出し、UX(使いやすさ・導線)と体験が整合的であるように設計することで、パーセプション要因「UX」への信頼性を高めます。接触体験にネガティブギャップがあると、記憶のアンカリングが崩れてしまうからです。
⑤ストーリーテリング × 社会文脈・価値観訴求
ブランドストーリー、社会的価値観、企業の立ち位置を訴えることで、パーセプション要因「社会的・文化的文脈」と整合します。理念やビジョンを日常的施策に落とし込むことで、単なる商品の延長でない意味づけが生まれます。
⑥リーチ・関連性 × 第三者評価求
露出を最適化する際、メディア掲載・記事レビュー・SNS拡散を絡めて「第三者評価の触点」を作ることが効果的です。つまり、単に広告を出すだけでなく、レビュー記事・口コミ・SNS拡散を得る仕掛けを設計し、連鎖的に評価が伝播する構造をつくります。
このように、6要素と5要因を掛け合わせて設計することで、ブランド連想とパーセプションが両立し、第一想起化がよりコントロールしやすくなります。


7.第一想起を狙うブランディング施策
前章で紹介した統合モデルを踏まえて、第一想起獲得に向けた施策を時期別に具体的に示していきます。
ブランドが顧客の頭の中で“真っ先に思い出される存在”になるには、「どんな場面で」「どんな感情とともに」想起されるかを設計し、段階的に記憶へ定着させていくことが重要です。
ここでは、短期(3〜6か月)/中期(6〜18か月)/長期(18か月〜)の3段階に分けて、第一想起を実現するためのブランディング施策を具体的に解説していきます。
短期(3〜6か月):基礎強化とシーン訴求露出増
まずは、ブランドと生活シーンを強く結びつけることから始めます。
「どんな時にこのブランドを思い出してほしいのか」という“場面の定義”を明確にし、視覚的・言語的に印象づけることが目的です。
(1)場面訴求型広告キャンペーン
・典型的な潜在ニーズ場面(朝・帰宅・休憩など)を選定し、広告クリエイティブを作る
・クリエイティブはビジュアル+コアメッセージ語句を必ず組み込む
・広告媒体はターゲットの導線に近いものから優先(SNS、動画、検索連動など)
(2)シチュエーションキーワードを中心とした検索広告
・ユーザーの「漠然とした悩み・欲求」キーワードを収集(例:「なんか疲れたときの飲み物」「朝の目覚めを助ける飲料」など)
・広告を通してブランド名を露出し、そのキーワードでの検索(認知喚起)につなげる
(3)PRによる場面ストーリー展開
・新聞・Webメディアに「この場面ではこう使われている」というストーリーを提供
・季節・トレンドを絡めて話題化を図る(例:夏の熱中症対策、冬の乾燥対策)
・レビュー記事・コラム投稿依頼など、第三者評価と絡める
(4)ブランドシンボルの露出増加
・ロゴやシンボルマーク(アイコン、図形要素など)を広告・媒体で頻繁に使う
・視覚要素が記憶に残るように、目立つ位置に配置
中期(6〜18か月):連想強化と体験拡張
ブランドの存在を“思い出される”段階から、“共感され、選ばれる”段階へ。
ユーザーとの接点を増やし、ブランドを日常の一部として感じてもらうフェーズです。
(1)場面別コンテンツマーケティング
・SEO視点:場面訴求型ハウツー記事(例:「疲れた午後のリフレッシュ法」)を複数展開
・各記事にブランド名/コアメッセージ語句を必ず含めておく
・内部リンク構造を整えて、ブランドサイト内回遊を誘導
(2)SNS・UGC活用と拡散設計
・ユーザーに「その場面で使ってみた感想投稿」を促すキャンペーンを実施
・投稿された画像・動画をリポスト/拡散
・ハッシュタグ設計、UGCでの語彙統一(例:「#朝リセット」「#リフレッシュタイム」など)
(3)タッチポイント接合点の再設計
・Web → 購入フロー → 梱包 → 開封体験 → サポートまで、一貫性チェック
・例えば、梱包を開けた瞬間にメッセージカード・ブランドカラー調の紙を使うなど、思い出トリガー要素を挿入
(4)レビュー誘導・メディアタイアップ強化
・購入客にレビュー依頼を送る(誘導設計と特典設計)
・業界メディア/専門誌へのタイアップ企画を仕込む
・インフルエンサーとの連携強化で信頼補強
長期(18か月〜):意味深化とロイヤルティ強化
ここからは、「知っているブランド」から「信じられるブランド」へと進化させる段階です。
社会的文脈や価値観と結びつけ、ブランドの“意味”を深化させます。
(1)ブランド理念と社会価値の浸透
・SDGs・社会貢献活動を中長期戦略とし、年次施策として展開
・ブランドがどのような立ち位置・価値観をもつかを明文化・発信
(2)製品改善と体験アップデート
・ブランドプロミス(約束)を元に、製品・サービス機能を改善
・ユーザーからのフィードバックを反映し、次フェーズに反映
(3)コミュニティ育成とブランドアンバサダー制度
・コミュニティ(オンライン・オフライン)を設計
・アンバサダー育成制度、口コミ促進、限定特典を通じてロイヤルティ化
(4)リテンションマーケティング・再利用促進施策
・メールマーケティング/リテンション広告で再利用喚起
・ロイヤルユーザー専用プログラム(特典、会報、限定情報)
(5)継続的パーセプションモニタリングと軌道修正
・定期調査(パーセプション調査)を回し、想起語・印象語を追う
・外部変化(競合・文化・トレンド)を反映し、ブランド表現を適時更新
「第一想起ブランド」になるためには、消費者の頭の中で“カテゴリーの代表”になることです。
そのためには、短期では露出と印象形成、中期では連想と体験の拡張、長期では理念と信頼の深化を意識して積み重ねていく必要があります。
最終的に、ユーザーがある瞬間に「そうだ、○○がある」と自然に思い出す。この状態こそが、ブランドが記憶に根づいた証です。
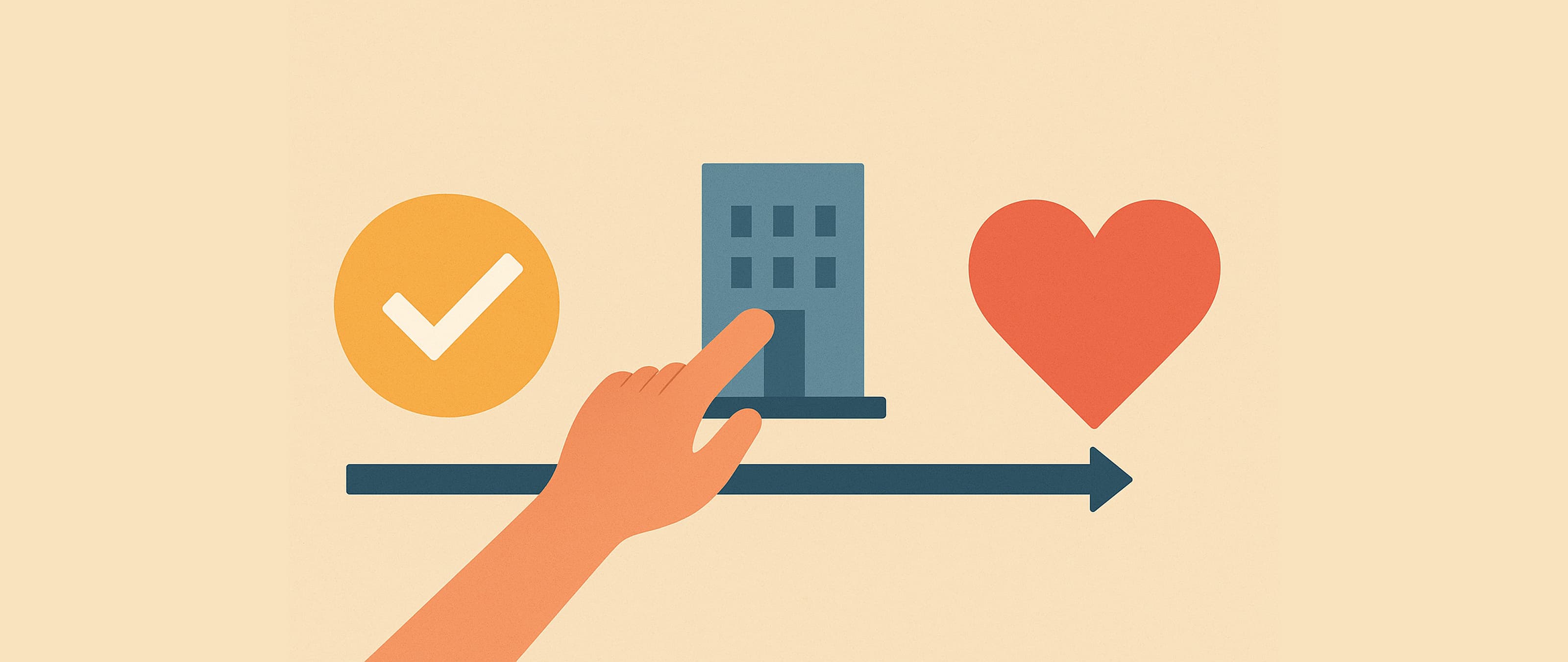
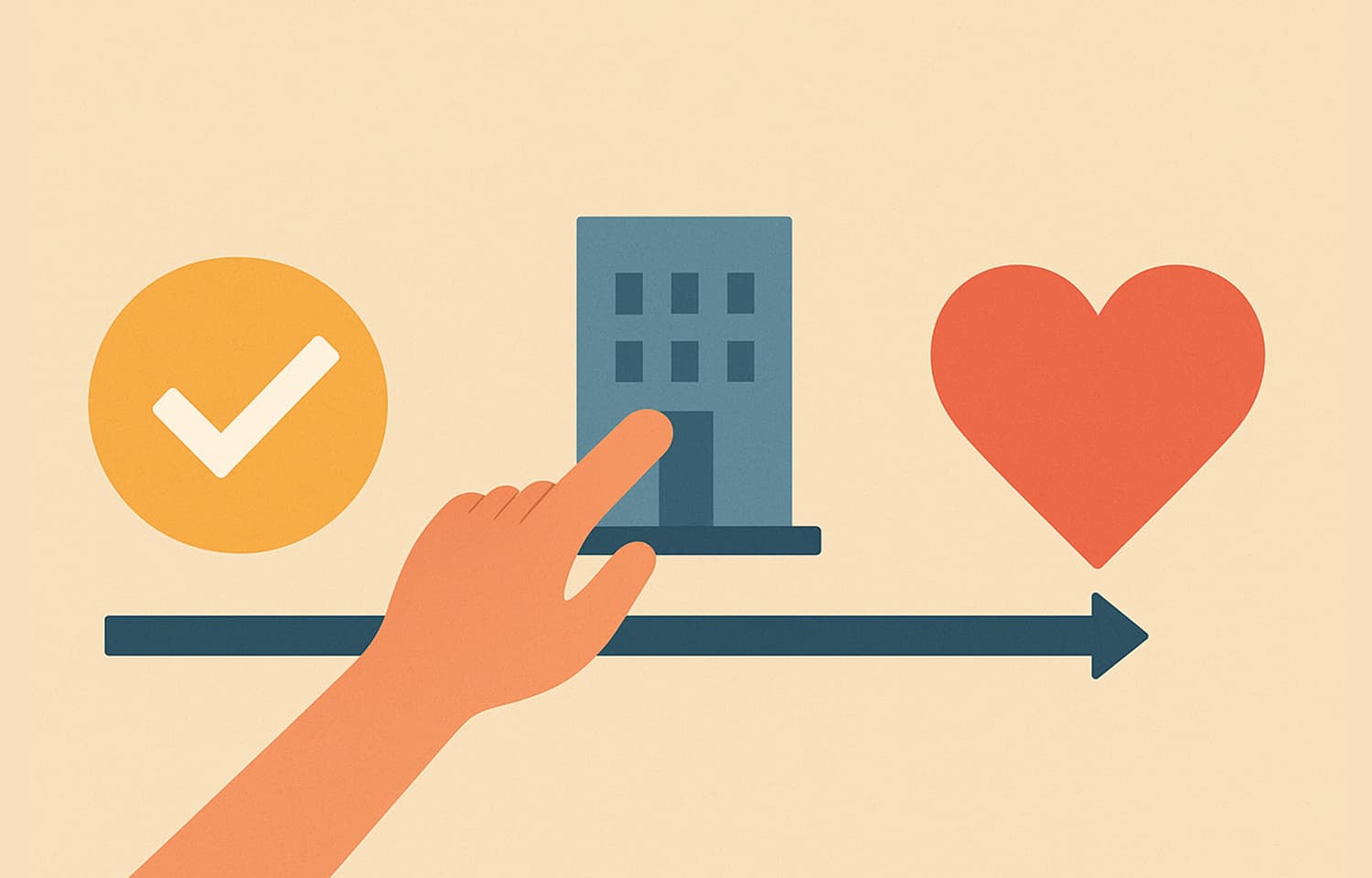
8.「一貫性」と「ブランドロイヤルティ」の関係
『ブランド論−無形の差別化をつくる20の基本原則』の著者で、「モダンブランディングの父」とも称されるデービッド・アーカー曰く、ブランドの一貫性とは、ブランドを継続的に認知さえさせる「何か」であり、視覚的なシンボルや全体的なデザインせいや雰囲気などがそのような一貫性を構成しているとしています。しかし、ブランドとは時代とともに常に変化しているのが実情です。ミッキーマウスやスヌーピーなどを例にしても明らかでしょう。
ただし、変化していない部分があります。それが、ブランドデザインやブランドコミュニケーションの構造です。ここでいう構造とは、ブランドのエレメントとエレメントとの一定の関係。基本的なデザイン構造です。先に取り上げたミッキーマウスやスヌーピーなども、基本的なデザイン構造を維持しつつ、ビジュアルやシンボルを少しずつ変えているのです。
このことからもブランドは短期間で醸成されるものではありませんが、同時に一度醸成されたブランドイメージを覆すことも容易ではありません。そこで、消費者から”誤った認知”を得ないことが重要であり、自分たちが伝えたい/見せたいことに一貫性を持たせ、一貫したブランドイメージを消費者に抱いてもらえるようブランドデザインや広告等を含めた消費者とのタッチポイントを設計し、ブランドコミュニケーションを育てていく長期的視点とプロセスが非常に重要となるのです。
一貫性について理解した上で、ブランドロイヤルティとの関係について紹介します。
・一貫性(Consistency)はブランド記憶の“接着剤”
前述のとおり、視覚や言語表現の一貫性は連想を強くします。人は断片的な情報よりも繰り返される一貫性のある表現を記憶しやすく、誤ったブランド連想を避けられます。
特に 視覚は前述の通り、人間の知覚できる情報の8割を占めているといわれ、記憶への定着から認知へとつながりやすい器官といわれています。そのことからも、多くの企業によって一貫性のあるブランドデザインを繰り返し周知する試みがなされています。
ただし、大規模広告やキャンペーンで一時的に認知を伸ばす際に、ブランドの「語り」と矛盾があると、ブランドパーソナリティとのギャップが生じてしまうことから逆効果になることが指摘されています。
・ブランドロイヤルティ(顧客忠誠度)との接続
ブランドロイヤルティとは、消費者がそのブランドの商品やサービスを使用することで得られる体験価値や感情(情緒的価値)を、ブランドロイヤルティの確立によって、こうした価値を消費者が購買する以前に連想できるようにする状態を目指します。
ブランドロイヤルティの確立は、第一想起が定着した先にある成果の一つです。Top of Mindを獲得して選ばれ続けると、利用回数が増え、再利用意向度や推奨行動(口コミ)が高まるためLTVが上がります。ロイヤルティを育てるには、一貫した体験(期待と提供の一致)が不可欠です。
9.実務チェックリスト
これまでブランド連想、ブランドパーセプション、それらを形づくっている要因やそれらを統合した第一想起に結びつけるブランディング施策や消費者行動を踏まえ、ブランドロイヤリティと一貫性の重要性について紹介してきました。
今回紹介した内容を踏まえて、自分たちのブランドにはブランド連想やパーセプション設計において、いったい何が足りていないのか?を見直すチェックリストを用意しましたので、ぜひ活用してください。
| チェック項目 | Yes / No |
|---|---|
| ブランドの目的・存在意義が社内外で一致しているか |
|
| ロゴ・カラー・トーンが全媒体で統一されているか |
|
| 顧客体験が一貫して快適か(UX・CS含む) |
|
| SNS・広告・Webで共通メッセージを発信しているか |
|
| 第三者発信(レビュー・PR・UGC)を活用しているか |
|
| 社会的テーマとの接続を意識しているか |
|
| 想起率・好意度・利用意向を定期測定しているか |
|
まとめ──「宿るブランド」をつくる条件
ブランディングの本質は、「認知を取ること」でも「広告を打つこと」でもありません。それは、ユーザーの中に“意味の記憶”を育てる行為です。
ブランド連想とパーセプション設計を軸に、接点・体験・物語を丁寧に積み上げていくことで、「思い出される」だけでなく「選ばれ続ける」存在へと進化していくでしょう。
また、「思い出したときに好まれる」こと。それこそが、ブランドが“宿った”状態なのです。
・ブランド連想 は「何を思い出すか」
・ブランド・パーセプション は「どう感じるか」
・第一想起 は「どんな場面で真っ先に浮かぶか」
これら三代要素を一致させるとき、ブランドは単なる商品名を超え、文化的記号として消費者の記憶に定着します。
ブランドづくりとは、広告ではなく「記憶設計」であり、パーセプション設計とは「信頼と好感の文脈をデザインすること」なのです。
参考資料:
・田中洋著『ブランド戦略論』
・日本マーケティング学会『ブランド論再考』
・電通総研「ブランド想起率と購買確率の相関研究」(2024)
・paddle design company 『ブランド価値を左右する「認知度とブランド価値の相関性』
・Zootripper Labo「ユーザーの頭に“ブランド”が宿る瞬間──パーセプションを形づくる5つの要因とは?」(2025年4月)
・Re-DERISE JAPAN 『ブランド連想のメリットと構築する6つのステップ・事例』
・ブランドに関する悩みのほとんどは「パーセプション」に行き当たる
RECENT POSTS

Vol.198
親子関係から地域コミュニティへ──多様性を育み、関係をデザインする教育の未来

Vol.197
ビジョンと多様性、未来志向を組み入れた未来の環境デザインを考える

Vol.196
教育の多様性と未来を拓くビジョンメイキング──環境デザインから読み解く“これからの学び”

Vol.195
「One Health」と日本──人・動物・環境を一体で考える時代へ

Vol.194
AI時代におけるデジタル教育のメリットと課題、教育のこれから

Vol.193
AI時代にこそ必要なビジョンメイキングーーAIが変える“働く意味“と“組織のあり方“











