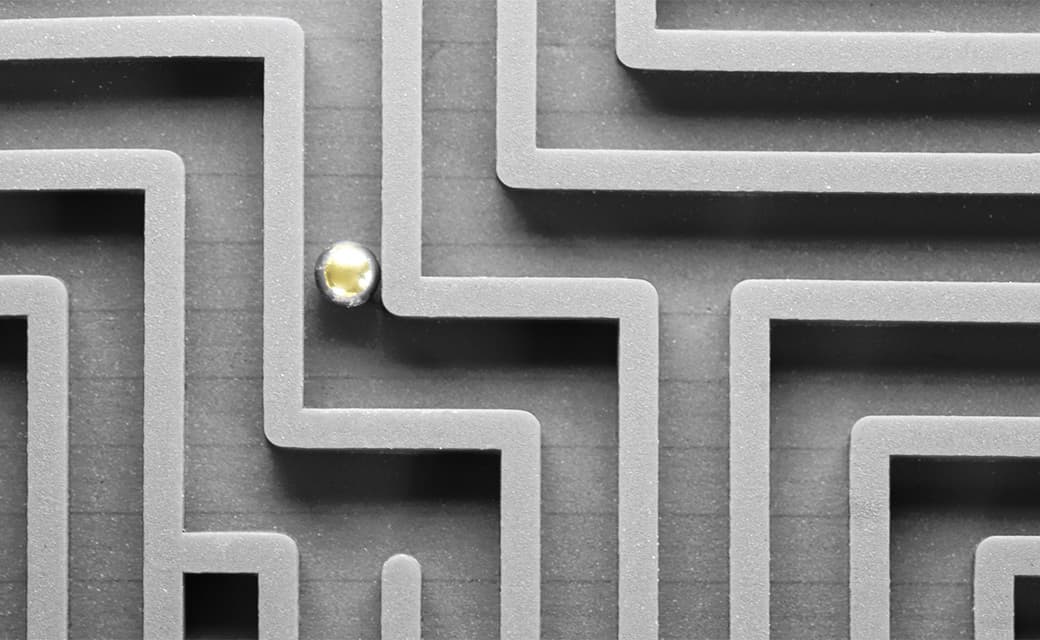ビジョンメイキングの力【後編】─組織とチームの未来を描くビジョンのつくり方
後編である今回は、前編の内容を踏まえて実際にどのようにビジョンを形づくり、日々の活動や経営に活かすのかを紹介します。


1. ビジョンメイキングに欠かせない3つの材料
1-1. ビジョンとミッション、バリューとの相関関係
ビジョンには不可分な関係であるミッションと、バリューがあります。この3つの言葉を総称して合わせてMVPと呼ばれてます。
まず、ミッション(Mission)とは、「組織や個人の存在意義」を示し、「私たちはなぜ存在するのか」「何のために活動するのか」という根本的な問いに答えるものです。時間軸でいうと「現在」に位置付けられ、ビジョンやバリューの基盤となります。
バリュー(Value)は「大切にする価値観・行動規範」を意味します。これは特定の時点に限らず「普遍的に」存在し、日々の行動や意思決定において判断の基準となります。バリューは、ミッションを体現し、ビジョンを実現するために欠かせない行動指針といえます。
ミッション、ビジョン、バリューの相関関係をまとめると以下の図のようになります。
| 項目 | 意味 | 時間軸 | 関係性 |
|---|---|---|---|
| ミッション(Mission) | 組織や個人の「存在意義」「何のために存在するか」 | 現在 | ビジョン・バリューの基盤となる。 |
| ビジョン(Vision) | 将来ありたい姿・目指す未来像 | 未来 | ミッションを実現した先に描く理想像。 |
| バリュー(Value) | 大切にする価値観・行動規範 | 常に | ミッションやビジョンを実現するための日々の判断基準。 |
つまり、ミッションが存在意義を示し、ビジョンが未来への理想を描き、バリューがその実現に向けた行動の規範を支えるという相互関係が成り立っています。これらの3要素が揃うことで、組織や個人は一貫性のあるアイデンティティの軸を持つことができるのです。
1-2. ビジョンを構成する要素
自分たちが目指す未来のあるべき姿・ビジョンを考える上で、最初に用意すべき3つの材料があります。それが以下の図に示す理念、方針、施策です。
・理念(Why)
ビジョンの根幹を成す理念は、「なぜその未来を目指すのか?」という価値観や存在意義を表します。ビジョンの動機づけを担い、組織の方向性を示す「軸」となります。理念は組織においては「心臓部」にあたり、すべての活動の”根拠”となります。
・方針(What)
「なぜ?」の部分である理念を明確にした上で、理念を実現させるために「どのような方向性で取り組むのか?」を示す指針がこれに当たります。ビジョンを実際の行動に落とし込むため、施策の優先順位や判断基準となる部分です。方針は理念を抽象的な理想に留めず、現実の方向性にするための、いわば「地図」となります。
・施策(How)
方針(What)をさらに具体化し、「どのような取り組みを実行するのか?」といったアクションプランに当たるのが施策です。組織やチームのメンバーが日々の活動レベルで実践できる行動指針を提供し、ビジョンを「言葉」→「行動」に移します。
| 要素 | 内容 | キーワード |
|---|---|---|
| 理念(Why) | 自分たちはなぜ存在するのか | 存在意義 |
| 方針(What) | 何を実現したいのか | 方向性 |
| 施策(How) | どうやって実現するのか | 戦略・行動 |
これら3つの要素が揃うことにより、ビジョンは単なるスローガンから「実現可能な未来像」へと進化します。
「理念(Why)」「方針(What)」「施策(How)」の3要素については、サイモン・シネックが提唱したゴールデンサークルの図と符合する点も多いので、より深い理解を得たい方は以下も参考にしてください。
1-3. ビジョンと経営理念の違い
ビジョンについて考えると、「経営理念とはどう違うのか?」と聞かれることがあります。実は経営理念や企業理念、そしてビジョンを混同してしまっているケースがよく見受けられます。経営理念とは、主に企業活動の目的を指し、企業の創業者が自らの事業に込めた思いや価値観、フィロソフィー(哲学)が該当します。「企業理念」という言葉も経営理念と同義のように扱われることがありますが、実は若干の違いがあります。経営理念は時代や外的要因によって変化しますが、企業理念は変化します。企業理念は、創業者の考えや想いを土台にして策定される、いわばDNAのような捉え方です。
経営理念は企業活動自体の目的を指し、ビジョンは会社そのものの将来における「在り方」を示したものだということを理解しておきましょう。
| 項目 | ビジョン(Vision) | 経営理念(Philosophy / Mission) |
|---|---|---|
| 定義 | 将来ありたい姿・目指す未来像 | 企業の存在意義や価値観、経営の基本的な考え方 |
| 時間軸 | 未来志向(5年〜10年先の目標像) | 常に変わらない普遍的な原則 |
| 役割 | 組織が進むべき方向性を明示し、社員や顧客を未来に導く | 企業がなぜ存在するのかを示し、意思決定や行動の根本基準となる |
| 性質 | 変化する可能性あり(時代や環境に合わせて更新) | 不変性が強い(創業以来の精神を引き継ぐ) |
| 具体例 | 「世界中の人々が健康で笑顔あふれる社会をつくる」 | 「人々の健康を守り、社会に貢献する」 |


2. ビジョンマップの作成方法
ビジョンメイキングに必要な材料や最低限の知識を紹介したところで、ビジョンマップの作成方法を紹介します。ビジョンマップを作成することで、理念・方針・施策を経た先の成果イメージを具体化できます。
2-1. ビジョンマップとは?
ビジョンマップとは、組織やチームが描く未来像を「見える化」するためのフレームワークとなります。
理念(Why)のような抽象度合いの高い言葉を、方針、施策、成果イメージへ順序立てて展開することにより、現実的なものにしていくプロセスを指し、抽象的な理念を、行動や計画に落とし込む「橋渡し」として機能します。
この流れを紙やホワイトボードに書き出し、全員で共有することで、頭の中のイメージが具体化されます。
また、思い描く未来を風景画のように一枚に描いてみるのもおすすめします。絵は複雑、かつたくさんの情報をシンプルに一目で伝えることができるので、とても効果があります。
そして、ビジョンマップという一枚の絵の中に、新たに浮かんだアイディアなどをどんどん付け加えていきます。アップデートしたビジョンマップを眺めながら、メンバー同士の対話を深めていくことで、次の活動に関する発想も生まれますし、作成した絵は対外発信する際にも多いに役立つことでしょう。
とはいえ、絵を描くのが苦手な人は次項で紹介する6ステップを参考に、ビジョンを言語化してみることをお勧めします。
2-2. ビジョンマップ活用のメリットと実践ポイント
ビジョンマップを活用するメリットとして代表的なのは以下の4つです。
①頭の中の抽象的なビジョンを共有化できる
→リーダーや経営層だけの頭の中にあった未来像を図解やイラストなど可視化することによって、メンバー全員が同じイメージを持てるようになる。
②行動と理念がつながる
→日々の業務やプロジェクトが、「大きな理念の実現にどう貢献しているのか?」といった具合に長期的視野で可視化されることにより、日々の仕事の意義がより明確になる。
③議論やフィードバックの土台になる
→ビジョンマップを紙やホワイトボードに書き出すことにより、「方針はこれでいいのか?」、「現状の施策は十分に具体的か?」といった問答や対話が促される。
④計画の進捗や整合性を点検できる
→施策が理念や方針からズレていないか?といったことを確認し、組織全体のバランスを再考、調整するチェックツールとしても役立つ。
ビジョンマップを実践し上記のメリットを享受する上で3つのポイントがありますので、以下に挙げておきます。
・可視化すること自体を目的とするのではなく、対話の起点にすること
→一度書いて終わりではなく、定期的に見直し・更新して「生きたマップ」として活用するのが重要です。
・全員参加で作るプロセスが大切
→トップダウンで作成するのではなく、メンバーが意見を出し合いながら作ることで、納得感と当事者意識が高まります。
・短期・中期・長期の時間軸を意識
→施策は短期的に動かせるもの、成果イメージは中長期的に目指すもの、といった時間軸の整理も加えると実効性が増します。


3. ビジョン作成の6ステップ
「ビジョンを持つことが大切」と言われても、具体的にどのようにして作ればよいのか、迷う経営者やリーダーは少なくありません。
単なるスローガンや美辞麗句ではなく、組織や個人にとっての「行動の指針」として”生きるビジョン”を描くためには、段階的なプロセスが必要です。ここでは6つのステップをもとに、実践的な方法を紹介します。
ステップ①:「自分らしさ」の探索
まずは「自分たちらしさ」を探ることから始めます。組織や個人が本当に大切にしている価値観を明らかにすることは、ビジョンづくりの土台です。
例えば「顧客第一」「挑戦」「地域貢献」といった言葉が挙がるかもしれません。しかし重要なのは、その言葉を表面的に並べるのことではなく、「なぜそれが自分たちにとって大切なのか」を掘り下げることにあります。
・顧客とは具体的にどのような人を指すのか?
・顧客は自分たちのどんな価値にお金を払うのか?
・会社の歴史や文化の中で、守り続けたい要素は何か?
こうした問いを重ねることで、企業としての価値観を言語化し、チーム全員で共有する「軸」をつくることができます。
ステップ②:未来の社会を想像する
次に視野を未来へと広げます。この先10年後、20年後の社会はどう変わっているでしょうか。テクノロジーの進化、人口構造の変化、環境問題の深刻化…。さまざまなトレンドを予測することで、未来の風景が少しずつ見えてきます。
未来を考える際には、「外部環境の変化」と「自分たちが望む未来像」の両方を描くことが大切です。現実的な社会変化のシナリオを踏まえながら、「その中で自分たちはどんな存在でありたいか」を言葉にしていきます。これがやがてビジョン・ステートメントへとつながります。
ステップ③:未来における役割を見つける
社会が変わる中で、自分たちはどんな役割を果たせるでしょうか?
たとえば、環境問題が深刻化する未来では「持続可能な社会の実現に貢献する存在」になれるかもしれません。あるいは人口減少社会において「地域に新しい活力を生み出す存在」となる可能性もあります。
「社会の課題解決」と「新しい価値の創造」の両面から、自分たちの役割を定義することが、ビジョンの核心に迫るステップです。
ステップ④:未来の風景を実際に描いてみる
言葉だけでは未来像が抽象的になりがちです。そこで役立つのが「ビジュアル化」です。イラストやストーリーボードを用いて、未来の自分たちや社会の姿を具体的に描き出します。
例えば「10年後の顧客との関わり方」や「未来の街での自社サービスの位置づけ」を図に落とし込むことで、共感が広がりやすくなります。視覚的に共有できる未来像は、メンバーの心に残り、共通の目標意識を育てる力を持っています。
ステップ⑤:未来における自分たちについて語り合う
ビジョンは一人で完結するものではありません。組織にとって大切なのは「共に描くこと」です。
ワークショップやミーティングを通じて、「もしこの未来が実現したら、私たちはどういう存在になっているか?」を語り合いましょう。メンバーの多様な視点や経験を持ち寄ることで、ビジョンは一層リアリティを増し、「自分事」として根付いていきます。
ステップ⑥:アップデートする
最後に忘れてはならないのが「ビジョンは固定化しない」という考え方です。社会や経済の状況は絶えず変化します。それに合わせて私たちの立ち位置も変化を求められます。
だからこそ、ビジョンは定期的に見直す必要があります。年に一度の振り返りや、中期経営計画の策定時などに、現状と未来像を照らし合わせ、必要に応じて修正し更新する。そうした「しなやかな運用」が、ビジョンを単なる額縁の中の言葉ではなく、実際に息づく指針へと育てていきます。
ビジョンづくりは単なる経営課題ではなく、組織の文化をつくる営みです。「自分らしさを探ること」から始まり、「未来を想像し、役割を定め、共に描き、更新し続ける」プロセスを経ることで、言葉に力が宿ります。
本当の意味でメンバーが共感できるビジョンは、会社の道しるべであると同時に、日々の意思決定を支える羅針盤となるのです。


4. 「競争」から「共創」へ。これからの社会におけるビジョンの活かし方と姿勢
ビジョンは作るだけでは意味がありません。日々の経営や事業に落とし込んでこそ価値が生まれます。
ビジョンは単なるスローガンや掲げるだけの標語ではなく、実際の経営や日々の意思決定に「血肉」として浸透させてこそ、初めて意味を持ちます。特に、競争の激しい現代社会においては「生きたビジョン」として機能させることが、持続的な成長と差別化の鍵となります。ここでは、具体的な活かし方と組織としての姿勢を掘り下げてみます。
①日常業務に落とし込む
・KPIとの接続
→ビジョンを「数値目標」にまで翻訳することが重要です。たとえば「地域に愛される企業を目指す」というビジョンを掲げるなら、KPIとして「地域顧客のリピート率○%」「地域イベントへの協賛回数○回」といった形に設定できます。数字に落とし込むことで、社員が「何をすればビジョンに近づけるのか」を理解できます。
・プロジェクト目標への展開
→ビジョンは長期的なゴールですが、それを小さな「マイルストーン」に分解し、各プロジェクトの目標に反映させます。たとえば「サステナブルな社会への貢献」を掲げている企業なら、製品開発プロジェクトにおいて「環境配慮型素材の使用率を○%に引き上げる」という短期的な目標を設定することが考えられます。
②社外との共有
・発信の一貫性
→ビジョンを外部に伝える際は、単なる「言葉」だけでなく「事例」や「ストーリー」と一緒に伝えることで説得力が増します。ホームページには実際の取り組みや社員の声を載せ、採用資料には「なぜこのビジョンを掲げているのか」という背景を加えることで、共感が広がります。
・ブランドとの統合
→ビジョンは企業ブランドの「芯」です。ロゴやスローガンだけではなく、広報活動、広告表現、顧客対応などすべての接点でビジョンが反映されているかを点検し、社外に一貫したイメージを届ける姿勢が求められます。
③人材育成に活かす
・教育プログラム設計
→社員教育のカリキュラムにビジョンを織り込むことで、単なる業務スキルの習得ではなく「なぜこの仕事をするのか」という意義を伝えることができます。例えば「イノベーションを通じて社会を変える」というビジョンを掲げる企業なら、新入社員研修の中に「失敗を恐れず挑戦する文化づくり」をテーマにしたワークショップを取り入れることが効果的です。
・モチベーション向上
→社員は「給料のために働く」のではなく「意義のある目標に向かって働く」ときに、最も力を発揮します。ビジョンを通じて仕事の意味を再確認できれば、日々の業務に対する意欲や主体性が自然と高まります。
④社会的インパクトを意識する
・利益と社会性の両立
→競争社会において「利益追求」だけを目的とした経営は、短期的には成果を上げられても長期的な信頼を失うリスクがあります。むしろ「自社の活動が社会にどんなプラスをもたらすか」を重視することで、顧客・パートナー・地域社会からの支持が得られ、結果的に事業の持続可能性も高まります。
・評価軸の多様化
→たとえば「環境負荷の削減」「雇用創出」「地域活性化」といった社会的インパクトを指標化し、社内で評価対象にすることで、社員の行動も自然と社会価値創出へと向かいます。
競争社会から「共創」社会への移行期にある現在、ビジョンを活かすためには、「掲げる」から「実装する」への転換が欠かせません。日常業務や人材育成にまで浸透させ、社外にも発信し、社会的意義を常に意識することで、ビジョンは組織の羅針盤として機能し続けます。最終的には、企業が「何を成し遂げたいのか」を内外に示すことで、社員の結束と社会からの信頼が同時に得られるのです


5. ビジョンを「ただの言葉」にしないための実務チェック
せっかく作成したビジョンを「ただの言葉」にしないための実務チェック・ガイドを紹介します。自分たちの掲げようとするビジョンを見直してみましょう。
✔︎具体性を持っているか?
— 「誰に」「何を」「どのように」届く未来かを1〜2文で説明できるか。
✔︎測れる要素が入れられているか?
— 定性的でもよいが、追跡可能なアウトカム(影響指標)を設定されている。
✔︎きちんと行動に落とし込みがなされているか?
— 会議・採用・評価など、主要プロセスでビジョン関連項目を必須にする。
✔︎物語化されているか?
— 数値だけでなく、顧客や社員の具体的なエピソードで語れるようにする。
✔︎定期的に検証されているか?
— ビジョンと現場のズレを年1回はレビューし、言葉だけで終わっていないか点検する。
併せて、よくある失敗や注意点に自分たちが該当していないか?についても見直してみるといいでしょう。
<よくある失敗と注意点>
・抽象すぎて行動に繋がらない:美しいが何をすればいいか分からないビジョンは意味が薄い。
・現実と乖離した約束:達成不可能な約束は信用を失う。現実的な道筋と短期的マイルストーンを示す。
・掲げたまま放置:社内に組み込まれていないと、ただのPRに終わる。運用設計が必須。
・硬直化:環境変化により戦術は変わる。ビジョンの核(なぜそれが重要か)は堅持しつつ、手段は適宜更新する。
ビジョンは未来への約束
【前編】(TIPS185)と【後編】(本記事)の2回にわたり、「ビジョンとは何か」という基本的な定義から、その意義・役割、そして実際に組織やチームで形にしていくための方法論までを体系的に解説しました。
振り返ると、前編では、ビジョンの持つ意味や重要性を確認し、組織にどのようなメリットをもたらすのかを整理しました。さらに、経営層と現場の認識のズレや抽象的表現といったビジョン策定に立ちはだかる障壁を明らかにし、そのうえで長期的視点や共感、柔軟性といった「ビジョンを描くうえでのマインドセット」を提示しました。後編の本記事では、実践的なプロセスとして「ビジョンマップ」や「6つのステップ」を紹介し、組織が未来を描くための具体的な道筋を示しました。同時に、ビジョンを単なる言葉に留めず、日常業務・人材育成・社会との共有に活かしていく姿勢の重要性を強調しました。
また、「ビジョンは未来への約束であり、共創のための共有財産である」ということを忘れないでいたいものです。ビジョンを持たない組織は漂流してしまう一方、明確なビジョンを掲げ、実践と更新を重ねていく組織は、仲間や社会の共感を得ながら持続的に成長していくのです。
参考資料:
・『正解がない時代のビジョンのつくり方』:三澤直加著
・『ビジョンの作り方5ステップ 定義や会社で浸透させる方法や事例を解説』:ツギノジダイ、前田健二著
・『一目でわかるミッション・ビジョン・バリュー、そしてパーパス。』:田中安人著
RECENT POSTS

Vol.198
親子関係から地域コミュニティへ──多様性を育み、関係をデザインする教育の未来

Vol.197
ビジョンと多様性、未来志向を組み入れた未来の環境デザインを考える

Vol.196
教育の多様性と未来を拓くビジョンメイキング──環境デザインから読み解く“これからの学び”

Vol.195
「One Health」と日本──人・動物・環境を一体で考える時代へ

Vol.194
AI時代におけるデジタル教育のメリットと課題、教育のこれから

Vol.193
AI時代にこそ必要なビジョンメイキングーーAIが変える“働く意味“と“組織のあり方“