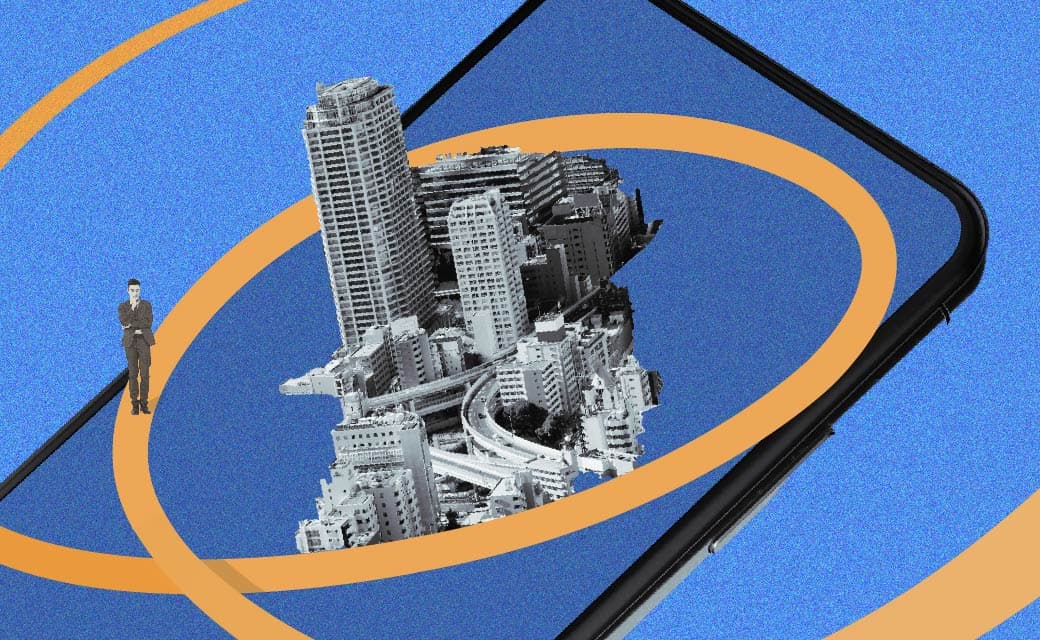デザイン思考とは何か?基礎から進化形まで徹底解説
本記事では、デザインの初心者の方にもわかりやすく、デザイン思考の基礎から最新動向、実践方法までを体系的に解説します。さらに、次世代アプローチであるスペキュラティブ・デザインへの橋渡しとして、なぜ今も「人間中心」の考え方が欠かせないのかを明らかにしていきます。


1. デザイン思考の基礎知識
最初にデザイン思考とはそもそも何なのか?その概念とまた誕生の由来、歴史的経緯について紹介します。
デザイン思考の定義と基本概念
デザイン思考(Design Thinking)とは、ユーザーの視点を中心に置き、創造的かつ実現可能な解決策を導き出すための方法論です。キーワードは「人間中心」。単に見た目を整えるのではなく、人間のニーズや行動パターンを深く理解し、それに基づいた解決策を創造することを目的としています。もともとはデザイナーが製品開発の過程で自然に行っていたプロセスを体系化したもので、今ではビジネスや教育、行政分野でも広く使われるようになっています。
デザイン思考の歴史的系譜と進化
1980〜90年代、製品やサービスは機能・価格競争が主流でした。しかし、2000年代に入るとユーザー体験(UX)が重視されるようになり、顧客の感情やライフスタイルに寄り添う発想が必要になりました。その中で注目されたのが、IDEOのCEOであったティム・ブラウン(Tim Brown)が提唱した「人間中心デザイン」の考え方です。
IDEOとスタンフォード大学dスクールの貢献
デザイン思考は、アメリカのデザインファームであるIDEO(アイディオ)によって提唱され、世界に広まりました。シリコンバレーであるパロアルトを本拠地にして1991年から活動を始め、インターネットの普及や情報化社会への変遷の最中の2000年代前半にデザイン思考が登場することになります。IDEOは世界中の企業と協業し、デザイン思考を用いた革新的な製品・サービスを多数生み出しました。特に先述したIDEOのCEOであったティム・ブラウンは、デザインを「問題解決の方法論」として再定義して、ビジネス界に浸透させました。
その後、デザイン思考はビジネス分野のみならず、教育分野にも広がることとなります。2003年にスタンフォード大学のdスクールは教育機関としてデザイン思考を体系的に学べる場を提供し、多くのイノベーターを輩出。スタンフォード大学にdスクールが開設された背景には、機械工学のうちにデザイン教育の伝統があること、また、IDEO創業者の一人であるデイヴィッド・ケリーが同大学の教授であったことが関係しています。日本では、2009年に東京大学にiスクールが誕生。デザイン以外を専門とする学生やビジネスマンが課題解決、課題発見のアプローチとしてデザインを学ぶ機運が高まりました。
2. ティム・ブラウンの3要素モデルとダブルダイアモンド
IDEOの元CEOであるティム・ブラウンが考えるデザイン思考とは、「デザイナーの発想法から生み出されたイノベーションへの人間中心的アプローチであり、人々のニーズとテクノロジーの可能性、ビジネス成功の条件の統合を図るものである」と定義しています。
三要素モデル
ティム・ブラウンが定義するデザイン思考には3つの指標が関わっているとされています。同時に、イノベーションを成功させるためには以下の3つの要素が重なり合う領域が重要だと述べています。
まず人々のニーズである欲求(Desirability)から始まり、テクノロジー視点である実現性(Feasibility)、ビジネス視点である収益・持続可能性(Viability)があります。
①欲求・ニーズ(Desirability)
→ユーザーや顧客が本当に望み、求めていること。感情や生活の質を向上させる要素。人間中心的な視点。
②実現性(Feasibility)
→技術的に実現可能かどうか。開発リソースやインフラを含む技術・コスト視点。
③事業性・収益性(Viability)
→ビジネスとして成立し持続可能であるか。収益性や持続可能性の経営視点。
これら3つの要素が交わる領域が、持続可能で価値のある解決策、つまりは成功するソリューションの核が存在するとされます。
図1:デザイン思考の3つの指標
ダブルダイアモンドモデル
英国デザインカウンシル(Design Council)が提唱した「ダブルダイアモンド」は、問題解決のプロセスをDiscover→Developへかけて、「発散」と「収束」を繰り返していることを説明しています。この流れは、図3に紹介するデザイン思考の6ステップ(共感→定義→創造→試作→テスト→実装)とも密接に対応しています。
◇第一ダイヤモンド◇
「課題の理解と定義」に関するプロセス(※図2のDiscoverの部分)で、流れとしては、課題(Problem)の探索と定義:発見(Discover) → 収束(Define)という構造になっています。第一ダイヤモンドのゴールは、「解くべき正しい課題や問題を定義すること」です。
・発見(Discover)ではユーザーの状況や課題を幅広く調査します。手法としてはユーザーインタビューや観察調査、データ分析が用いられ、自分たちが思っている課題ではなく、実際にユーザーが直面している隠れたニーズやインサイトを発見することがポイントとなります。
・定義(Define)では、発見(Discover)のフェーズで収集したインサイトを整理し、課題の核心、本質を明確化します。手法としては、ペルソナ作成やカスタマージャーニーマップなどが用いられます。ここでは多様な情報を取捨選択し、チーム全員が納得・合意できる正しい問題・課題設定ができるかがポイントとなります。
◆第二ダイヤモンド◆
解決策の創出と実行に関するプロセス(※図2のDevelopの部分)で、流れとしては、解決策を広く発想する(発散)から再的なものを選び実装する(収束)へと進みます。ここでは、開発(Develop)→ 提供/実装(Deliver)として紹介します。
・開発/創造(Develop)では、第一ダイヤモンドで定義された課題・問題に対して、多様な解決策の候補となるアイディアを生み出していきます。具体的にはブレインストーミングやプロトタイピング、アイディアスケッチやワークショップといった手法を通じて、自由にアイディアをアウトプットしていきます。ここでのポイントは実現性の高さよりも「量」と「多様性」を重視する点です。
・提供/実装(Deliver)まで進むと、出されたアイディアがある程度かたちになっていて、残るは試作や検証を繰り返し、最適解を実装して提供する段階となります。ユーザーテストが行われることが一般的ですが、ここでユーザーの反応を見直し、それを採用していく中で、最終的にユーザーに価値を届ける形に磨きをかけます。提供物がユーザーにとって「価値を生み出す正しい解決策」となっているかを把握することが重要となります。
図2:ダブルダイヤモンドの問題解決プロセス
図3:ダブルダイアモンドモデルとデザイン思考の6ステップとの関係
3. デザイン思考の6ステップ
デザイン思考の枠組みに関して、1.で紹介したスタンフォード・デザインスクールが体系化したプロセスは「共感を生むこと」→「定義すること」→「アイディアを創出する」→「プロトタイプをつくる」→「テスト」と5つの要素の流れを説いています。今回はそれに「実装(Implement)」や「展開(Launch)」を含めた6ステップをご紹介します。
①共感する(Empathize)
ユーザーインタビューや観察を通してニーズを発見することを目的とするフェーズです。コンテクスチュアル・インタビュー、シャドーイングといった観察やエスノグラフィーの実施、カスタマージャーニーマップを作成してターゲットの行動や感情の動き、タッチポイントなどを設計します。ここでポイントとなるのが、平均的なユーザーではなく、極端なユーザーやノンユーザーにも当たることで、調査中のいわゆる”思い込み”を払拭することにあります。
ここでは、ユーザーサンプルの多様性、発見された新規インサイト数、再現性のある観察技術の蓄積を目指しましょう。注意すべきは、最初から解決策について考えるのではなく、事実ベースに情報を収集することです。「こうではないか?」といった調査する側の勝手な思い込みでユーザーを誘導したりせず、オープンな質問を中心に実施すること、また平均的なマスのユーザーの声ばかりに注目するのではなく、極端なユーザー(パワーユーザーからノンユーザー)まで幅広いデータを収集することが重要です。
②問題を定義する(Define)
ユーザーのインサイトやニーズに関する情報データが得られたところで、課題を明確化し、解決の方向性を設定するフェーズに入ります。この段階での目的は、問題を”解ける”形に細分化して、チームで合意した焦点を定めることにあります。このフェーズでは、まず親和図法とも呼ばれるAffinity図法やKJ法を用いたインサイトの収束から始めます。
Affiniy図法とは、大量のデータ(例:インタビュー結果、観察メモやアイディアなど)を意味の近さや類似性(親和性)でグルーピングする手法で、ビジネス現場で「付箋をまとめる」方法として広く用いられています。スピード感があり、実務に馴染みやすく、チームで共通認識を作る場に有効です。しかし、KJ法に比べて「深い構造化」や「文章化による洞察」は弱めです。
KJ法とは、文化人類学者である川喜田二郎氏が開発した「質的データの整理・分析法でAffinity図法ももともとはKJ法をルーツとしています。本来はフィールドワークなど膨大な記述を創造的に構造化するための学術的手法として用いられてきました。Affinity図法よりも手順が厳格で、グルーピング→関係付け→図解→文章化まで行い、より分析・研究よりで深い洞察や仮説の構築を強みとしている点が特徴です。
インサイトを収束する意義は、種々雑多な発見に基づく観察、引用や数値を”意味のかたまり”として凝縮して、問題の本質を炙り出すことにあります。インサイトの収束を経て、問題文の再定義を行います。ここでは以下の流れに沿って、文章にして考えることを重要視しています。
問題文作成の流れ:事実→インサイト→ニーズ→POV→HMW
ここでは、POVとHMWについて例とともに簡単に触れておきます。
POV(Point of view)
まずは、ユーザー視点での”問題・課題の芯”を一文で言い切ることが重要です。書式は、【誰が】、どういった【状況】において、【何に困っている/何ができずに困っている】があります。
(例)図書館の利用体験の改善をテーマとするならば、「小さな子どもを持つ保護者は、子どもが飽きずに過ごす工夫を求めている。なぜなら、図書館を利用したいが、子どもが退屈すると滞在を続けられないことに困っているから」
HMW(How might we…?)
POVをもとに「どうすれば〜できるだろうか?」と解決の探求質問に変換します。「では、どうしていこうか?」といった自問の形式でOKです。
(例)・「どうすれば子どもが飽きずに楽しみながら過ごせる図書館体験をつくれるだろうか?」 ・「どうすれば親が安心して利用できる、子ども向けの学び空間を設計できるだろうか?」
問題文の再定義を経て、効果指標であるとか、制約や前提といった成功基準の明文化をしていきます。注意点は、絞ったつもりの課題をかえって拡げ過ぎてしまったり、問題や課題を抽出するべき段階であるのに、仮説に基づく解決案を混ぜてしまうといったことがあります。このフェーズではあくまでも”問題文”に止めることが重要です。
③創造する(Ideate)
問題や課題がどこにあるのか?を明文化した時点で、ブレインストーミングなどで幅広くアイデアを出す発想のフェーズに入ります。ここでは、多様で大胆な解決案を量と質の両側面から生み出すことを目的としていますので、まずは時間を区切ってたくさん出すことを意識してアイディアを出し、量を担保しましょう。後の工程である発想〜テストで、「何をもって良しとするのか?」といった判断基準で迷わないためにも、合意済みの物差しや基準がアイディア選定やピボット判断の際の衝突を防ぎます。
具体的な方法としては、チームでアイディアを幅広く出す際には、ブレインライティングの手法を用いて大量のアイディアを収集したりしますが、なかなかアイディアが出ずに行き詰まった場合には、クレイジー8Sという、Google Venturesが提唱するアイディア出しの方法も有効かもしれません。A4用紙を8分割にし、各スペースに1アイディアとして8分で8アイディアを出していきます。限られた制限時間内に思考をロックすることで、直感的で奇抜なアイディアに出会えることが強みです。他にもアイディア出しの方法としては、既存の製品やサービスを異なる視線で改良できないか考えるSCAMPERという方法や、イノベーションや新規事業探索の際に向いているとされ、他分野や他業界、他文化をヒントにして新しい発想に変えるアナロジー発想を加えた4つの手法が代表的です。
④プロトタイプを作る(Prototype)
”考えるために”を目的とした試作品を迅速に作り、早期に形にするフェーズです。とにかく最低限でいいので、仮説を可視化して検証可能な状態にすることが目標ですので、まずは低忠実度のものからスタートします。そこから、体験ストーリーボードやサービスブループリントを作成して、リスクの高い仮説から順に”学習のための実験”を設計していきます。サービスブループリントに関して詳しく知りたい方は顧客や従業員の体験を可視化するサービスブループリントをご覧ください。
ここで注意しなければならないのは、作り込み過ぎることです。目的はあくまで”考え学ぶこと”にあります。惜しまず捨てられる粗さで構わないので、まずは仮説を可視化することに集中しましょう。また、価値提案、料金感や導入フローを可視化することも重要です。
⑤テストする(Test)
仮説を可視化するプロトタイプの段階を経て、テスト段階に入ります。このフェーズでは、ユーザーの行動や発言、反応などを通じて仮説の検証をします。ユーザーや関係者からのフィードバックを得て、それを活かすことで、試作段階の商品やサービスにより磨きをかけていきます。手法としては一連のユーザビリティテストやユーザーの理解度や魅力度、価値受容度を測るコンセプトテスト、またLPや広告で受容シグナルを計測するスモークテストと呼ばれる方法も用いられます。注意点は、どのユーザー集団からサンプルを抽出するのかといった点で、身内のターゲット母集団にしたことで偏重したデータになってしまうことや、ユーザーの主観的な自己申告に頼ってしまうことです。ここでは客観的に測れる行動データ(クリック/離脱)を重視するようにしましょう。
⑥実装/展開する(Implement/Launch)
ユーザーテストを繰り返して検証・改善を加えて、いよいよ最終的に市場や現場に導入する実装/展開を迎えます。この最終フェーズでは、テストからの学びをプロダクトやサービスに反映し、現場運用に乗せて価値を継続的に提供していくことが目的となります。本番の運用を見据えた運用手順書の作成、機能フラグの活用はもちろん、組織へのオンボーディングや計測設計のための定義や基盤の作成をしていきます。
最も重要なことは、「作って終わり」にしないことです。せっかくこれまでユーザーの価値に則したプロダクトやサービスを作っても、計測×改善、PDCAのループを切ってしまっては、いつまでもユーザーに支持されることは難しいでしょう。また、製品やサービスを送り出す現場が未整備な状態では、運用段階でつまづくことにもなりかねません。トレーニングや顧客とのコミュニケーションの設計、計画も同時並行で整備していくことが求められます。
実装のその先にある意味と世界観
スタンフォード・デザインスクールが体系化したデザイン思考の6つのステップについて、明快で使いやすい反面、テンプレートとして段階的、また機械的に作業を進めていくと、デザインの本質と少しズレるような感じがするという意見を、アートセンターのアンディ・オグデンや他のファカルティが出しています。どうしても、この枠組みを実践で活用する場合には、各ステップを行ったり来たりすることがありますが、それを恐れないことが成功への鍵です。
デザイン思考の実践を通して得られた洞察・統合作業をもとに創造される「世界観」、製品やサービスに対するユーザーにとっての「意味」、そして「ビジョン」が密接につながっているように考えられます。デザイン思考によって新たに提案された世界観や、その中で創造された製品やサービス、ビジネスモデルが新しい意味をユーザーに与え、それがユーザーシナリオとなっていくのです。
世界観を把握する上で、わかりやすい例を挙げるならば、スタジオジブリとディズニーです。スタジオジブリが描く世界観はディズニーの描く世界観とは異なり、独自性があり想像力豊かなものです。また、ディズニーも独自の世界観や空間の創出に成功していますし、どちらもユーザーにとっては一目でその世界観を捉え、提供される意味を感じることのできる体系となっています。
世界のユーザーの共感を呼ぶ世界観を創出し、その世界に到達するように新しいアイディアを出し、それがブランドにつながっていく。成功しているブランドは、こうしたステップや流れを踏襲しているのです。やはり、そこで鍵となるのは、「共感を生む世界観と意味」でしょう。
4. デザイン思考の進化と未来
これまでデザイン思考の中身や手法に関して紹介してきましたが、デザイン思考は単なる製品開発にとどまらず、組織変革や公共政策、教育分野にも応用され、より複雑で多層的な課題へのアプローチへと進化し続けています。このような背景には、社会が直面する問題が単一の解決策で対応できな「複雑性」が強まっていることが関係しているとされます。
気候変動、人口動態の変化、デジタル化といった課題は、従来型の問題解決プロセスだけでは十分に対応できないため、デザイン思考のさらなる進化と拡張が求められています。そこで、デザイン思考と他分野からの思考プロセスとの融合が注目されています。
サービスデザインやシステム思考といった他手法との融合
デザイン思考が個別の課題解決に強みを持つ一方で、現代の課題はしばしば「サービス全体の体験設計」や「相互に依存するシステム全体の最適化」を必要としています。この点で、サービスデザインやシステム思考との融合が重要性を増しています。
サービスデザインとは、顧客接点全体(タッチポイント)を「サービス・ジャーニー」として捉え、ユーザーがサービスを利用する前後を含めた包括的なユーザー体験を設計する手法です。これにより、デザイン思考で得られたユーザーのインサイトをより実務的な形でサービスに落とし込むことができるようになります。
一方で、システム思考は、複数の要素が相互作用する構造を俯瞰的に理解し、部分的ではなく全体における最適解を目指す枠組みを設計します。例えば、環境問題や都市政策といった規模も大きく複雑な社会課題を扱う際などには、デザイン思考の「人間中心的」なアプローチとシステム思考の「全体俯瞰」というアプローチを組み合わせることが不可欠です。こうすることで、単なる課題解決に終始するのではなく、よりサステナブル(持続可能)な社会システムの設計に寄与します。
スペキュラティブ・デザインへの接続
デザイン思考の枠組みは現状の問題解決に強みを持ちますが、不確実性の高い課題に備える未来志向のアプローチとの接続を試みる動きもあります。その一例が、スペキュラティブ・デザインという考えです。
スペキュラティブ・デザインに関しては、スペキュラティブ・デザイン─デザイン思考のその先へで詳しく紹介していますので、ここでは詳述しませんが、スペキュラティブ・デザインは近未来における技術や社会の変化を前提とした「もしも」のシナリオを提示し、望ましい未来から逆算することで、まだ存在していない課題や問題を探り、発見する手法です。製品やサービスの即時的な開発を目的とはしておらず、より広い視野で社会における価値観であったり、倫理観を再考する役割を担うとされています。
いわば未来へのアプローチであるスペキュラティブ・デザインというアプローチ法にデザイン思考が接続することで、短期的な問題解決と長期的な未来像の検討を往復する「二層的なデザイン実践」が可能となります。つまり、現実の制約を踏まえながら未来の可能性を模索することで、より持続的で倫理的な解決策が生まれるのです。
これからの時代に求められるデザイン思考の姿
デザイン思考は、単なる流行りのビジネス用語ではなく、人間中心の発想で課題解決を行うための方法論として、適用範囲は拡大しています。
AI、IoT、サステナビリティ、社会的包摂などの課題に対し、デザイン思考はますます重要になります。ポイントは「手法」ではなく「姿勢」としてのデザイン思考をいかに根付かせるかということです。つまり、「正しい問いを立てる力」が注目されています。
従来の問題解決方法の多くは、与えられた課題に対していかに効率的に答えを見つけるかが重要視されてきましたが、今日の社会課題は「問題そのものが不明確」であったり、「どの問題を優先すべきか定まっていない」といった特徴を持つケースが多いのです。解決すべき「問題」が不明瞭な状態では、何に取り組んだらいいのかわかりません。そこで、正確に問題を捉えて提起する姿勢がより重視されるようになるでしょう。
デザイン思考の次の段階は、「問いを立てる」ことを基盤とし、さらにスペキュラティブ・デザインを始めとした手法や未来洞察、さらにシナリオプランニングといった手法も併用することによって、不確実性の高い社会においてサステナブルで柔軟な解決策を生み出す視座となることです。
まとめ
デザイン思考は「終わった」手法ではありません。むしろ時代の要請に従って進化を続けています。従来の製品開発やサービス改善の枠を超え、社会課題や未来の不確実性に向き合う枠組みへと広がりを見せています。デザイン思考の理解のためには、まず「三要素モデル(Desirability・Feasibility・Viability)」や「ダブルダイアモンドモデル」といった概念が基礎的な学習の鍵となります。これらは、デザイン思考が単なる発想法でなく、段階的な探求と統合のプロセスであることを示していることがわかるでしょう。
また、デザイン思考の6ステップである、「共感」「定義」「発想」「プロトタイプ」「テスト」「実装」を踏まえることによって、人間中心のアプローチを設計することができます。またデザイン思考の次のステップとして、スペキュラティブ・デザインなど未来志向型の手法と組み合わせることで、現状の問題解決にとどまらない、将来の社会課題や技術の可能性を模索した上での新たな課題発見、問題提起につなげることができます。もはや、デザイン思考は静的な枠組みではなく、未来に向けて拡張可能な「動的な実践」へと変化しているのです。
デザイン思考の本当の姿は、さまざまな分野に適応しながら進化を続ける柔軟な思考法です。そして、その中心にあるのは常に人間の体験と価値です。したがって、これからもデザイン思考は未来を形づくる重要なアプローチであり続けるでしょう。
参考資料:
・九州大学デザイン基礎学研究センター「デザイン思考-Design Thinking」
・デザイン思考の歴史1,2
・英国デザイン・コンシル(Design Council)
・『戦略の創造学 ドラッカーで気づき デザイン思考で創造し ポーターで戦略を実行する』山脇秀樹著
RECENT POSTS

Vol.198
親子関係から地域コミュニティへ──多様性を育み、関係をデザインする教育の未来

Vol.197
ビジョンと多様性、未来志向を組み入れた未来の環境デザインを考える

Vol.196
教育の多様性と未来を拓くビジョンメイキング──環境デザインから読み解く“これからの学び”

Vol.195
「One Health」と日本──人・動物・環境を一体で考える時代へ

Vol.194
AI時代におけるデジタル教育のメリットと課題、教育のこれから

Vol.193
AI時代にこそ必要なビジョンメイキングーーAIが変える“働く意味“と“組織のあり方“