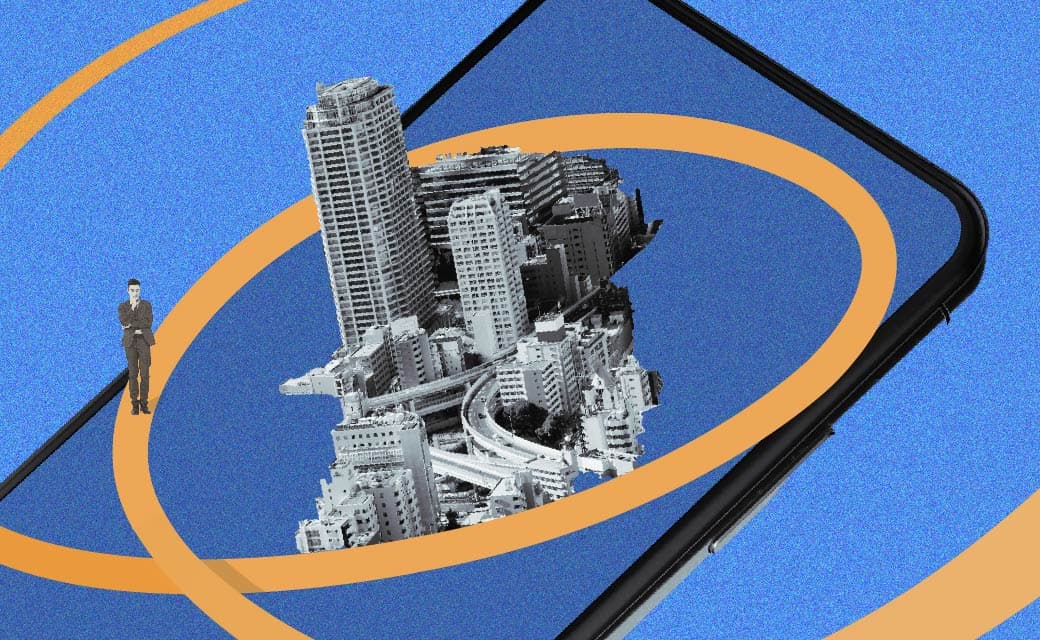スペキュラティブ・デザイン─デザイン思考のその先へ
本記事では、スペキュラティブ・デザインとは何か?その背景、事例、実践方法を初心者にも分かりやすく解説し、「デザイン思考」との違いや相互補完性についても触れながら、未来を創造するデザインの可能性を探ります。


スペキュラティブ・デザインとは?
スペキュラティブ・デザインの定義と起源
スペキュラティブ(Speculative)とは、“思索的な”や“熟考する”といった意味を持ちます。つまり、スペキュラティブ・デザインは、今すぐに使える解決策を提示するのではなく、未来のシナリオや可能性を想像することに焦点を当てたデザイン手法です。
社会的、政治的、テクノロジーや倫理的な問題を探求し、新たなアイディアや解決策を生み出すために用いられています。まさに、未来が「どうあり得るか」をデザインの視点で探ることであり、未来視点で現在をよりよく理解することで、より良い意思決定ができるよう図ることを目的としています。
スペキュラティブデザインは、2009年、英国ロイヤル・カレッジ・オブ・アートで教鞭を取っていたアンソニー・ダン(Anthony Dunne)とフィオナ・レイビー(Fiona Raby)が提唱し、著書『Speculative Everything: Design, Dreaming, and Social Dreaming』で一躍知られるようになりました。
著書内で、”スペキュラティブ・デザインは想像力を源とし、いわゆる“難解な問題”に新たな視点を提供することを目指します。ありうる生き方について議論と対話の場を創出し、人々の想像力を自由に広げることを奨励するのです。デザインによる仮説は、私たちの現実との関係を再定義するための触媒となり得る。”と紹介し、デザイナーは今日の課題に取り組むだけでなく、「将来の課題にどうデザインで取り組めるか」を考える必要があることを説いています。
スペキュラティブ・デザインの目的と特徴、従来のデザインとの違い
現在、デザインと名のつく手法や成果物の範囲や網羅する領域は幅広くなっています。建築などの空間デザイン、ポスターや冊子などのグラフィックデザイン、またWebデザインからユーザー体験をデザインするエクスペリエンスデザインに至るまで、もはや私たちの生活にデザインは密接に関わっている中で、スペキュラティブ・デザインでは、私たちが現在抱えている課題解決の手段としてのデザインの枠を越え、「未来の在り方をデザインする」にまで至りました。
その背景には、新しいテクノロジーの登場や発展に伴い、人間がコントロールできないまでに複雑化した、地球環境の変化や近い将来でさえ予測困難になっている昨今の急速な情勢変化があります。
ここで間違えてはならないのは、この困難な現状の先を予測することが、スペキュラティブ・デザインの目的ではないということです。スペキュラティブ・デザインは未来を予測することではありません。あくまで「現在をよりよく理解する」ために問題提起をして思考を刺激することを目的とした上で、「未来における在り方や可能性」を追求、探求することです。
スペキュラティブ・デザインの基本的な考え方は、将来起こり得る体験やテクノロジー、プロダクトを視覚化し、未来を想像した上で現在を振り返り、未来と現在がどう関係・影響し合っているのか?を考えることにあります。まさに「今を疑い、異なる未来を想像する」、現在抱える問題を未来視点で捉えて、解決策を探ることにスペキュラティブ・デザインの本質があります。
スペキュラクティブデザインの基本
・問題解決ではなく「問題提起」に重点を置く
・テクノロジーと社会の未来に関する“もしも”の世界を描く
・見慣れた日常に違和感を持たせ、思考を揺さぶる
・ユーザーに「選択の余地」を与え、対話を促す
スペキュラティブ・デザインとデザイン思考との違い
スペキュラティブ・デザインの概念が生まれたのは2000年代初頭のことですが、デザインの分野で広く使われる概念にデザイン思考があります。これはある課題に対してデザイナーが取る解決方法であったり考え方を指すものですが、時に顧客のニーズを観察・分析した上で立案した仮説をもとに、プロトタイプを作成してユーザーテストを繰り返しながら商品やサービスを生み出す工程全体を指す場合もあります。
デザイン思考と本記事で紹介しているスペキュラティブデザインには大きな違いがあります。
デザイン思考は「いまの問題をどう解決するか」に照準を合わせる一方、スペキュラティブ・デザインは「そもそも何が問題なのか」を問う視点を提供します。両者は矛盾するのではなく、探索と収束の両輪として活用できます。
| 観点 | スペキュラティブ・デザイン | デザイン思考 |
|---|---|---|
| 時間軸 | 未来志向(5年〜数十年先) | 現在〜近未来(1〜3年) |
| 目的 | 問題を提起し、議論を促す | 問題を解決し、価値を提供 |
| 対象 | 社会、文化、倫理 | ユーザー、ビジネス |
| 問いの姿勢 | 「What if...?」 (もし〜だったら?) |
「How might we...?」 (どうすれば〜できるか?) |
| アプローチ | 仮想シナリオやプロトタイプで未来を表現 | 共感・発想・試作・テストの反復プロセス |
| 成果物の性質 | フィクション性が高い (架空のプロダクトやストーリー) |
実用性が高い (サービスや製品の試作) |
特にデザイン思考とスペキュラティブ・デザインでは、時間軸や目的、問いの立て方が異なる点に注目しましょう。
・時間軸の違い:デザイン思考は「今」、スペキュラティブ・デザインは「未来」
・目的の違い:デザイン思考は「問題解決」、スペキュラティブは「問題提起」
・問いの立て方:前者は「どうやって?(How)」、後者は「もし〜だったら?(What if)」
例:同じテーマを使った場合の違い
テーマ:高齢化社会における移動手段の課題
・デザイン思考:高齢者でも使いやすい自動運転タクシーのUIを設計する
・スペキュラティブ・デザイン :高齢者が「自動運転車と対話して孤独を癒す未来」のプロトタイプをつくる
事例から学ぶスペキュラティブ・デザイン
Dunne & Raby「Foragers(採集者たち)」
「Foragers(採集者たち)」 は、アンソニー・ダン(Anthony Dunne)とフィオナ・レイビー(Fiona Raby)が2010年に発表した作品で、未来の食糧危機をテーマに、遺伝子改変で植物を効率的に摂取できる器具を装着した人々の世界をビジュアル化したプロジェクトです。未来の食料危機をテーマに、都市の人々が「採集者」として進化する可能性を探っています。
プロジェクトの背景と目的
・2050年には人口が90億人を超えると予測され、食糧不足が大きな問題になる。
・遺伝子組換えや大規模農業以外の解決策を探るため、個人レベルでの食糧調達の未来を想像。
アプローチ
・人間が自然環境で食物を採集し、自らの体や道具を通じて加工・消化するという仮想的なライフスタイルを提示。
・「胃の外で消化する」ための携帯用発酵装置や、海藻を効率的に収穫・処理するための器具など、架空の道具や衣装をデザイン。
特徴
・実際に製品化することを目的とせず、「こんな未来もあり得る」という議論を促進。
・デザインを通じて社会や技術の倫理的・文化的側面を問う。
Superflux「Mitigation of Shock」
「Mitigation of Shock」 は、Superflux(アナーシャ・アニャンガ・アンダーソンらによるデザインスタジオ)によるインスタレーション作品で、ロンドンの未来を舞台に、気候変動が深刻化した中での生活、ロンドンの未来の家庭を実寸大で再現しています。自給自足や代替エネルギー、強制的な生活変化を提示し、持続可能性への問いを実際の体験を通して訴えています。
プロジェクトの背景と目的
・近未来における都市生活の現実的な変化(食糧不足、インフラ崩壊など)を可視化。
・抽象的な気候リスクを「今ここにある問題」として実感させる。
アプローチ
・架空のアパートの一室を作り込み、その内部には自作の水耕栽培棚、発電装置、缶詰備蓄、教育用ビデオ、気候対応レシピ本などが整備。
・訪問者はその空間を歩きながら、2050年の「リアルな日常」を体感できる。
特徴
・リアルなプロトタイプを通じて、未来の生活の質感や制約を身体的に感じさせる。
・脱炭素社会やレジリエンス(回復力)についての議論を誘発。
Near Future Laboratory「Design Fiction」
Near Future Laboratoryは、ジュリアン・ブレトン(Julian Bleecker)らによって設立された、スペキュラティブ・デザインの文脈で活動するスタジオです。彼らのアプローチは「Design Fiction(デザイン・フィクション)」と呼ばれ、架空の未来の商品カタログや広告を用いて、あり得る未来を“生活感”とともに描き、現実とのギャップを示しています。
プロジェクトの背景と目的
・テクノロジーの進化に伴う社会的・文化的変化を思考実験的に探る。
・現在の意思決定に影響を与えるような、代替的な未来を視覚化・物質化する。
アプローチ
・架空の製品広告、ユーザーマニュアル、チラシ、ニュース番組などを制作。
・例えば、「スパムメールを物理的に配達する郵便サービス」「未来の自己量子化デバイス」など。
特徴
・「もしこの未来が実現していたら?」という想像を促すドキュメンタリースタイル。
・プロトタイプや映像などのマルチメディア形式を駆使し、観察者に「この未来が現実かもしれない」という感覚を与える。
これらの事例は、いずれも「未来を予測する」のではなく「未来について考えるための装置」としてのデザインであり、政策立案者、企業、一般市民に対して、新たな価値観や選択肢を提示する役割を担っています。
スペキュラティブ・デザインのプロセス
| ステップ | プロセス内容 |
|---|---|
| 1:未来への仮説設定 | 社会的・技術的なトレンドをもとに、仮説的な未来像を描く |
| 2:問いの明確化 | 「この未来において、何が問題となるか?」という問いを立てる |
| 3:フィクションの構築 | プロトタイプ、映像、文章、展示などで“物語”を具現化する |
| 4:対話の設計 | 展示やワークショップ、SNSでの公開などを通じて社会との対話を促す |
スペキュラティブ・デザインのプロセスについてここで触れておきます。一般的なデザインプロセスは、アイデア生成 → 調査 → 発想 → 試作 → テストといった流れで行われるケースが多いですが、スペキュラティブ・デザインではさらに以下の2つの工程が追加されます。
・探索(Exploration):新技術、文化的変化、時事問題などをヒントに未来を探ります。
・視覚化(Visualization):スケッチ、ストーリーボード、プロトタイプなどでアイデアを実体化させます。
大まかな流れとしては以下のステップを踏むことによって、未来から現在への視点を軸にしたデザイン設計がなされます。
ステップ1:未来への仮説設定
社会的・技術的なトレンドをもとに、仮説的な未来像を描く
ステップ2:問いの明確化
「この未来において、何が問題となるか?」という問いを立てる
ステップ3:フィクションの構築
プロトタイプ、映像、文章、展示などで“物語”を具現化する
ステップ4:対話の設計
展示やワークショップ、SNSでの公開などを通じて社会との対話を促す
スペキュラティブ・デザインはどこで活用されているのか?
スペキュラティブ・デザインは実際にどのような場で活用されているのでしょうか。スペキュラティブ・デザインの主な活用場所は、教育機関や企業、また行政機関による公共政策などにも応用されています。
教育現場
美術大学やデザインスクールで未来思考を鍛える教材として利用されている他、未来の職業訓練というワークショップの開催もその一例です。世界経済フォーラムのレポートによると、現在小学校に入学する子どもたちの65%は、今は存在しない職業に将来就くと予想されています。そのことから未来の職業教育のあり方を探る試みの際に、スペキュラティブ・デザインの考え方が取り入れられています。他にも教育現場で様々な活用例があります。
活用例:
・デザイン系大学のカリキュラム
→ロイヤル・カレッジ・オブ・アート(RCA)などでは、Dunne & Rabyが中心となってスペキュラティブ・デザインを教育に組み込んで、「未来の生活様式」や「倫理的ジレンマ」をテーマに学生がプロトタイプやシナリオを制作します。
・STEM教育との融合
→中高教育において、気候変動、AIの倫理、ジェンダーなどをテーマに「こんな未来が来るかもしれない」といった思考実験を行い、生徒の創造性と批判的思考を育む授業が導入されています。
・ワークショップ形式の実践学習
→「2050年の学校」「気候危機後の都市生活」などを題材に、未来のシナリオを構築し、映像、模型、演劇などを使って表現する授業が行われています。
企業・R&D部門
R&D部門とは、企業における研究開発部門を指します。スペキュラティブ・デザインの思考が取り入れられるのは、技術開発の方向性の検証(技術が将来どのような影響を社会に与えることが想定されるか?)であったり、将来の市場や価値観の仮説探索をすることを目的とするケースがあります。自動車業界をはじめ、新しいテクノロジーが社会や消費者にどう受容され得るのか?を検証する際に用いられることが多いでしょう。以下に代表的な活用例を挙げます。
活用例:
・Philips Design – “Design Probes” プログラム
→未来の医療、食、ライフスタイルをテーマに、10年〜20年後の社会を前提としたプロトタイプを開発。これにより、技術的可能性だけでなく社会的インパクトの検討材料を提供しています。
・Google・MIT Media Lab
→デジタルID、AIと人間の共生など、抽象的かつ未来的な課題を可視化するため、スペキュラティブなアートやプロトタイピングを導入。プロダクト開発前の“問い”を設計する段階で活用されています。
・自動車業界(例:Audi、BMW)
→未来のモビリティや、完全自動運転社会におけるユーザー体験を想像し、コンセプトカーやインスタレーション作品として表現。消費者や社内の未来観の共有に活用されています。
行政・公共政策
スペキュラティブ・デザインの考え方は、政策ラボや地方自治体といった行政機関においても市民との未来対話のツールとして活用されている例がいくつもあります。その目的としては、未来政策に対する市民参加の促進であったり、社会的合意形成のため、また公共事業における課題提起とビジョン形成が挙げられます。
活用例:
・イギリス政府「Foresight Programme」
→ 社会保障、環境、テクノロジーの未来シナリオをつくり、政策提言に繋げる取り組み。ここではスペキュラティブな映像やストーリーが使われ、市民との対話を促しています。
・バルセロナ市「Design for City Making」
→市民が参加する未来都市づくりのワークショップに、スペキュラティブ・デザインを導入。未来の暮らしや都市のあり方を市民とともに創造し、行政施策の参考にしています。
・日本国内:国交省や経産省の実証実験
→スマートシティや地域再生プロジェクトにおいて、架空の未来住民のストーリーを用いて合意形成や住民の想像力喚起に活用するケースも増えています。
スペキュラティブ・デザインの限界と未来
これまでスペキュラティブ・デザインについて、その定義やデザイン思考との違い、加えて活用事例などを紹介しましたが、スペキュラティブ・デザインを取り入れる際に押さえておきたい点と可能性について触れておきます。
スペキュラティブ・デザインの限界
未来を想像することを基点とする考え方とはいえ、スペキュラティブ・デザインでは現実的な基盤が不可欠です。現状、または現実に沿わない非現実的なシナリオは意味を持ちません。 例えば、2030年のホテルルームをデザインするとしても、現在存在しない技術だけに依存してはならず、あくまで「実現可能性」を考慮する必要があります。
スペキュラティブ・デザインをする上で、実現可能性を考慮することは不可欠です。未来から現在の課題をあぶり出す上でも、現在の延長線での文脈を検討することが重要です。
スペキュラティブ・デザインの未来
先に教育、企業R&D、また行政分野におけるスペキュラティブ・デザインの活用事例を紹介しましたが、スペキュラティブ・デザインは分野を問わず応用が可能です。技術の進化や社会の変化を読み解き、「もしこの技術が普及したら?」「この傾向が加速したら社会はどうなる?」といった問いを通じて未来を描くことから、今後広範囲の活用が期待されています。
近い将来、例えばAIの倫理課題や、自動運転車が都市や雇用に与える影響、メタバースをはじめとする仮想空間と現実世界の融合などといった分野が今後の探求テーマとなり、スペキュラティブ・デザインを取り入れる可能性が大きいと言われています。
最後に─想像力が社会を変える鍵になる
スペキュラティブ・デザインは、私たちに未来を考える力を提供します。デザイン思考が今の課題にアプローチするツールであるならば、スペキュラティブ・デザインは“私たちが未だ見ぬ問い”に対するセンサーといえます。
また、スペキュラティブ・デザインは創造的思考を刺激し、既存の常識や枠組みを超えてデザインするための強力な方法論でもあります。まだ存在しないプロダクトやサービスを創出したり、既存のモノ、コトを再構築する際に応用できます。
未来は予測するものではなく、対話し、選び取っていくもの。スペキュラティブ・デザインが必要とされている理由がここにあります。
参考資料:
・Anthony Dunne & Fiona Raby, “Speculative Everything” (MIT Press, 2013)
Superflux 公式サイト
・Near Future Laboratory, “「デザイン思考とは何か?」IDEO Japan” (MIT Press, 2013)
・Near Future Laboratory, IDEAS FOR GOOD 「スペキュラティブデザインとは・意味」
・「THE BASICS YOU NEED TO KNOW & UNDERSTAND ABOUT SPECULATIVE DESIGN」:Pradipto Chakrabarty
RECENT POSTS

Vol.198
親子関係から地域コミュニティへ──多様性を育み、関係をデザインする教育の未来

Vol.197
ビジョンと多様性、未来志向を組み入れた未来の環境デザインを考える

Vol.196
教育の多様性と未来を拓くビジョンメイキング──環境デザインから読み解く“これからの学び”

Vol.195
「One Health」と日本──人・動物・環境を一体で考える時代へ

Vol.194
AI時代におけるデジタル教育のメリットと課題、教育のこれから

Vol.193
AI時代にこそ必要なビジョンメイキングーーAIが変える“働く意味“と“組織のあり方“