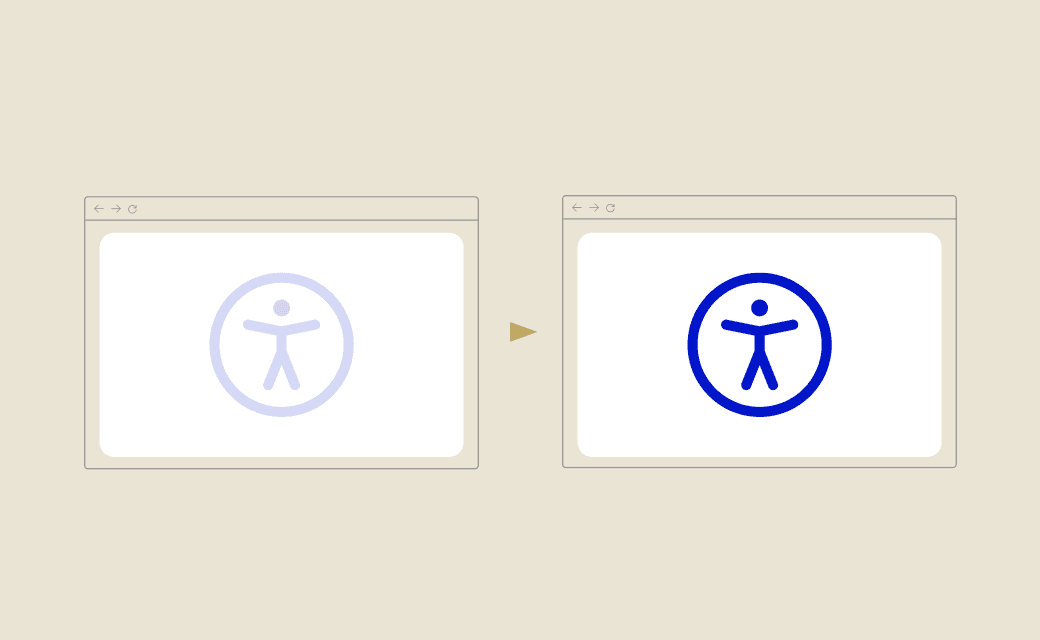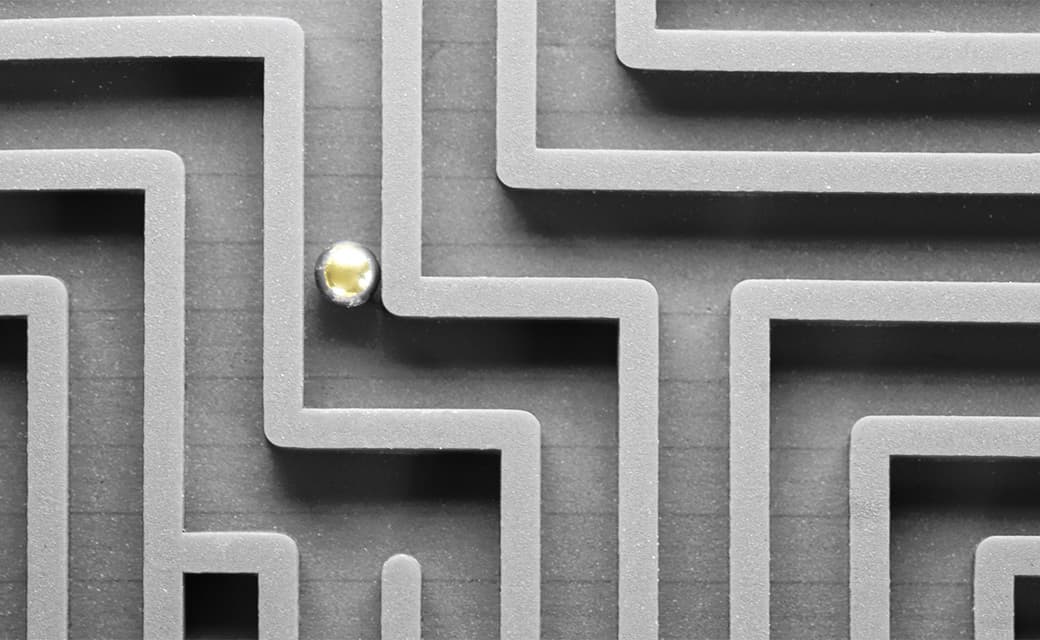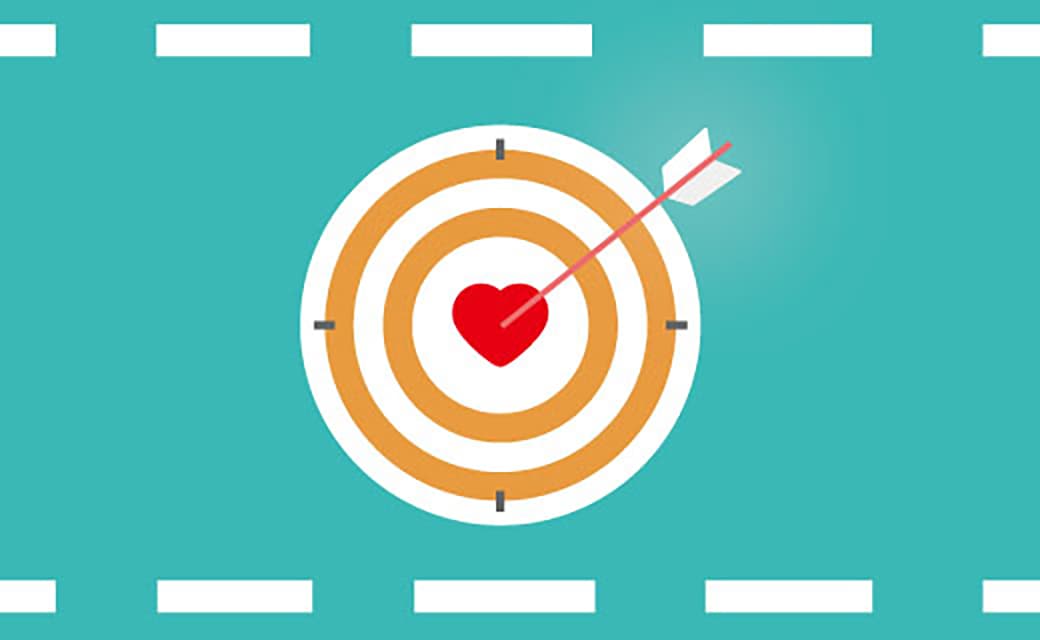企業価値の新常識?サステナブル・ブランディング【前編】
そうした中で、サステナビリティはもはやCSRの一部ではなく、企業ブランディングの核そのものへと進化しつつあります。本記事では、サステナビリティとブランディングの関係を多角的に解説しながら、企業がブランド戦略へどのように統合すべきか、実践的な視点で考察していきます。


サステナビリティはなぜビジネスに必要なのか?
サステナビリティの定義
サステナビリティとは「環境・社会・経済の持続可能性を担保しながら、現在と未来の世代が豊かに暮らせる社会を目指す」考え方です。国連が掲げたSDGs(持続可能な開発目標)の17項目を軸に、企業活動も再設計する流れが加速しています。
国連が掲げるSDGsの17項目(日本ユニセフ協会SDGsクラブより引用)
| 分野 | 主な内容 |
|---|---|
| 環境(Environmental) | 温暖化対策、再エネ導入、省エネ、循環型社会、脱炭素 |
| 社会(Social) | 雇用の多様性、労働環境、人権配慮、地域共生、社会貢献 |
| 経済(Governance) | 公正な経営、ガバナンス強化、情報開示、サプライチェーンの透明性 |
「サステナビリティの3つの柱」は、企業や社会が持続可能な発展を実現するうえで重視すべき**「環境」「社会」「経済」の3つの分野を示しています。これはESG(Environmental, Social, Governance)とも深く関わっており、それぞれの柱には以下のような内容が含まれます。
① 環境(Environmental)
主な内容:温暖化対策、再エネ導入、省エネ、循環型社会、脱炭素
この柱は、地球環境への影響を最小限に抑え、持続可能な自然資源の活用を目指すものです。
・温暖化対策:CO₂などの温室効果ガスの排出削減、気候変動への適応。
・再生可能エネルギーの導入:太陽光・風力・地熱などの再エネを活用し、化石燃料依存からの脱却。
・省エネルギー:効率的な設備投資や運用改善によってエネルギー使用量を削減。
・循環型社会の実現:3R(リデュース・リユース・リサイクル)や廃棄物ゼロを目指す設計・運用。
・脱炭素:製品・サービス・物流などすべての活動でカーボンニュートラル(実質ゼロ)を目指す。
② 社会(Social)
主な内容:雇用の多様性、労働環境、人権配慮、地域共生、社会貢献
この柱は、企業や組織が人々と地域社会に対してどのような影響を与えるかに関わります。
・雇用の多様性(ダイバーシティ):ジェンダー、国籍、年齢など多様な人材の受け入れと活躍支援。
・労働環境の整備:安全で健康的な職場、適切な労働時間や福利厚生の確保。
・人権への配慮:従業員や取引先など関係者の権利を尊重し、不当な扱いを排除。
・地域社会との共生:地元企業や住民との協働・支援を通じた地域活性化。
・社会貢献活動:教育支援、災害支援、ボランティア活動などのCSR(企業の社会的責任)活動。
③ 経済(Governance)
主な内容:公正な経営、ガバナンス強化、情報開示、サプライチェーンの透明性 この柱では、企業の経営体制や意思決定プロセスの信頼性・透明性が問われます。
・公正な経営:不正行為の排除、コンプライアンス(法令遵守)の徹底。
・ガバナンス強化:取締役会や監査機関によるチェック機能の強化。
・情報開示の推進:財務情報だけでなく、環境・社会の取り組み(非財務情報)の開示。
・サプライチェーンの透明性:取引先の選定・監査、人権や環境への配慮を求める責任ある調達。
3つの柱は相互に関連
これらの3つの柱は、独立しているのではなく、相互に影響し合う構造になっています。
たとえば:
・環境への配慮が地域社会の信頼(社会)を高め、経営の評価(ガバナンス)にも寄与。
・サプライチェーンの透明性(ガバナンス)は、人権配慮(社会)や脱炭素(環境)に直結
サステナビリティ経営の重要性
企業を取り巻く外部環境が急速に変化する中、投資家やステークホルダーのサステナビリティへの関心が高まっています。そこで、サステナビリティへの対応が、従来のCSR、社会貢献活動や慈善活動とは異なり、経営課題自体に紐づけられることが多くなりました。つまり、経営の前提条件までが変化しつつあるのです。
サステナビリティへの関心は何も経営的視点からだけではありません。資本市場や消費者市場はもとより、労働市場にも波及しています。
例えば、BAIN&COMPANY「日本とアジア太平洋地域における消費者のサステイナブル意識調査(2022年1月)」によれば、アンケート回答者である消費者の80%以上の人がプレミアム価格を支払ってでもサステナビリティに配慮された製品を購入したいと回答しています。
また労働者市場におけるサステナビリティへの関心の高まりを示す数字として、株式会社IDEATECHが2023年に実施したアンケートで、回答者の20%近くの学生が、就職先企業を選ぶ上で「SDGsに対する姿勢や取組」を挙げている点はこれからの未来動向を予測する上でも注目すべきでしょう。
サステナビリティは経営上はもちろんのこと、企業価値を計る上においても、もはや無視できない重要ファクターとなっているのです。その上で、企業経営の根幹にアプローチする企業ブランディングのあり方も変化していくのは当然の流れでしょう。
サステナビリティは、企業価値の新常識
サステナビリティは、もはや企業の「選択肢」ではなく、「前提条件」です。
企業ブランディングの真の目的は、「誰のために、何のために、どのように存在しているのか」を明示し、社会と共に価値を築いていくことにあります。サステナビリティという視点は、その問いに最も本質的に向き合うための“羅針盤“となるのです。
企業ブランディングとサステナビリティの接点
かつての企業ブランディングは「ロゴ」「キャッチコピー」「広告戦略」など、いわゆる“外見の魅力化”に偏っていました。しかし現代においては、「企業としてどう社会課題に向き合っているか」がブランドイメージそのものに直結しています。
企業ブランディングの新潮流とは?
・企業の存在理由(Purpose)を明確に示すこと
→「Purpose(パーパス)」とは、企業がなぜ存在するのか、何のために社会に価値を提供するのかという存在意義や使命のことです。単なる利益追求ではなく、社会における「役割」や「志」にフォーカスした考え方です。
・環境・社会への貢献を“誠実に伝える”こと
→サステナビリティ、DE&I(多様性・公平性・包括性)、地域貢献などの活動を単に「取り組んでいます」と宣伝するのではなく、正直かつ検証可能な形で開示・共有する姿勢が求められています。”誠実に伝える”とは、①CO2削減量やリサイクル率など客観的な数値で示すこと、②「まだ〇〇といった改善が必要です」と、達成できなかった課題についても共有すること、③第三者認証や認可期間の指標を活用して客観的な情報を盛り込んで伝えることなどを指し、後述するグリーンウォッシングとの違いをきちんと消費者に示す行為ともいえます。
・ブランド体験すべてにおいて一貫した価値観を示すこと
→ブランドは「ロゴ」や「広告」だけでなく、顧客が接するすべての体験の中で形成されるものです。サステナブルな価値観を訴えていても、購入体験・接客・梱包・カスタマー対応などのタッチポイントで矛盾があると、ブランドの信用も失墜します。一貫性が問われる場面としては、商品設計だけでなく、パッケージや店舗運営、顧客対応に至るまで、ステークホルダーとのタッチポイントすべてに行き渡ることが理想とされます。ここでは、「言行一致(ブランドの言っていることと実際にやっていること」に矛盾がないのか?が厳しく問われることになります。
これらを実現するために、サステナビリティの理念をブランド戦略に統合する必要があるのです。
サステナブル・ブランディングとは何か?
サステナブル・ブランディングの定義と特徴
サステナブル・ブランディングとは、「持続可能な社会づくりに貢献する姿勢を、ブランドの中心に据える」アプローチです。見せかけのイメージ戦略ではなく、企業活動全体に根差した本質的な変革が求められます。
| 観点 | 従来のブランディング | サステナブル・ブランディング |
|---|---|---|
| 主な目的 | 製品・サービスの認知拡大、差別化 | 企業の社会的責任と共感による信頼構築 |
| 中心価値 | 品質、デザイン、価格、利便性などの機能的・感性的価値 | パーパス(存在意義)、倫理、環境・社会的貢献 |
| コミュニケーションの主軸 | 商品の特徴や利便性の訴求 | 企業の姿勢、行動、長期的ビジョンの共有 |
| 消費者の役割 | モノ・サービスの「受け手」 | 企業の価値観に共鳴し「共創」するパートナー |
| KPI(評価指標) | 売上、認知度、ロイヤルティ | ESGスコア、LTV、NPS、ステークホルダーの共感度 |
| 持続性の視点 | ブランド寿命=短期的成長中心 | 社会・環境とともに成長し続けるブランド構築 |
従来のブランディングは、企業や商品・サービスの「らしさ」や「魅力」を戦略的に設計し、消費者の心にポジティブなブランドイメージや印象を定着させる活動が一般的でした。アプローチとしても、ロゴ、タグライン、パッケージ、WebサイトのデザインやSNS、広告戦略など、どちらかというと、商品の「機能的価値」や「情緒的価値」をいかに強く印象付けるのか?という点が重要視されていました。
従来のブランディングに対して、サステナブル・ブランディングとは、より社会・環境に重点を置いた戦略設計をします。社会や市場の劇的な変化の中で持続可能な行動、そしてビジョンをブランド体験として伝えるアプローチです。特徴としては、①先述した企業の存在理由(Purpose)がブランドの中心に据えられている点、②ストーリー性と環境や社会への貢献に関する誠実な行動を重視する点③また商品・サービスの機能的価値だけでなく、製造過程や背景、材料やステークホルダーの関わり方への共感であったり価値というものに、より基準が置かれていることです。
つまり、サステナブル・ブランディングとは、「企業としてどう在りたいか」を社会との関係性の中で実践し、その姿勢をブランド資産に変えていく持続可能な経営戦略です。従来のブランディングが“外見(見せ方)”の戦略だったとすれば、サステナブル・ブランディングは“内面(あり方)”の誠実さを軸とした新しい時代のブランド構築です。
ブランド戦略におけるサステナビリティの活かし方
サステナブル・ブランディングの3ステップ
ステップ1
サステナビリティ・パーパスの明文化社会課題と自社事業の接点を明確にし、理念やビジョンに組み込む。
ステップ2
ブランド体験すべてに一貫性を持たせる製品、店舗、社員教育など、あらゆる接点で同じ価値観を示す。
ステップ3
透明性のある情報発信ESGレポートやSNSなどを活用し、定量・定性の両面から継続的に発信。
ここからは、企業がどのようにサステナビリティをブランド戦略に取り込んでいけるのかを、具体的なステップに分けて解説します。
ステップ1:サステナビリティ・パーパスの明文化
企業の理念やビジョンの中に、社会課題と自社の事業との接点を明文化することから始まります。例えば、製造業であれば「循環型社会の実現」、教育事業であれば「学びの機会の公平性」など、事業ドメインに根ざしたサステナビリティの定義が重要です。
ステップ2:ブランド体験すべてに一貫性を持たせる
製品設計、包装材、店舗設計、広告表現、社員教育……すべてにおいてサステナビリティという価値観が一貫していることが、ブランドとしての信頼を形成します。
ステップ3:透明性のある情報発信
どんなに優れた取り組みをしていても、伝わらなければ存在しないのと同じです。企業はESGレポートやWebサイト、SNS等を通じて、定量・定性両面から継続的に情報開示することが求められています。
グリーンウォッシュへの注意と信頼形成
サステナビリティを語る企業が増える中で懸念されるのが、「グリーンウォッシュ」です。
グリーンウォッシュには定まった定義がありませんが、一般的に金融商品、投資戦略、企業が環境や気候にプラスの影響を与える性質や程度について、実態の伴わない環境配慮アピールをすることを指します。企業が自身のビジネスモデルや活動、商品について、実際には環境に害を与える可能性があるにも関わらず、環境に対する影響が正味プラス、もしくは中立であると示唆することです。現在では、グリーンウォッシュは、故意の有無に関係なく行われウルトの考えが広く受け入れられています。
グリーンウォッシュへの対応は、消費者だけでなく世界の多くの金融、また投資家の間でも大きな課題となっています。グリーン性を勘案した投資を好むリテール投資家や機関投資家が市場における存在感を増している背景もあり、グリーン性の真正性や信頼性が投資判断の上で重要な要素となっているからです。見せかけだけのサステナビリティでは、本当の意味でグリーンやソーシャルに資することはありませんし、環境・社会の課題は決して解決しません。
サステナビリティやSDGsを標榜するだけで実態が伴わないグリーンウォッシュに対する執行措置も増加傾向にあります。さまざまな規制当局やアクターが、市場を欺いていると考える企業に対して強制手続きを開始しています。対象となったグリーンウォッシュには、以下のようなものがあります。
①ブランドのグリーンウォッシュ
→組織のプロフィール、活動、や心を全体的にグリーンウォッシュすること
②ファンド商品のグリーンウォッシュ
→商品の不当表示や不当販売
③グリーンウォッシュ資産へのファイナンス
→グリーンウォッシュされた資産に「グリーン」ファイナンスを提供すること
④財務報告のグリーンウォッシュ
→金融機関が環境関連の開示に関して虚偽または誤認を招くような記述をすること
以上のようなグリーンウォッシュに関する課題に関して、世界中の規制当局が注目が高まっています。そんな中で、どのようにグリーンウォッシュと向き合えばいいのか?グリーンウォッシュをいかに回避し、真の意味で信頼を得られるのか?各企業が向き合う必要があるのです。
信頼を得るためには:
・サステナビリティの成果を数値で開示する
→CO2排出量の削減率、リサイクル率、再生可能エネルギー使用比率やサプライチェーンでの改善状況などを具体的な数値で好評、目標(KPI)と実態との差異も明示することで進捗の透明性が高まります。数値による開示は客観性を担保し、また消費者だけでなく、投資家視点においても、ESG投資などの評価基準となります。
・第三者機関の認証や評価を受ける
→B Corp、ISO 14001、SBTi、CDP、EcoVadisといった国際機関によるサステナビリティ認証を取得する、NGOやNPO、研究機関などの第三者評価・レポートを活用して客観的な評価を示します。重要なのは、自社だけの判断による情報ではなく、中立的な立場の評価を入れることです。グリーンウォッシュと疑われるようなリスクの回避にもつながります。
・ネガティブな情報も正直に共有する
→前項でも自社だけの判断による情報だけでなく中立的・客観的評価を入れることの重要性について述べましたが、たとえ、自社にとっては公表したくないようなネガティブな情報に関しても正直に共有することが求められます。サステナビリティの目標の未達成であるとか、環境事故や課題、また反省点を「誠実に」伝えることによって、「透明性」を担保でき、信頼につながります。
グリーンウォッシュは複雑化しており、それに対処する監視機関の規制もこれから先、強化されることが予想されます。本当の意味でのサステナビリティとは何か?環境・社会課題と正面から向き合うことが、これまでより一層、企業やそれに投資する金融機関、投資家や消費者自身にも求められる時代となるでしょう。
最後に
サステナビリティは、もはや企業の「選択肢」ではなく、「前提条件」です。
企業ブランディングの真の目的は、「誰のために、何のために、どのように存在しているのか」を明示し、社会と共に価値を築いていくことにあります。サステナビリティという視点は、その問いに最も本質的に向き合うための“羅針盤”となるのです。
後編では、サステナブル・ブランディングについてさらに深掘りするとともに、具体的な成功事例に関しても掘り下げていきます。
サステナブル・ブランディングは、一朝一夕にできるものではありません。しかし、地道な対話と行動の積み重ねが、企業の未来を拓き、社会との真のつながりを築いていきます。今こそ、より地球環境や社会を見据えた広い視点で自社のブランド戦略を見直し、より持続可能性に秀でたブランドを構築するタイミングです。
参考資料:
・「サステナブルな企業価値創造に向けた サステナビリティ関連データの効率的な収集と戦略的活用(2022.12.13)」:経済産業省経済産業政策局、企業会計室
・「サステナビリティ関連データの 効率的な収集及び戦略的活用に関する報告書 (中間整理)(2023.7.18)」:経済産業省経済産業政策局、企業会計室
・「日本企業における サステナビリティ・SDGs の現状 ~取り組みが開始された日本のサステナビリティ経営~」
・「すべての企業が持続的に発展するために - 持続可能な開発目標(S D G s エスディージーズ )活用ガイド -」:環境省
・「グリーンウォッシュとその回避方法:アジア金融業界向け入門ガイド(日本版)」:AIGCC,ClientEarth
RECENT POSTS

Vol.198
親子関係から地域コミュニティへ──多様性を育み、関係をデザインする教育の未来

Vol.197
ビジョンと多様性、未来志向を組み入れた未来の環境デザインを考える

Vol.196
教育の多様性と未来を拓くビジョンメイキング──環境デザインから読み解く“これからの学び”

Vol.195
「One Health」と日本──人・動物・環境を一体で考える時代へ

Vol.194
AI時代におけるデジタル教育のメリットと課題、教育のこれから

Vol.193
AI時代にこそ必要なビジョンメイキングーーAIが変える“働く意味“と“組織のあり方“