- Vol.184
- DESIGN
- Vol.184
- DESIGN
- 2025.9.19
クリティカルデザインとは何か?──デザイン思考・スペキュラティヴ・デザインとの違い
「デザインは従来の機能的で問題解決の手段の枠を超えて、もっと思考的で挑発的であっていい。」このような動きが20世紀後半から欧米を中心に出てきました。「社会や文化を問い直す思考方法」としてデザインが新たに見直される中で、注目されるアプローチの一つが今回紹介する 「クリティカルデザイン(Critical Design)」 です。
例えば、多くのデザインプロジェクトは「いかに効率的な製品をつくるか」「どうすれば使いやすくなるか」といった実用的な課題を出発点としますが、クリティカルデザインでは、あえて「もしこんな未来が実現したら、私たちはどう感じるのか?」といった問いを立て、社会に議論を投げかけます。
クリティカルデザインとこれまでのデザイン思考との共通点や違い、また近年同じく注目されるスペキュラティブ・デザインとの関係、また初心者にお勧めするクリティカルデザインの実践ステップや方法を事例等を交えながら解説します。
ストラテジック・デザイナー
T.M.

1. クリティカルデザインとは何か?定義と背景
1-1. クリティカルデザインの定義
クリティカルデザインを一言で説明するならば、それは「私たちの価値観や前提を揺さぶるデザイン」です。問題を解決するのではなく、あえて問題を浮き彫りにし、人々に考えるきっかけを与える──この姿勢こそがクリティカルデザインの核心にあります。
この考え方を広めたのが、イギリスのデザインユニット ダンとレイビー(Anthony Dunne & Fiona Raby) です。彼らは1990年代以降、ロイヤル・カレッジ・オブ・アートを拠点に「デザインは社会的批評のための道具になり得る」と提唱しました。
ダンとレイビーはその著書『Speculative Everything』の中で、クリティカルデザインを次のように説明しています。
・日常の慣習や価値観を可視化する
・テクノロジーや制度が持つ潜在的なリスクや矛盾を浮き彫りにする
・未来のオルタナティブ(別の可能性)を考えるきっかけをつくる
また、ダンとレイビーは、デザインを肯定的(アファーマティブ)デザインと批評的(クリティカル)デザインとにカテゴリー分けしている点も特筆すべきでしょう。
”デザインは二つの大きなカテゴリーに分けることができる:肯定的デザインと批評的(クリティカル)デザインだ。前者は、今現在物事がどうあるのかを肯定し、文化、社会、技術、そして経済的な期待に沿うもの。多くのデザインはこのカテゴリーに入る。後者は、現在物事がどうなっているのか拒否し、デザインを通して常識を批評し、代わりの社会的、文化的、技術的、経済的価値を提供しようとするものだ。- Dunne & Raby"
その上で、クリティカルデザインを当初以下のように定義したとも書かれています。
”「クリティカル・デザインは、日常生活における製品の役割についての狭い前提や思い込み、与えられた前提条件を問い直すために、スペキュラティヴなデザイン提案を用いることである」 これは方法論というよりも「姿勢」や「立場」であり、対極にあるのは現状を強化するデザイン──すなわち「アファーマティブ・デザイン」です。- Dunne & Raby”
つまり、クリティカルデザインは、デザインの力によって人々が現状の日常生活に対してクリティカルな見方を持つよう導き、人々に「当たり前」を疑わせることを目指しているのです。
1-2. 発祥と歴史的文脈
クリティカルデザインの起点は1990年代のロンドン、ロイヤル・カレッジ・オブ・アート(RCA) ですが、その思想の背景には、フランクフルト学派(ホルクハイマー、アドルノなど)が唱えた大衆文化と消費文化への批判があるとされます。
1990年代当時のデザイン界は「人間中心デザイン」や「デザイン思考」といった課題解決型のアプローチに注目が集まっていました。
しかし、先に紹介したダンとレイビーはフランクフルト学派とは距離を起きつつも、「デザインが常に企業の利益や消費者ニーズに従属するのは健全ではない」と考え、彼らはむしろ、デザインが「社会批評の手段」として機能できるのではないかと考え、「現状を強化するデザイン(affirmative design)を否定するデザイン(critical design)」を打ち出し、提示しました。
1-3. 実用よりも思考を刺激するデザイン
クリティカルデザインの特徴を端的に表すと、次のようになります。
・使えないデザイン:あえて不便にすることで問題提起
・奇妙なデザイン:日常に違和感を与えることで考えさせる
・未来的デザイン:実現不可能なシナリオを提示して思考実験を促す
こうしたデザインは、マーケティングの現場では役に立たないかもしれません。しかし教育、研究、政策形成、社会活動においては極めて大きな価値を持ちます。
2. クリティカルデザインとデザイン思考の共通点と違い

2-1. デザイン思考とは
クリティカルデザインを理解する上で、多くの人が比較するのが「デザイン思考(Design Thinking)」です。
デザイン思考は、スタンフォード大学d.schoolやIDEOなどによって普及した課題解決型の思考法 で、もともとはデザイナーがプロダクト開発の過程で自然に行っていたプロセスを体系化したものです。
代表的なデザイン思考のプロセスは以下の通りです。
共感(Empathize):ユーザーを理解する
定義(Define):問題を定義する
発想(Ideate):アイデアを出す
試作(Prototype):形にする
テスト(Test):改善する
デザイン思考とのその活用方法に関しては、TIPS181の記事で詳しく紹介しているので、そちらも合わせて参考にしていただくことで理解が深まるでしょう。
2-2. クリティカルデザインとデザイン思考の共通点と違い
クリティカルデザインとデザイン思考の両者はともに「デザインを思考の方法として使う」という点で共通していますが、目的やアプローチは大きく異なります。
【クリティカルデザインとデザイン思考との共通点】
・人間中心の視点を持つ
・現状に対して「なぜ?」と問いを立てることから始まる
・プロトタイピングを通じて思考を具体化する
【クリティカルデザインとデザイン思考の違い】
デザイン思考:課題解決を目的とする。新しい製品やサービスを創出することに重点がある。
クリティカルデザイン:課題解決よりも「問題提起」が目的。答えを出すのではなく、議論や対話を生むことを重視する。
クリティカルデザインとデザイン思考の代表的な違いについて、まとめたのが以下の図になります。
| 項目 | デザイン思考 | クリティカルデザイン |
|---|---|---|
| 目的 | 課題解決・価値創造 | 問題提起・批評 |
| アプローチ | 共感 → アイデア創出 → 試作 → 検証 | 仮想シナリオ → フィクション構築 → 問題化 |
| 成果物 | 製品・サービス・ビジネスモデル | 議論・気づき・社会的対話 |
| ユーザー関与 | 顧客ニーズに基づく | ユーザーの思考を刺激 |
つまり、クリティカルデザインとデザイン思考の大きな違いはその目的にあり、デザイン思考が問題解決型の手段として用いられるのに対して、クリティカルデザインでは、現状では見えていない問題を提起することを目的としています。
また、デザイン思考は「よりよい世界をつくるための実装的手法」であるのに対し、クリティカルデザインは「本当にそれでよいのかと問い直す批評的手法」であるといえます。
3. クリティカルデザインとスペキュラティブ・デザインとの関係
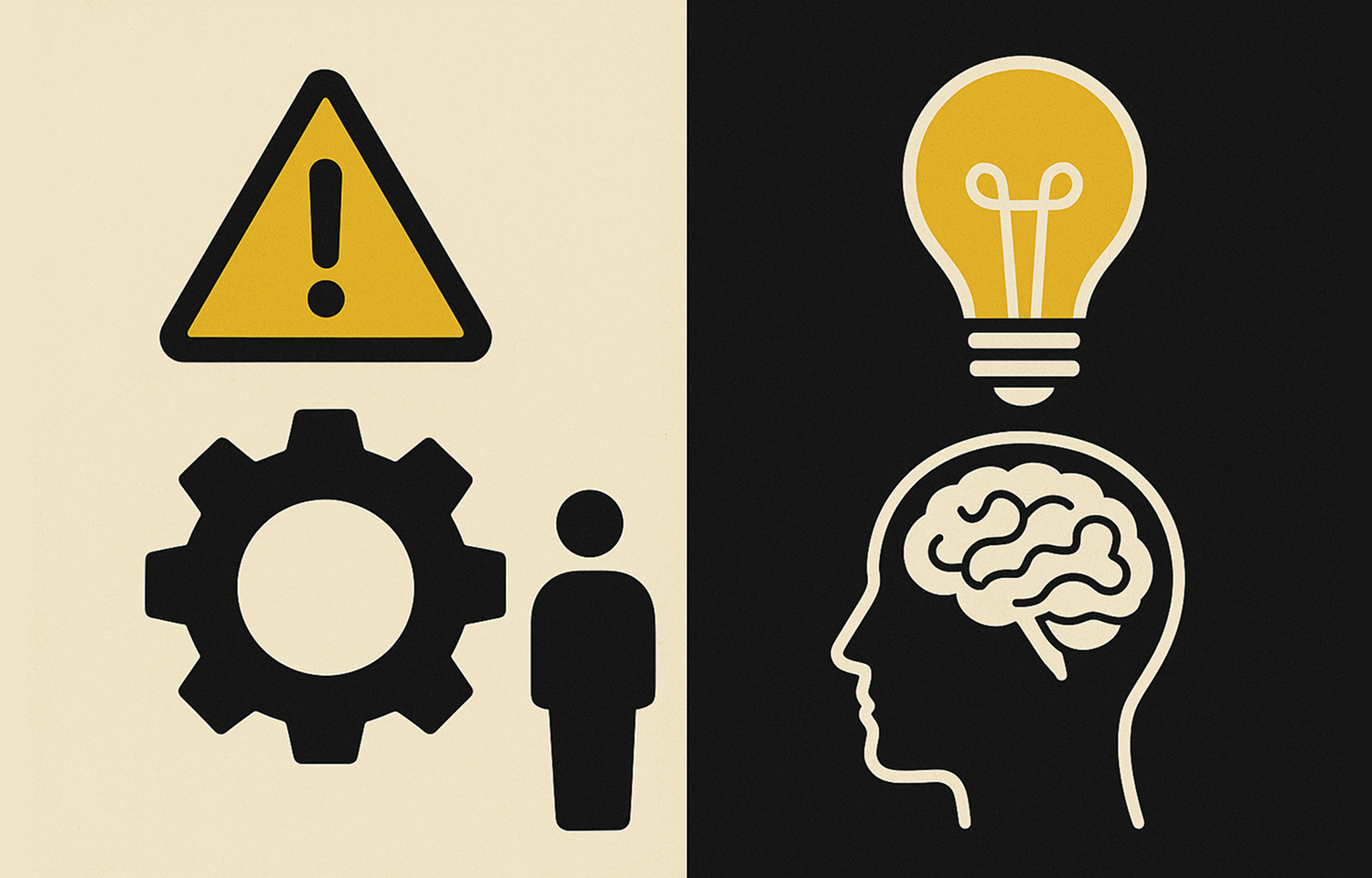
3-1. スペキュラティブ・デザインとは
クリティカルデザインとしばしば混同されるのが スペキュラティヴ・デザイン(Speculative Design) です。スペキュラティヴとは「思索的」、「推測的」、「仮想的」という意味で、未来のあり得る姿を仮想し、それをデザインによって提示する手法を指します。
スペキュラティブ・デザインでは、主に社会的、政治的、テクノロジーや倫理的な問題を探求して、新たなアイディアや解決策を生み出すために用いられています。未来が「どうあり得るか?」をデザインの視点で探ることであり、未来視点で現在をよりよく理解し、より良い意思決定ができることを目的としています。
スペキュラティブ・デザインに関してもTIPS180の記事で詳しく紹介していますので、合わせて読むことで理解がより深まるでしょう。
4. クリティカルデザインの方法論と実践ステップ(初心者向け)

4-1. クリティカルデザインの方法論
クリティカルデザインのアプローチはデザイン思考とは異なり、問いの設定をその目的としていることは先述した通りです。わかりやすいように例を挙げるならば、「都市のインフラ」というテーマが与えられたとします。
デザイン思考でアプローチするならば、「地域住民を始めとするインフラ利用者が心地良く使える電柱の配置方法は?」といった問題設定に向かうところを、クリティカルデザインでは、「もし年のインフラをすべて民間企業が管理するとしたらどうなるだろうか?」、「電線や電柱を全て無くしてしまったらどうだろうか?」など、より具体的で、仮想的な問いの立て方をしていきます。
①問いの設定:「私たちは何を当然と考えているか?」を問う
②仮想シナリオの構築:「もしこうなったら?」を想定する
③プロトタイプ化:物や映像、展示で形にする
④対話の場づくり:議論を促す
つまり、クリティカルデザインでは、より根本的で価値観を揺さぶるような設問を通して、仮想シナリオを策定して、議論を促していく方法がとられます。
4-2. クリティカルデザインの実践4ステップ(初心者向け)
前項で紹介したクリティカルデザインの方法論を基に、初心者にもわかりやすいように具体的な行動を4つのステップにして紹介します。
| ステップ | やること | 具体例 / ポイント |
|---|---|---|
| ステップ1 | 問いを立てる | 例:「AIが人間の感情を完全に再現できたら?」 — 既成概念を疑う問い、倫理や感情に関する観点を含めると議論が深まる |
| ステップ2 | フィクションを考える | シナリオ化し、短いストーリーにする — 主人公・舞台・時間軸を設定し、日常の変化を描く |
| ステップ3 | 形にする | モックアップ、イラスト、動画などで表現 — 物理的プロトタイプや映像で観客の身体感覚に訴えると効果的 |
| ステップ4 | 対話を生む | 展示会やワークショップで意見を集める — 観客の反応を記録し、次の問いに活かす |
ステップ1:問いを立てる(問題意識・テーマ設定)
まずは現代社会や日常における「当たり前」を疑うところから始めます。例えば、AIテクノロジーというテーマを選定したとして、「AIが人間の感情を完全に再現できたら?」といった問いを立てるといった具合です。ここでのポイントは「正解」を探すのではなく、たとえ非常識な内容であったとしても構わないので、あくまで「問い」を立てることが重要です。
ここからリサーチした情報から、既存の価値観や前提を洗い出して、批判的に考察します。「なぜそれが当たり前になっているのか?」を問い直していきます。
(例)SNSというテーマ→「SNSで常に評価される社会は本当に幸せなのか?」
ステップ2:フィクションを考える(仮想シナリオ・世界観の構築)
リサーチした情報をもとに、あえて極端な未来や異常な状態を想像します。そこから、「もし〇〇がもっと進んだら?」であったり、「もし××が禁止されたら?」という仮定を立てます。現実と対比できるように日常とはまるっきり異なる設定にしてみるのがポイントです。
仮想シナリオとして、シナリオ化したり短いストーリーにしてみると、より世界観が深まるでしょう。
(例)SNSの「いいね」文化が人々の自己肯定感やメンタルにどう影響しているのかをリサーチ→「人間の価値が全て”いいね”で決まる社会」という未来シナリオを設定。
ステップ3:形にする(プロトタイプやアーティファクトの制作)
前ステップで作成した仮想シナリオを視覚化・具体化するモノ(アーティファクト)を作成します。よく用いされるのが、モップアップ※1※1製品やWebサイト、アプリなどのデザインを具体的に表現した実物大の模型やサンプルのこと。やイラスト、映像作品などがありますが、形式は自由です。重要なのは、完成度よりも「考えさせる力」や「違和感」を抱かせるようなモノを目指すことです。
(例)「いいね」が多いほど軽くなる服、というコンセプトの衣服を制作。
ステップ4:対話を生む(展示・共有して議論を喚起)
プロトタイプやアーティファクトを、展示会やワークショップなどを通じて観客やユーザーに見せて、反応や議論を引き出します。方法としては、展示会やワークショップの他にも、SNSや論文などという方法もあります。目的はあくまで「これって本当にいいの?」と人々に考えさせることにあることを忘れないようにしましょう。
最後に、展示・共有した結果、議論や反応の内容の振り返りを行います。そして、最初に設定した自分の問いや視点を再考・再検討します。そこで、新たな問いや視点が生まれたら、次のクリティカルデザインへつなげてみましょう。
(例)展示会で作品を見た人に、どんな未来が望ましいのか?をディスカッションしてもらう→「いいね文化を否定するだけでなく、どう付き合っていくのか?を考える必要がある」と気づく→次の問いへ
※1 製品やWebサイト、アプリなどのデザインを具体的に表現した実物大の模型やサンプルのこと。
最後に
クリティカルデザインは、製品を売るためのデザインとは異なり、「社会に問いを投げかけるためのデザイン」といえます。その目的としては、デザイン思考が「問題解決」、スペキュラティブ・デザインが「未来を考えるため」であるのに対し、クリティカルデザインは「批評と対話のため」のアプローチです。
各種のデザインアプローチはその目的は違えど決して対立するものではなく、補完的に組み合わせることによって、より深く・広い視点で未来や社会を考えることができ、新しい視点をもたらすことにもつながるのです。
参考資料:
・Dunne, A., & Raby, F. (2013). 『Speculative Everything』
・Jeffrey Bardzell,SHaowen Bardzell著:『What is “Critical” about Critical Design?』
・『デザイン思考とクリティカルデザインの違い』:Mamiko Yamazaki
・Deer Ozkaramanli,Pieter M.A. Desmet著:『Provocative design for unprovocative designers:Strategies for triggering personal dilemmas』
TAGS
RECENT POSTS
TRENDING
MORE FOR YOU
今日もあなたに気づきと発見がありますように