- BRANDING
- Vol.178
ストラテジック・デザイナー
T.M.
- Vol.178
- BRANDING
- 2025.7.18
ブランド資産を高めるデジタル施策と方法
かつてのブランディングは、テレビCMや雑誌広告などマス媒体を中心とした「広く認知させる」活動が主流でした。しかし、デジタル化が進んだ今、ブランディングの主戦場はオンラインへと移っています。こうした中で、「ブランド資産(Brand Equity)」という考え方が、企業規模を問わず重視されるようになっています。ブランド資産とは、顧客がブランドに対して抱く認知や信頼、感情、体験などの“目に見えない価値”の集合体(無形資産)です。
このブランド資産は、短期的な売上では測れない“長期的な企業価値”につながる重要な指標とされており、とくにデジタル施策との相性が良い点でも注目されています。本記事では、「ブランド資産を高めるにはどんなデジタル施策が有効か?」というテーマで、初心者にもわかりやすく、図解や事例も交えて解説していきます。

ブランド資産とは何か?ブランド価値の向上
ブランド資産とは?
ブランド資産とは、顧客がブランドに対して抱く認知や信頼、感情、体験などの”目に見えない価値の集合体”と冒頭で紹介しましたが、欧米の企業に比べ日本企業は無形資産の中でも特にこのブランド資産が生み出すブランド価値に対する意識が低いことで知られています。
理由の一つに、ブランドは形には見えず、財務諸表にも価値が乗らない非財務資本であり、かつ無形資産であることから投資対象になりにくいと日本企業の経営者たちが考えてきたことが大きな要因でしたが、今やビジネスにおいて非常に大きな影響を及ぼすものであり、もはやステークホルダーにどう認知されるかを含め企業にとって無視できないファクターとなっています。
そこで、まずは「ブランド資産」の正体を理解しておきましょう。
ブランド資産について理解する上で、まずマーケティングの権威ケビン・レーン・ケラーが提唱する「CBBEモデル」をご紹介します。ケラーのCBBEモデルでは、ブランド資産は以下の4つの要素で構成されるとされています。
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| 1. ブランド認知(Brand Awareness) | 消費者がそのブランドを知っているかどうか |
| 2. ブランド連想(Brand Associations) | どんなイメージや意味と結びついているか |
| 3. ブランドの知覚品質(Perceived Quality) | 品質が高いと感じられているか |
| 4. ブランド・ロイヤルティ(Brand Loyalty) | 繰り返し購入・支持するファンがいるか |
以上の4つの要素は相互に影響し合いながら、ブランドの「価値」を形成していきます。
ブランド価値については、これまでBtoC企業では意識されることが多かったのですが、BtoB企業では、経営者をはじめとするトップマネジメントの間においても意識が薄いという現状があります。
ブランド価値を向上させるには?
ブランド価値の向上のための代表的な施策としては以下の5つの方法が挙げられます。
①自社の現状把握
②ブランドステートメントの見直し
③事業領域と提供価値の明確化
④自社が貢献できる領域や方法論の整理
⑤トップから従業員レベルまでの「自分事化」
①自社の現状把握
改めて自社の存在意義や目指す姿を再確認する必要があります。「ありたい姿」が明確であればいいのですが、自社がどのような姿を目指しているのかということが、企業ブランドを明確にする上でも欠かせません。また、「ありたい姿」やパーパスが社内に浸透しているかについても、現状を客観的に捉えておく必要があります。必要に応じて、インナーブランディングなどの施策を講じることを視野に入れる必要があります。過去にインナーブランディングについての記事やブランディングの効果測定に関する記事を公開しています。ぜひ参考にしてみてください。
②ブランドステートメントの見直し
ブランドとは、自社が提供する価値に関するステークホルダーとの約束とも言えます。たとえば、「このブランドなら安心」であるといったブランドへの信頼もそういった約束に基づいています。つまり、自社が社会にどのような価値の提供を約束するのか?がブランドステートメントです。ブランドステートメントを再定義する上で重要なのが、顧客からの期待と認知が自社内における認識と合致しているか?確認することです。過去の成功体験からの期待の変化に気づかずに、旧態依然のブランドステートメントを発信し続けてしまう結果、顧客の期待と自社の自己認識との間に大きなギャップが生じているケースが少なくありません。また、時代と合わなくなってしまったというケースもあります。今一度、顧客からの期待、トレンドと自社の認知にギャップが生じていないか確認しましょう。
③事業領域と提供価値の明確化
ブランド価値を向上させていく上で、自分たちがどの事業領域を得意とし、どのような価値を提供しているのかを定期的に見直すことは必須です。事業領域と提供価値を明確にすることにより、企業ブランドと自分たちの事業のつながりを顧客、社会、従業員に伝える上で重要なメッセージとなります。自社の価値をどの領域で提供するのか、どの事業領域に重点を置くのかを明示して発信することにより、「〇〇(事業領域)といったら△△会社だ」という戦略的ポジショニングにもつながります。
④自社が貢献できる領域や方法論の整理
先行きが見えにくい現代において、自社の事業領域が他社と類似してくることが少なくありません。自社のオリジナリティはどこにあるのか?と不安を感じた際に重要なのが、自社はどうしてこの事業領域に特化しているのか?という問いと向き合うことです。②のブランドステートメントの裏付けをとる上で、他社に対して自社が貢献できる領域や方法論をパーパスに照らし合わせながら整理することが大切です。自社にはどのような特徴があり、強みを持っているのか?技術かもしれないし、顧客に近いところに販路を持っていることかもしれません。自社の強みを言語化し、社内が共通認識として納得している状態が理想です。
⑤トップから従業員レベルまでの「自分事化」
①でも説明しましたが、ブランドは宣伝や広告だけで形成されるものではありません。特にBtoB企業にとっては、従業員一人ひとりの社会や顧客、ステークホルダーとの接点がブランドを形成する従業はファクターです。その上で、ブランドを具体化して、社内にまず浸透させることがキーとなります。
実は企業と顧客との接点は、営業や販売部門だけではありません。人事採用であったり、カスタマーサポートやサービス関連も含まれます。では、それらの従業員にどう自分事化してもらえばいいのか?といった課題に直面することになります。大事なのは、トップだけが語っていても、社内全体への浸透には不十分だということです。トップから経営・マネジメント陣、ミドルから従業員レベルまで、リレー形式で”自社ブランドへの思い”語り継いでいくことが重要です。
2.ブランド資産とデジタル施策の関係性

パタゴニアが実践するサステナブル・ブランディングの施策
デジタル施策とは、企業がデジタル技術・データ、オンラインチャンネルなどを活用して、顧客体験(CX)の創出や改善、マーケティング効率の最大化を図る取り組みを総称したものです。
例としては、SNS運用やデータ分析、AIチャットボットなどが代表的で、「誰に・何を・どう届け・どのように体験してもらうのか」をデータ分析に基づき、設計・実装する点が特徴です。実は、下記に紹介するようなデジタル施策は、ブランド資産にも大きく貢献します。
ここからは、デジタル施策がなぜブランド資産、ブランド価値の向上に貢献するのか?といった理由や施策の具体的な内容について紹介していきます。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| データ取得が容易 | 消費者行動の可視化が可能 |
| 顧客との接点が豊富 | SNS、Web、メールなど多チャネル |
| 双方向のコミュニケーション | リアルタイムに反応・改善が可能 |
| コスト効率が高い | TVなどに比べて少ない予算でも実施可能 |
①双方向コミュニケーションによるブランドロイヤルティの向上
SNSやチャットなど、従来のマスメディア広告の一方的な情報発信ではなく、双方向のコミュニケーションにより、消費者とのインタラクティブな関係性を築くことができるようになりました。そのことにより、消費者の声に即時に対応できることによる信頼や共感の獲得、ユーザー生成コンテンツによる消費者の企画・生産側への参加型経済、競争による「自分ごと化」の促進、また長期的な関係構築によるブランドへの愛着創出などが起こり、ブランドロイヤルティの向上に貢献することになります。
②データの活用によるブランド認知とパーセプションの精緻化
デジタル施策の特徴として、まずターゲットに応じたパーソナライズがしやすいという利点が挙げられます。例えば、収集した行動履歴や購買データに基づいた広告配信により、認知を拡大する精度を高められたり、A/Bテストなどで訴求点を最適化することによって、ブランドの印象(ブランドパーセプション)をより精密に設計することができるなど、データの活用の仕方によってはブランド認知やブランド連想のプロセスを戦略的に組むことができるようになります。
③ストーリーテリングがより簡易に、かつ広範囲に展開できる
ブランド価値はストーリーとして語られることで、より記憶に残ります。SNSや動画発信プラットフォームを通じて、ブランドに込めた想いや、パーパスを可視化して伝えることも有益ですし、何より消費者・ユーザーとの感情的なつながりを築くことこそが、ブランドの意味的な価値をより高めることになり、競合他社にはない自社が選ばれる「理由」や「意味」になるのです。
④ブランド体験(CX)の設計と改善が容易
デジタルツールを用いた施策の利点として、「手を入れやすい」ことが挙げられます。ECサイトやアプリであれば、UI/UXを改善することによってブランドに対する知覚品質の向上が見込めるでしょうし、カスタマージャーニーを可視化し、全体で一貫したブランド体験を提供する上でも、デジタル施策においてはユーザー行動のデータを取りやすい分、よりユーザー視点に寄り添った一貫性のあるブランド戦略が可能となります。また、ブランド資産は「一貫性のある高品質なブランド体験」に基づき向上するため、CX設計・改善が重要なファクターとなります。
⑤成果の可視化と改善スピードの速さ
ブランド施策の効果が数値で見えにくいという課題は多く聞かれますが、デジタル施策においては、KPIや指標(エンゲージメント率、クリック率、リピート率など)で施策の成果をより定量的に把握することができ、効果が出ない場合の改善・最適化の目処を立てやすいことから、ブランドのイメージ毀損やリスクを最小化しやすい点が挙げられます。ブランド資産をコントロールする上でも、何が伸ばせ、どんなリスクが潜んでいるのかといった管理のしやすさも特長といえます。
以上にデジタル施策がブランド資産・価値にもたらす代表的な効果を5つ挙げました。デジタル施策は、ブランド資産の構築、強化、また維持においても極めて高い親和性を持っていることがわかります。企業におけるブランド価値を「資産」として積み上げていくには、感情的なつながり、関係構築、CX設計、データ活用という三位一体の戦略が必要ですが、デジタル施策はそれらに大きく貢献する可能性を有しています。
次章では、ブランド資産を高める具体的なデジタル施策を紹介します。
3.ブランド資産を高めるデジタル施策7選

ブランド資産とデジタル施策の相性に関して理解した上で、具体的にどういったデジタル施策がブランド資産の向上に貢献するのか?について、ここでは具体的なデジタル施策を7つに絞って紹介します。
① SEOとコンテンツマーケティング(認知と信頼を育てる)
背景と意義:
現代の購買行動の多くは「検索から始まる」と言われており、ユーザーが抱える課題や疑問を解決する情報を発信することで、ブランドとのファーストコンタクトを生み出します。特に、BtoB業界や高価格帯商材では、ブランドの信頼性や専門性を示すコンテンツが意思決定に大きく影響します。
実践のポイント:
単にアクセスを集めるのではなく、ブランドの立ち位置や思想が伝わるような記事設計が重要。
「○○の選び方」「失敗しない○○の導入法」など、読者に寄り添ったトピックで入口をつくり、最終的にブランドへの信頼につなげる。
SEOのテクニカル施策(キーワード設計、内部リンク、モバイル対応)も忘れずに。
② SNSブランディング(共感とファン化)
背景と意義:
SNSはブランドの“人間味”を伝える場であり、企業の「価値観」「態度」「社会との向き合い方」など、広告では伝えにくい“空気感”を発信できる重要なチャネルです。アルゴリズムによる拡散性や、ユーザーの参加型行動を活かすことでファン化が進みます。
実践のポイント:
投稿は“ビジュアル+物語性”が鍵。社内文化や開発ストーリーなど、ブランドの裏側を見せることで共感が生まれる。
X(旧Twitter)は速報性、Instagramは世界観、LinkedInは信頼性など、SNSごとの役割とトーンを整理する。
エンゲージメント(いいね、コメント、シェア)を目的にした投稿設計が、アルゴリズム上も有利。
③ UX/UIの最適化(知覚品質の向上)
背景と意義:
ユーザーがブランドに接触する場(Webサイト、アプリ、ECサイトなど)が快適であることは、ブランドの信頼・品質に直結します。どれだけ中身がよくても、見づらかったり、読み込みが遅かったりすると、ユーザーは「粗い印象」を持ってしまいます。
実践のポイント:
LCP(最大コンテンツの表示時間)、CLS(レイアウトの安定性)など、Googleの指標に基づいたパフォーマンス改善が有効。
デザインだけでなく、「目的地に最短でたどり着ける導線設計」や「迷わないナビゲーション」が重要。
ブランドカラーやタイポグラフィも、使いやすさと統一感のバランスを意識する。
④ 顧客レビュー・UGC活用(信頼とリアリティ)
背景と意義:
企業発信ではなく、「第三者の声」が購買や信頼に最も大きな影響を与える時代です。リアルな使用感、体験談、口コミは、ユーザーの意思決定の後押しになります。
実践のポイント:
レビューは「放っておく」ものではなく、返信やリアクションによるエンゲージメントが重要。
SNSに投稿された写真やコメントをWebサイトに埋め込むことで、ブランド体験を立体的に伝えられる。
インフルエンサーの声も有効だが、日常の“ちょっとしたUGC”のほうが親近感があるケースも多い。
⑤ メールマーケティング・CRM(関係性の継続)
背景と意義:
ブランドの価値は、購入時だけでなく「購入後の体験」にも左右されます。メールやLINEによるフォローは、一方的な売り込みではなく、「あなたを気にかけています」という姿勢の表明です。
実践のポイント:
単なる情報配信ではなく、パーソナライズされた内容(誕生日、過去の購入履歴、地域など)で「私だけ感」を出す。
ブランドストーリーや社員コラムなど、商品以外の接点を持つことがロイヤルティに直結。
定期的に配信することで、「存在を忘れられない」工夫も重要。
⑥ ブランドムービー・ストーリーテリング(感情価値を届ける)
背景と意義:
テキストや画像だけでは伝えきれない「情緒的価値」「人の想い」「ブランドの温度感」は、動画によって圧倒的に伝わりやすくなります。共感や感動が生まれやすく、記憶への定着率も高いメディアです。
実践のポイント:
ブランドの起源や価値観を伝える「ミッション系ムービー」は、社員の意識醸成にも活用できる。
顧客インタビューやユーザーのリアルな声を動画にすることで、「ブランドの証言」が強く響く。
SNSで拡散させる際は、短尺+字幕あり+モバイル最適の三点が必須。
⑦ ブランドガイドラインのデジタル整備(全体の統一感)
背景と意義:
デジタル施策が多様化した今、表現がバラバラでは「信頼の低下」や「ブランドの分裂」が起こりやすくなります。統一されたルールを作り、それを関係者全体に共有することが、ブランド価値の安定と成長に不可欠です。
実践のポイント:
ロゴやフォントだけでなく、使う言葉、語尾、対応姿勢(顧客対応やFAQ)まで統一することが理想。
ガイドラインはPDFや印刷物ではなく、常時アクセスできるオンライン形式(Notion、Figma、クラウド)がベスト。
コンテンツ制作者やパートナー企業にも配布し、誰が触れてもブレない表現を保つこと。
以上の7施策は、それぞれが異なるブランド資産の構成要素(認知・連想・品質・ロイヤルティなど)を高めるための役割を担っており、一つひとつを点で取り組むのではなく、ブランド戦略と紐づけて面で設計することが鍵となります。中小企業やスタートアップであっても、リソースに合わせて段階的に取り組むことで、確実にブランド価値の蓄積が可能です。
4. ブランド戦略全体とデジタル施策の接続点
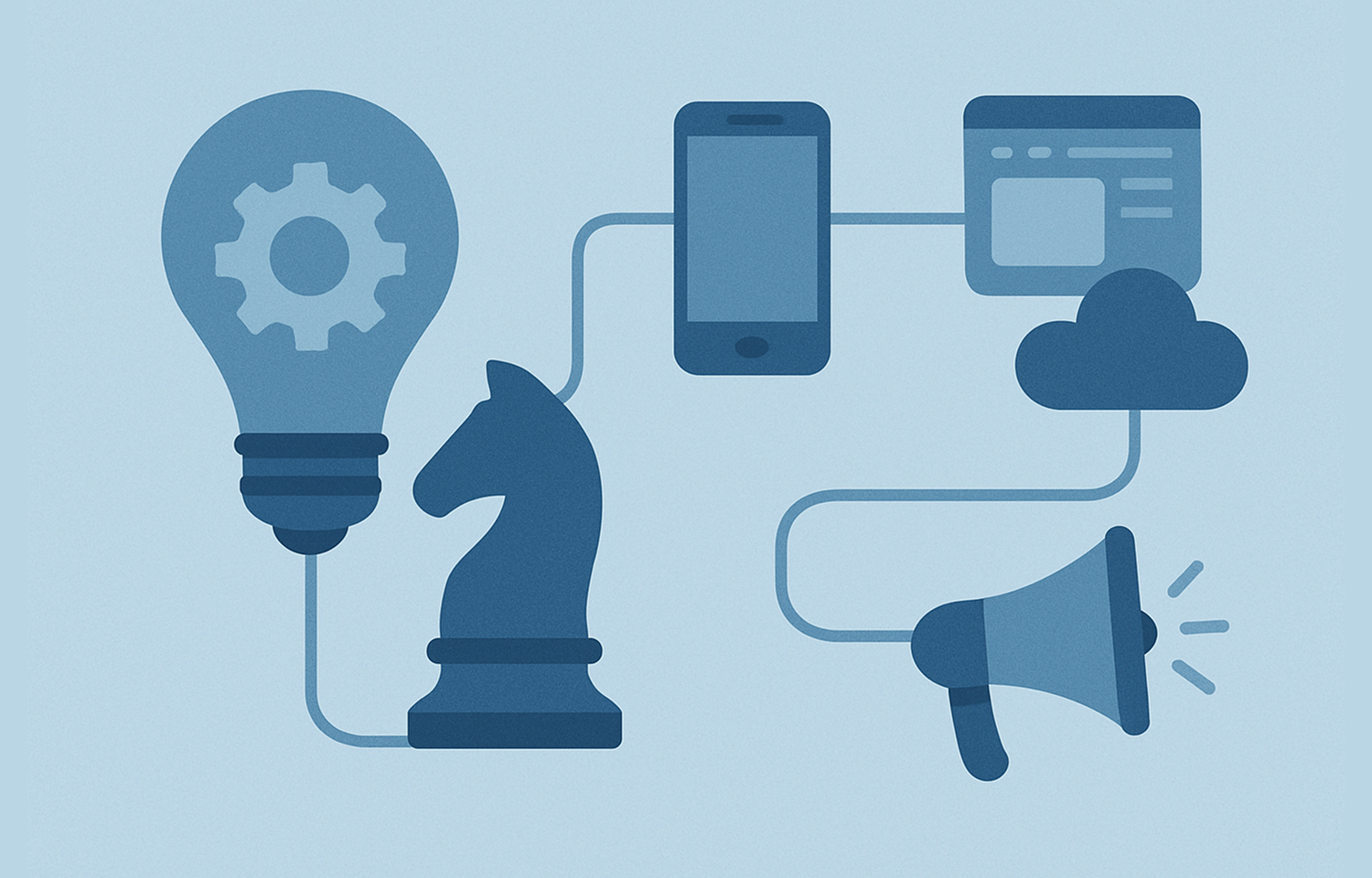
先ほどデジタル施策で代表的なものを7つ紹介しましたが、ここで大事なことをお伝えします。それは、ブランド資産を高めるには、個々のデジタル施策だけでは、不十分であることです。
そもそもブランド資産とは、消費者の記憶・感情・体験の積み重ねによって形成される無形資産であることからも、短期的な施策で終わるキャンペーンでは、一時的な効果しかもたらさないことが多いのです。したがって、時間軸に沿った一貫性のあるメッセージと体験の蓄積することにより、ブランドが強化され、価値が高まっていきます。それにはそれなりの時間と複数の施策が必要になります。つまり、ブランド資産を高めるには、単発のデジタル施策だけでなくブランド戦略全体との整合性が重要なのです。
そこで、デジタル施策とブランド戦略の整合性がもたらす効果について、図表で表したのが以下です。
| 観点 | 整合性のあるデジタル施策 | 整合性がない場合のリスク |
|---|---|---|
| パーパスとの一致 | ブランドの“想い”をコンテンツやUXに反映(例:サステナビリティ思想をUIや配送プロセスに落とし込む) | 企業理念との乖離が生じ、「偽善的」「中身がない」と受け取られる |
| ビジュアル・言語トーンの統一 | SNS、広告、アプリ、接客すべてにブランドの世界観を反映 | 顧客が“別のブランド”と感じ、ブランド認知の定着が阻害される |
| CX全体の設計 | オン・オフ問わずスムーズかつ感情に訴える体験設計 | チャネルごとに体験が分断され、信頼や満足度が低下 |
| KPIの統一と測定 | ブランド価値(NPS、LTV、好意度)にひもづいた評価軸 | 広告のCVRやPVのみで判断し、長期価値が軽視される |
| 部門間連携 | マーケ、開発、営業、CSなどがブランドビジョンを共有 | 施策の重複・矛盾・属人化が起こり、資産の“漏れ”に |
では、「ブランドの整合性」を実現するためには、具体的にどういったアクションプランが必要なのでしょうか? 行動例とともに5つのステップにして紹介します。
ステップ①:ブランドパーパス・価値観の言語化
→例:「テクノロジーで人の感情を豊かにする」が企業のパーパスなら、それをコンテンツやUX、応答の言葉遣いまで落とし込む
ステップ②:CXジャーニーのマッピング
→SNS→Web→購入→配送→サポート→再購入という全体の流れにおいてブランドらしい一貫した体験を設計する
ステップ③:チャネルごとの役割とトーンの統一
→SNSは「共感と対話」、メールは「信頼と案内」、アプリは「パーソナル体験」など
→ ブランドの語り口がチャネルごとに微調整されつつも、共通の世界観を保つことが重要
ステップ④:全体KPIの設計と測定
→各施策に共通指標(ブランド好意度、エンゲージメント、NPS、LTVなど)を設け、短期成果と中長期ブランド価値を両輪で評価する。
→評価方法に関しては、以前の記事でも紹介しています。ぜひご参照ください。
デジタル施策は非常に効果的な戦術」ですが、それを活かすには明確なブランドパーパスや世界観を軸とした「戦略」が不可欠です。整合性が取れた全体設計があってこそ、デジタル施策はブランド資産の“積み上げ”として機能し、単なる一過性の施策ではなく「資産化」されていきます。
5. 最後に
ブランド資産は「広告に費用をいくらかけたか」で決まるものではありません。むしろ、日々の顧客接点の“質”をどう設計するかが問われるます。デジタル施策はその土台をつくるための強力なツールであり、丁寧に運用すれば、企業の信頼と価値を何倍にも高めてくれる存在です。
中小企業やスタートアップにとって、「ブランディング」や「ブランド戦略」は敷居が高く感じられるかもしれません。しかし、デジタル施策を活用すれば、少ない予算でも“ブランド資産”を育てることは可能です。
これからの時代、「何を売るか」だけでなく、「誰から買うか」が選ばれる時代になります。その“誰”を形づくるのが、ブランド資産の力なのです。
RECENT POSTS
TRENDING
MORE FOR YOU
今日もあなたに気づきと発見がありますように